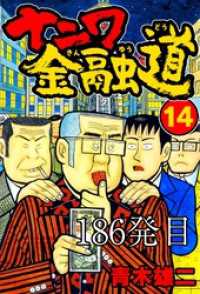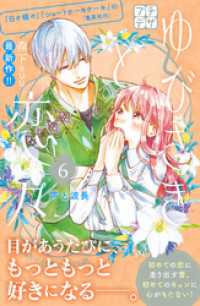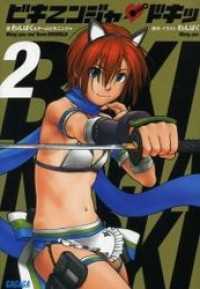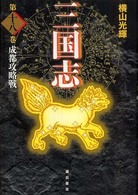出版社内容情報
〔都市生活の社会心理学〕アメリカ都市論研究の第一人者による都市社会論の決定版。豊富な事例とデータにもとづき、都市文化のさまざまな可能性をも示唆するすぐれた概説書。
内容説明
アメリカ都市論研究の第一人者フィッシャー教授による都市社会論の決定版。豊富な事例とデータにもとづき、新しい都市の構造を多面的に描き出した本書は、社会学のみならず行政・都市工学その他あらゆるジャンルからのアプローチが可能なすぐれた概説書でもあり、都市文化のさまざまな可能性を示唆している。
目次
第1章 序説 本書の概観
第2章 都市生活のイメージ―通俗的見解と社会学理論
第3章 都市生活―物的環境
第4章 都市生活―社会的環境
第5章 都市の社会集団―第二次集団
第6章 都市の社会集団―第一次集団
第7章 都市における個人―心の状態
第8章 都市における個人―パーソナリティと行動
第9章 メトロポリスの内部―都市と郊外体験
第10章 都市の未来―結論、予測、政策
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
いたま
1
都市社会学の代表的な分析視点の一つである下位文化理論の中心的書籍。下位文化理論は都市化を人口の集中から説明し、大雑把に言えばコミュニティの規模が大きいのであればそれだけ多様な人間がおり、珍しい嗜好でも支えられる人口があるという論である(少ない割合でもかける数が大きければそれなりに影響力をもつ大きな数になる)。著者の提示する論点は簡明だが、本書は旧来の俗な都市観に丁寧に論駁するものであり、シカゴ学派・ジンメル的な都市の見方を尽く覆していく。また黒人差別に関わる地域格差の問題にそれと知らずに迫っている。2021/07/30
いまにえる
1
都市と村落の住民の違いはどのようなものがあるのかを理論的に説明した本。参考文献もきちんとその都度明記されていた。この本では都市を住民の数が多い町と定義しているが、そのような単純な定義でも案外説明可能なことは多いのだなと思った。「小さな町の住民は、より民族的な偏見を持っているが、大都市の住民は実際により敵意に満ちた民族間の出会いを体験している。かくして、民族的な疑心と不信は、アーバニズムとともに、増加する傾向にある。」この一節はなかなか興味深いと思った。もっと都市について学びたいと思った。2018/03/07
佐藤あき
0
初学者にもたいへん読みやすい、都市の社会学のいろいろな範囲について書かれたすばらしい本でした2025/05/23
SQT
0
都市における人びとの逸脱的なふるまいを、シカゴ学派(や大陸の初期の社会学)は第一次集団の規範が薄くなってきたこによるアノミー状態から見てきたが、フィッシャーはこれを下位文化内の規範に成員が従ったためとする下位文化理論を唱える。この下位文化は農村では、そもそもの人口数が少ないために顕在化されなかったが、都市にはコミュニティを形成できるほどの人口(臨界値↑)がいるため、この「逸脱的な」下位文化のコミュニティが生まれる。また、下位文化はそのほかの下位文化と接することによって自身の独自性を強化する傾向にある。2018/10/06