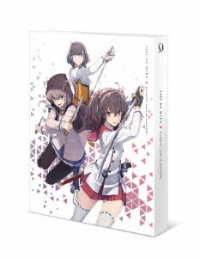出版社内容情報
厨川白村(1880年から1923年)文芸評論家・京都帝国大学教授。
大正期に日本の批評空間で「ラヴ・イズ・ベスト」の神話を生み出した厨川白村。当時熱狂的に読まれた文芸批評や『近代の恋愛観』は、その後朝鮮半島・中国でも一大ブームを起こし、『苦悶の象徴』『象牙の塔を出て』は魯迅が翻訳にあたった。この事実は、東アジア文学の将来を考えるとき、多くのヒントを与えてくれる。現代へと続く文化的礎石を作ったその生涯をはじめて解き明かす。
【目次】
プロローグ なぜいま厨川白村か
第一章 京都と大阪で過ごした幼少年時代
1 謎の残る幼年期
2 小学校時代の面影
3 エリート教育への第一歩
第二章 最初の音符を奏でるのは大事だ
1 英詩翻訳の試み
2 若き精神が奏でる詩の旋律
3 批評のための予行演習
第三章 鉄は熱いうちに打て――三高で過ごした日々
1 三高進学という関門
2 誇り高き三高生になって
3 自由な校風に育まれて
4 校友会誌の編集にも
第四章 象牙の塔での喜悲劇――東京帝大での歳月
1 赤門をくぐって
2 最高学府で味わった苦楽
3 教える「天才」を目の当たりにして
4 恩師の「解任」騒動に巻き込まれて
5 夏目漱石の教えを受けて
6 悲喜こもごもの巣立ち
第五章 三高の英語教授になるまで
1 見知らぬ地で田舎教師になる
2 英語教師の評判
3 相思相愛の末に
4 名物教授の泣き笑い
5 母校の教壇に立つ
第六章 新進気鋭の評論家のデビュー
1 人気者と道化役は紙一重
2 新進気鋭の教授の光と影
3 文壇に殴り込む
4 処女作が誕生する前夜
5 処女作がベストセラーに
6 さらなる飛躍へ
第七章 左足切断という不運に見舞われる
1 『文芸思潮論』を刊行するまで
2 左足切断という災厄に見舞われる
3 アメリカ留学への旅立ち
第八章 アメリカ留学での体験
1 ニューヨーク生活の泣き笑い
2 肌で触れたアメリカ文学
3 懐郷の念がそそられる異国体験
4 幻の「現代日本小説集」英訳の波紋
5 シエルコフ夫人の正体
第九章 学界と論壇を股にかけて
1 京都帝大復帰の重み
2 語り継がれる伝説の虚実
3 意図せぬアメリカ論
4 社会批評や文明批評にも
第十章 人生の頂点から思わぬ結末へ
1 海外にも名を轟かせて
2 「ラヴ・イズ・ベスト」という神話の誕生
3 予想外の災厄
エピローグ 日本から東アジアへ――独り歩きする人間像
参考文献
あとがき
厨川白村略年譜
人名・事項索引
内容説明
厨川白村(一八八〇~一九二三)文芸評論家・京都帝国大学教授。大正期に日本の批評空間で「ラヴ・イズ・ベスト」の神話を生み出した厨川白村。当時熱狂的に読まれた文芸批評や『近代の恋愛観』は、その後朝鮮半島・中国でも一大ブームを起こし、『苦悶の象徴』『象牙の塔を出て』は魯迅が翻訳にあたった。この事実は、東アジア文学の将来を考えるとき、多くのヒントを与えてくれる。現代へと続く文化的礎石を作ったその生涯をはじめて解き明かす。
目次
プロローグ なぜいま厨川白村か
第一章 京都と大阪で過ごした幼少年時代
第二章 最初の音符を奏でるのは大事だ
第三章 鉄は熱いうちに打て―三高で過ごした日々
第四章 象牙の塔での喜悲劇―東京帝大での歳月
第五章 三高の英語教授になるまで
第六章 新進気鋭の評論家のデビュー
第七章 左足切断という不運に見舞われる
第八章 アメリカ留学での体験
第九章 学界と論壇を股にかけて
第十章 人生の頂点から思わぬ結末へ
エピローグ 日本から東アジアへ―独り歩きする人間像
著者等紹介
張競[チョウキョウ]
1953年上海生まれ。華東師範大学を卒業、同大学助教を経て日本へ留学。東京大学大学院総合文化研究科比較文学比較文化博士課程修了。東北芸術工科大学助教授、國學院大学助教授、明治大学教授を経て、明治大学名誉教授。主著『恋の中国文明史』筑摩書房、1992年、ちくま学芸文庫、1997年(読売文学賞・評論・伝記部門受賞)。『近代中国と「恋愛」の発見』岩波書店、1995年(サントリー学芸賞・芸術・文学部門受賞)(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。