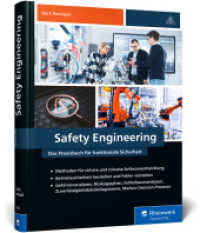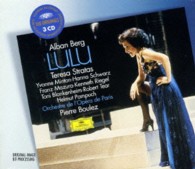出版社内容情報
彼女たちはいったいどのような理由で夜の世界で働くことを選んだのか。何を考え、どのような気持ちで働いていたのか。そのような問いに立ち、女給たちの眼を通して夜の銀座を見つめたい。そこには何が見えるのだろうか。
内容説明
彼女たちはいったいどのような理由で夜の世界で働くことを選んだのか。何を考え、どのような気持ちで働いていたのか。そのような問いに立ち、女給たちの眼を通して夜の銀座を見つめたい。そこには何が見えるのだろうか。
目次
まえがき 夜の銀座を「女給」の視点で考える
第1章 文明開化とともに西洋飲食店現る
第2章 カフェーの登場と女性給仕たち
第3章 関東大震災からの復興とカフェーの乱立
第4章 震災後の女給たちの生活実態
第5章 カフェーの多様化と社会問題化
第6章 「女給ブーム」による銀座女給の記号化
第7章 戦後の銀座と女性たち
あとがきにかえて 女給たちが教えてくれたこと
著者等紹介
小関孝子[オゼキタカコ]
2013年立教大学大学院21世紀社会デザイン研究科比較組織ネットワーク学専攻博士課程修了。博士(社会デザイン学)。現在、跡見学園女子大学観光コミュニティ学部講師(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
fwhd8325
51
夜の銀座には縁がありませんが、映画では社長シリーズなどで見ていた世界なのでしょうか。タイトルにそそられましたが、学術書みたいだったらと、不安がありました。内容はとても読みやすく。丁寧に調べられ、面白く読みました。社会情勢と密接に関係していることを考えると、松本清張さんの「黒革の手帖」や「歴史は夜作られる」という言葉に説得力を感じます。2024/05/06
よしたけ
48
明治初期に舶来飲料を出す店が流行し、その流れで台湾喫茶店で女給が採用された。大正に入ると、整備された街路・路面電車・路面店等で銀座イメージが向上し、水商売も発展。関東大震災あうも松屋と松坂屋の進出で盛り返し、戦争経るも米軍相手の商売で銀座は活況を取り戻した。女給は軽んじられてきたが、女給を主人公にした映画大ヒット、東京五輪で浸透した外来語「ホステス」のイメージ戦略もあり地位が向上。その後、カフェーに入り浸る学生が増えたことから、「特殊飲食店」と規定する法規制が施行され、現在の水商売へとつながっていった。2023/08/31
MASA123
12
昭和33年(1958)に、坂口佐千代が銀座に「クラクラ」というバーを開店させると、文壇バーとして多くの作家が集った。夫、坂口安吾の急逝の翌年のことで、坂口の前には、織田作の二度目の妻もバーを経営していて、文士が作家未亡人のバーを盛り立てた。佐知代さんは、いつも文士たちが自宅に集まってくるので、同じようなものだったとか。その頃、ホステスという呼称が、女給のかわりに登場し流行になった。大阪万博のときも「ホステス」て呼んでいた。 2023/06/24
本の蟲
11
明治から昭和にかけて、創作物では欠かせない存在「カフェー」。そして、そこに勤めていた女給たちを題材した一冊。西洋飲食店と女性給仕の黎明期。関東大震災からのカフェー乱立。西と東の業態の違いとカフェーの多様化。境界が定まらない給仕・コンパニオン・ホステスの仕事。単なる職業名であった女給が蔑称になってしまった理由。「接待」と「特殊飲食店」が法律で定義されるようになった経緯。「女給」という言葉で記号化・消費された彼女たち。残された資料から丁寧に読み解いた各々の収入・生活実態・想いが生々しい2023/05/07
miu_miu
3
カフェの女給という言葉は古い映画や本で知っていましたが、そういうことだったのか。銀座は、明治維新による西洋化が元芸妓を飲食業界に引き寄せ、大衆的な浅草がに対して、外人相手の物販店の多かった銀座はハイカラな街として、ビヤホールに始まり、カフェやバーが勃興。関東大震災後も数か月で銀座は復興し、この頃から女給と呼ばれた女性を売りにしたカフェが隆盛を誇った。女給は完全チップ制で、シングルマザーや地方からの出稼ぎなどで住み込みで働ける店が多く、受け皿になったと。話はそれますが、銘酒屋という業態は知りませんでした2023/07/13