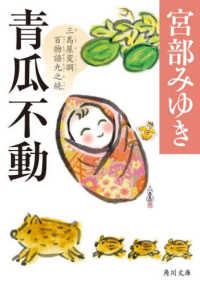出版社内容情報
本書は、私たちの日常と切っても切り離せない科学技術とどのように付き合い、またその成果やプロセスをいかに判断して、生活の中で対応していくかを考えるための格好のテキスト。第1部では主に戦後から現在までの日本の科学技術史を、大きな事件や課題を手がかりに解説する。そして第2部ではSTS(科学技術社会論 Science
目次
第1部 現代科学技術史からの視座(原爆で始まった戦後;公害問題と科学技術;広がるフロンティアとオルターナティブの追究;ポスト神戸と3・11)
第2部 STSからの視座(現代的課題;概念と方法)
著者等紹介
塚原東吾[ツカハラトウゴ]
神戸大学大学院国際文化研究科教授
綾部広則[アヤベヒロノリ]
早稲田大学理工学術院教授
藤垣裕子[フジガキユウコ]
東京大学大学院総合文化研究科教授
柿原泰[カキハラヤスシ]
東京海洋大学学術研究院教授
多久和理実[タクワヨシミ]
東京工業大学リベラルアーツ研究教育院講師(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
無重力蜜柑
10
STSの項目別解説。見開き1ページで1項目を解説し、全108項目。参考文献の案内が非常に丁寧で助かる。自分は専攻なので一応通読したが辞書的に使うのが正解か。タイトルは「科学技術史・STS」なので前半は科学技術史、後半がSTSの課題や概念になっているが、前半もSTSの補助のための歴史という感じで第二次世界大戦後かつ日本の事例に偏っている。とはいえ分け方は不鮮明だし、寄稿者が多いこともあり内容の重複が目立つのは残念。ただ、環境学周りの話など読みたい本や議論が増えたので有用ではある。2022/07/04
jackbdc
8
科学技術は毒にも薬にもなるという話。便利さと公正さは時に相反する場合がある。ありがとう!と感じる時、ふざけんな!と感じる時、その両方が訪れる。得する人と損する人、その両方がいる。民主主義の中でバランスをとれるのか?それが問題意識になるんだろう。象徴的なテーマはテクノクラシーと原子力。前者は社会システムとして、後者は代表的な技術として。過去の歴史を振り返ると、人間は科学技術の進歩の恩恵を受け、時に失敗し、色々と学びながら人も社会も適応を続けて今に至る。今後学びのサイクルをさらに効果的に回す必要がありそう。2022/03/31
mim42
5
寄稿者が多いので品質にムラがある。基本的に、反原発、反体制的な偏向が強い。論理よりもイデオロギーや感情が優先されている印象。前半だけ読んで、その先を読む気にならずそっ閉じ。2023/11/27
onoeume
0
科学と技術の歴史的な融合を学べます。オススメです。2022/02/14
-
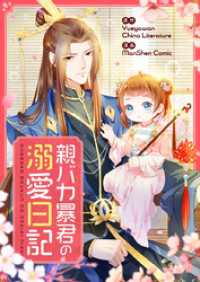
- 電子書籍
- 親バカ暴君の溺愛日記【タテヨミ】第5話…
-

- 電子書籍
- ル・ボラン2021年8月号