出版社内容情報
源 頼朝(1147年から99年)征夷大将軍・鎌倉幕府の創始者。
平治の乱に敗れ伊豆に流されるも一転、平氏打倒の挙兵後、鎌倉を本拠に勢力を伸ばした源頼朝。反乱軍として出発しつつもやがて天下を平定、武家政権の基礎を確立した、その足跡と人物像に迫る。
内容説明
征夷大将軍・鎌倉幕府の創始者。平治の乱に敗れ伊豆に流されるも一転、平氏打倒の挙兵後、鎌倉を本拠に勢力を伸ばした源頼朝。反乱軍として出発しつつもやがて天下を平定、武家政権の基礎を確立した、その足跡と人物像に迫る。
目次
序章 頼朝の遺産
第1章 河内源氏の繁栄と低迷―義朝以前
第2章 幼年期の頼朝と保元の乱
第3章 平治の乱と伊豆配流
第4章 流人頼朝の挙兵
第5章 頼朝率いる反乱軍の動向
第6章 流動化する内乱情勢の行方
第7章 頼朝の変貌と鎌倉幕府権力の展開
第8章 頼朝の政治と建久の「平和」
著者等紹介
川合康[カワイヤスシ]
1958年三重県生まれ。1987年神戸大学大学院文化学研究科博士課程単位修得退学。現在、大阪大学大学院文学研究科教授。博士(文学)(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
-
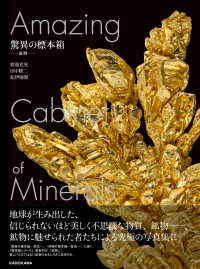
- 和書
- 驚異の標本箱 ‐鉱物‐
-
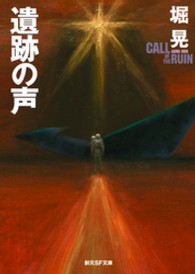
- 和書
- 遺跡の声 創元SF文庫






