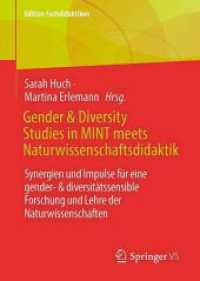出版社内容情報
本書は、高等学校の検定済教科書をもとにした法学入門書である。「政治・経済」や「現代社会」、「経済活動と法」の教科書の内容を、法学の体系に再構成し、法学の全体像を分かりやすく解説する。法学の初学者が、法令用語や法学特有の言い回し、法学独特の思考方法に接すると、法学は難しいとの感想を抱くことがあるが、高校の授業との接続を大切にしながら、様々な法分野を丁寧に説明する。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
trazom
98
高校の「政治・経済」「現代社会」の教科書をもとにした法学の入門書。刑法がないのは片手落ちだが、高校の教科書では刑法は説明されないからだと言う(何故?)。一冊を通して「なるほど」と納得する部分が多くあるのは、私のレベルが高校生以下ということなんだろう。法令用語で、「及び」と「並びに」、「又は」と「若しくは」が、それぞれ厳密に違うことすら知らなかったのは恥ずかしい。ただ、勉強にはなるが、やはり「教科書」というのはちっとも面白くない。「判例紹介」等のコラムが救いだが、淡々と権利や制度の説明を読み続けるのは辛い。2021/11/15
アルカリオン
11
p12 法令では「その他の」は、前に置かれた語句が後ろに続く語句の例示となる。例:「賃金、就業時間、休息その他の勤労条件」▼「その他」は、その前後の語句を並列の関係で並べる場合に使用する。例:「官公庁その他公務員が職務を行う所」▽この場合、「官公庁」は例示ではなく、その後ろに続く語句と並列である▼▼ん?厳密に考えると「官公庁」と並列なのは、「公務員が職務を行う所」か「その他公務員が職務を行う所」かどちらだろう?用法解説によれば前者、例示の補足説明(および字面上の論理性)によれば後者、となりそうだが。2021/11/15
Go Extreme
2
法の意義: 役割 分類 形式的効力 適用と解釈 日本の近現代法のあゆみ: 近代法との出会い 近代法の整備 社会運動の発展 第二次世界大戦 戦後改革 高度経済成長と経済大国日本 バブル経済の崩壊と社会主義体制の崩壊 東日本大震災と新型コロナウィルス感染症の流行 日本国憲法と基本的人権 日本の政治機構: 国会と立法 内閣と行政 裁判所と司法 権利・義務と財産権 契約と財産権の保護 株式会社と法 消費者と法 労働と法: 労働基本権と労働法 労働組合法 労働関係調整法 労働基準法 民事紛争の予防と解決 家族と法2021/11/12