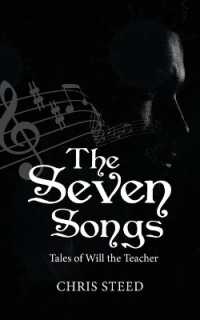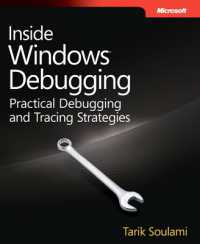出版社内容情報
長井新左衛門尉(?から1533年?)・斎藤道三(1504年から56年)・義龍(1529から61年)・龍興(1547年から73年) 美濃国の戦国大名。
僧侶から土岐氏重臣に上り詰めた長井新左衛門尉。下剋上により美濃国主となった斎藤道三。父親を倒して国威を増した義龍。織田信長の攻勢により敗れた龍興。稲葉山城を舞台に勃興し没落していった四代の軌跡を描く。
内容説明
長井新左衛門尉(?~一五三三?)・斎藤道三(一五〇四~五六)・義龍(一五二九~六一)・龍興(一五四七~七三)美濃国の戦国大名。僧侶から土岐氏重臣に上り詰めた長井新左衛門尉。下剋上により美濃国主となった斎藤道三。父親を倒して国威を増した義龍。織田信長の攻勢により敗れた龍興。稲葉山城を舞台に勃興し没落していった四代の軌跡を描く。
目次
序章 前斎藤氏の隆盛と衰退
第1章 長井新左衛門尉の台頭
第2章 「斎藤」氏へ
第3章 道三、美濃国主へ
第4章 道三と義龍
第5章 義龍の領国支配
第6章 義龍の死と信長の侵略
第7章 龍興の没落とその後
第8章 語られる道三・義龍・龍興
著者等紹介
木下聡[キノシタサトシ]
1976年、岐阜県生まれ。2007年、東京大学大学院人文社会系研究科博士課程単位取得退学。博士(文学)。現在、東京大学大学院人文社会系研究科助教(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
サケ太
20
“美濃の蝮”としてのイメージが強すぎる斎藤道三。美濃の守護代であった前斎藤氏(妙椿)から始まり、道三の父である長井新左衛門の立身出世。“斎藤”道三の国主への道。息子、義龍との対立。龍興の興亡。姓を、名を変えて多くの戦いの中を生き抜いた斎藤氏四代。蝮という虚像を小説家によって与えられた道三。一色姓や范可を名乗った義龍、その内政の手腕は確かに信長を苦しめた。竹中半兵衛の城取の理由は、物語化されたものと比べると、当時の人物らしくて納得。今のイメージで形成されているものとは違う人物像が提示されていて興味深かった。2020/03/22
MUNEKAZ
11
長井新左衛門尉・道三・義龍・龍興の四代の評伝。史料の少なさから著者の推測も多いが、イメージ先行の一族を実証的に描こうとしている。梟雄だが陰謀家というよりは剛腕の戦上手な道三、軍事・内政ともに大きな瑕疵はないが早死にしたせいでボロが出なかっただけかも…な義龍、愚将から再評価される龍興(でも有能とは言っていない)と、それぞれに個性的で面白い。また著者の専門から義龍の一色改姓の話題にページを割いているのも印象的。西村→長井→斎藤→一色と代々変わる名字が、その成り上がりを示している。2020/02/24
フランソワーズ
6
下剋上の代名詞のような道三。地名度の高さから実像とかけ離れた面を、限られた史料の中で修正。そして道三以前の斎藤氏と、滅亡してしまったために評価が低い道三以後の斎藤氏を論述。特に隠れた名将義龍をしっかり評価してくれているのがいい。著者官位官途等の研究をされておられるからでしょうか、その面での論述はとても説得力がありました。2021/08/06
相馬
4
新左衛門尉から道三、義龍、龍興までの四代についての、最新の研究を纏めた評伝。一冊に纏まっていて読み易い。横山住雄氏の研究に大きく寄っていて、目新しい部分は多くはないが、一色氏への改名、妻女になどについても更に詳しく述べられていて興味深い。2020/05/03
Toska
3
「下剋上」の雄・斎藤氏の実相に迫る。とにかく史料が少なく、四代の発給文書が稲葉一鉄一人よりも少ないというのは驚きだ。だからこそ著者の力量が問われるテーマでもあり、特に家格や官位、実名の分析は木下氏にとり自家薬籠中のもので、興味深く読めた。肝はやはり義龍だろうか。父殺しのタブーを犯しながら家中を動揺させなかったばかりか、幕府との交渉に辣腕を振るい、改姓も改名も思いのままという、考えてみればものすごい業績。彼の熱意を考えると、本当は一色氏と呼びたいところなのだが…2021/09/04
-

- 電子書籍
- ああ、生きているって素晴らしい【タテヨ…