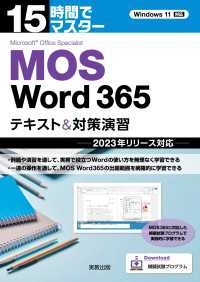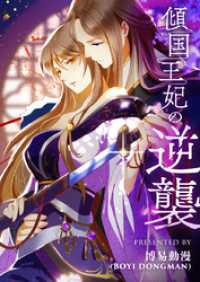出版社内容情報
これは身体拘束をしている現場の人々を糾弾する本ではない。
なぜ縛るのかと問うことは、精神科病棟や認知症施設の外でも日々行われている、力や器具や言葉によるあらゆる形の拘束について考えることだ。
からだと思考、感覚や感情さえも縛られていると感じるこの国のすべての人に読んでほしい。
松嶋 健(文化人類学者・広島大学准教授)氏推薦
精神病院における身体拘束は、人権にかかわる重要な問題である。イタリアでは、1978年に世界で初めて精神病院の廃絶を定めた「法律180号」が制定された。イタリアで精神病院を解体していった経緯や、現在進行中の拘束廃止をめぐる運動、また、拷問のような「拘束」が頻繁に起こるメカニズムやその社会的背景について、運動の中心メンバーである著者が初めて日本へ向けて書下ろした。「拘束」問題を問う画期的な一冊である。
内容説明
イタリアでは、一九七八年の「法律一八〇号」によって、精神病院の閉鎖が始まり、精神医療の拠点は地域に移された。この法律にたどり着くまでの解放運動で、自由と解放のシンボルとされたのが、本書カバーの「青い馬」である。精神病院は解体されたものの、精神医療の現場では依然として拷問のような「拘束」が存在している。本書は、この拘束を廃止するための運動を長年イタリアで続けている著者が、現在進行中の運動や、拘束が頻繁に起こるメカニズム、その社会的背景について、日本へ向けて書き下ろした画期的な一冊である。
目次
第1部 拘束廃止に向けた精神科医の経験から(総合病院内SPDCで拘束された男性;精神保健局での拘束廃止へのあゆみ―カリアリのケースから)
第2部 イタリア拘束廃止運動の実際(ケアの場での器具による拘束;精神的困難を抱えた人への人権侵害―イタリアにおける脱施設化の経験と改革後にも残る拘束;やればできる)
第3部 拘束廃止に向けたインタビュー(拘束は拷問です;もはや人間ではない;遁走する主体)
著者等紹介
デル・ジューディチェ,ジョバンナ[デルジューディチェ,ジョバンナ] [Del Giudice,Giovanna]
1946年イタリアのレッチェ生まれ。1971年バリ大学医学部を卒業、1975年にパルマ大学精神医学専門課程修了。1971年フランコ・バザーリアの院長時代にトリエステ県立精神病院に研修医として勤務。トリエステでの脱制度化過程に関わり、1980年精神保健センターの責任者など地域精神保健サービス発展に重要な役割を担う。2002年以降、サービスの改善や向上を求める地域に赴き、カゼルタ2地区の精神保健局長、2006~2009年にはカリアリ精神保健局長を歴任。2010年トリエステに戻り「Conferenza Permanente per la Salute mentale nel mondo(CoPerSamm)Franco Basaglia(世界精神保健の永久協議会:フランコバザーリア協議会)」を起ち上げ、2013年~現在まで協議会代表を務め、イタリア国内や中国、アルゼンチンなど多くの世界の国々と連携を図り、その国の人々とともに精神保健の問題改善に取り組んでいる
岡村正幸[オカムラマサユキ]
大阪府庁、愛知みずほ大学を経て、佛教大学名誉教授。東洋大学博士(社会福祉学)
小村絹恵[コムラキヌエ]
精神科病院、地域の相談支援事業所にて精神保健福祉士として勤務。2010年佛教大学大学院社会福祉学研究科修士課程修了。2016年トリエステ大学人文学部社会福祉学科修士課程に1年間聴講生としての留学中、トリエステ精神保健局内のさまざまな機関にて参与観察を行う。現在、大谷大学・佛教大学非常勤講師。一般社団法人イケダ大学代表理事(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
トンちゃん
Go Extreme