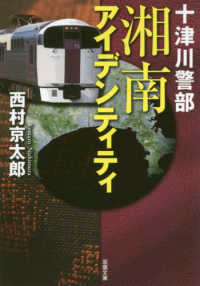出版社内容情報
保育者が描く34本のエピソード記述と著者による解説から見えてくるいま求められる“新たな保育のかたち”子どもの心の動きを真に問題にした「新しい保育論」を提言。――「いつ、何を子どもたちにさせるか」という従来のカリキュラム的発想ではなく、子どもの心の動きに沿って保育者が対応するところを取り上げようとする立場から、子どもと保育者の関係性を軸にした「新しい保育論」の必要性を説きます。エピソードに描き出されるものこそ「保育する」営みそのものであるという考えのもと、本書では珠玉の34本のエピソード記述を紹介。保育者によるエピソードと著者による解説を読み解くなかで、“新たな保育のかたち”が見えてきます。
はしがき
第?部 理論編
第1章 「保育する」営みを再考する──新保育論のために
1 「接面の人間学」の基軸となる基本的な考え方
2 「接面の人間学」の考えを新保育論のために整理する
3 新保育論のために
4 なぜ保育者は自らの保育をエピソードに描く必要があるのか
第2章 子どもの「ある」と「なる」を考える
1 主体が抱える二面──「ある」と「なる」
2 「ある」に含まれる現状肯定と現状止揚の二契機
3 「なる」への過程における子どもと保育者の葛藤
4 「なる」が生まれるまでの保育者の対応を考える
第?部 実践編
第3章 0、1歳児への保育者の「教育の働き」
1 この章の目的
2 一連のエピソード記述から
3 各エピソードの要約と本章のまとめ
第4章 「ある」を受け止めることから「なる」への兆しへ
1 本章の目的
2 一連のエピソード記述から
3 各エピソードの要約と本章のまとめ
第5章 挑戦する心──「ある」から「なる」へ
1 本章の目的
2 一連のエピソード記述から
3 各エピソードの要約と本章のまとめ
第6章 子ども同士のトラブルは「なる」への跳躍台
1 本章の目的
2 一連のエピソード記述から
第7章 集団活動(遊び)のなかで子どもに何が育つのか
1 本章の目的
2 一連のエピソード記述から
3 各エピソードの要約と本章のまとめ
あとがき
鯨岡 峻[クジラオカ タカシ]
著・文・その他
内容説明
子どもの心の動きを真に問題にした「新しい保育論」を提言。―「いつ、何を子どもたちにさせるか」という従来のカリキュラム的発想ではなく、子どもの心の動きに沿って保育者が対応するところを取り上げようとする立場から、子どもと保育者の関係性を軸にした「新しい保育論」の必要性を説きます。エピソードに描き出されるものこそ「保育する」営みそのものであるという考えのもと、本書では珠玉の34本のエピソード記述を紹介。保育者によるエピソードと著者による解説を読み解くなかで、“新たな保育のかたち”が見えてきます。
目次
第1部 理論編(「保育する」営みを再考する―新保育論のために;子どもの「ある」と「なる」を考える)
第2部 実践編(0、1歳児への保育者の「教育の働き」;「ある」を受け止めることから「なる」への兆しへ;挑戦する心―「ある」から「なる」へ;子ども同士のトラブルは「なる」への跳躍台;集団活動(遊び)のなかで子どもに何が育つのか)
著者等紹介
鯨岡峻[クジラオカタカシ]
現在、京都大学名誉教授。京都大学博士(文学)(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
-
- 洋書
- Curious Me
-

- 電子書籍
- 基本刑法 総論 第3版