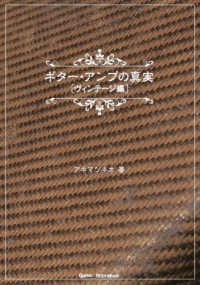出版社内容情報
支援が困難なケースの実態をリアルに描き、けっしてあきらめない支援の方法と展望について、発達臨床の視点から指し示す。生きづらさを抱える子どもや大人には多様なニーズがあり、ときにその重なりや思いもよらぬ理由から、困難な事例が生じることがある。教育・保育・心理・福祉・医療の現場に携わる人たちは、そうした事例に懸命にかかわり、自身の支援のあり方を確認しながら、発達支援への糸口を模索する。結果、苦い教訓が残ることもある。本書は、そうした現場での試行錯誤をリアルに描き、今できるよりよい支援に必要なことを、発達臨床の視点から考える。
まえがき
第1章 支援が困難な事例(シビアケース)のとらえ方(香野 毅)
1 実践を振り返るということ
2 アセスメントに起因したと思われる困難さ
3 複雑に絡み合った問題による困難さ
4 家族との連携における困難さ
5 相談ニーズと相談行動にかかわる困難さ
6 実践において生じる困難さを少しでも減じるために考えうること
第2章 自閉スペクトラム症児の困難事例の理解と支援?──遊戯療法と母親面接(中西由里・別府悦子)
1 自閉スペクトラム症(ASD)とは
2 自閉スペクトラム症(ASD)と診断されているAくん(男児)とその母親に対する支援
3 事例の経過
4 事例をもとに自閉スペクトラム症(ASD)の心理療法を考える
第3章 自閉スペクトラム症児の困難事例の理解と支援?──学童クラブでの集団活動(服部敬子)
1 場面緘黙をともなう高機能自閉スペクトラム症(ASD)児の支援の困難
2 Aくんの支援について
3 支援の経過
4 Aくんの変化と支援についての考察
第4章 自閉スペクトラム症児・者の困難事例の理解と支援──発達のアンバランスに注目して(別府 哲)
1 自閉スペクトラム症(ASD)の問題行動と機能連関
2 定型発達における1歳半の節と機能連関
3 自閉スペクトラム症(ASD)における1歳半の節と問題行動
第5章 ろう学校の重複障害学級での困難事例の理解と支援──「天敵」がかけがえのない友になるとき(竹沢 清)
1 ぶつかりあう俊作と昇太
2 実践で大事にしたいこと
3 実践の主体者になるために
第6章 医療的ケアを必要とする重症心身障害児の困難事例の理解と支援──肢体不自由特別支援学校での実践(別府悦子・近藤博仁)
1 医療的ケアの必要な重症心身障害者の支援の困難
2 重症児Aさんの支援について
3 支援の経過
4 重症児へのかかわりの困難とそれに向かう支援
第7章 学童期における困難事例の理解と支援──ソーシャルワークの観点から(鈴木庸裕)
1 ソーシャルワークのある社会
2 自閉スペクトラム症(ASD)の疑いがある小学生Aくん(男児)への支援──個別的対応事例をもとに
3 個々の多様性と家族を丸ごととらえる支援と学校づくりを通じて
4 多様性の尊重をめざして
第8章 思春期・青年期における困難事例の理解と支援──生活指導と集団づくり(湯浅恭正)
1 「支援困難な子ども」の理解
2 生活指導の視点から思春期・青年期をとらえる
3 支援困難な中学生の自立への取り組み
4 困難な課題を持つ青年への支援
第9章 強度行動障害者の困難事例の理解と支援──障害者施設での実践(別府悦子・藤井美和・別府 哲)
1 障害者施設で生活する人たちと支援
2 行動障害の人たちの実践事例から支援について考える
3 実践の試行錯誤と職員の願い
4 集団の中で生活経験を踏まえた支援を
第10章 支援の困難を生み出す保育の構造的な課題──巡回相談の現場から(田宮 縁)
1 問題の所在
2 巡回相談で出会った保育者たち
3 考 察──現場の構造的な課題
4 人と人との営みの中で
第11章 災害時における障害児・者や家族の理解と支援(小林朋子)
1 支援の必要性
2 災害後の障害のある子どもの心身の反応
3 災害時における保護者の困難
4 障害のある子ども・人および家族への支援
5 キーワードは「場所」「情報」「人」
第12章 支援が困難と感じるとき──児童精神科医の立場から(田中康雄)
1 われわれのクリニックの現状
2 支援が困難と感じるとき
3 「理解・協力者」から「応援されるべき者」へ──子どもにかかわる人への支援
4 優れた支援者
5 愚者の独語
6 支援者へのエール
7 支援から共生へ
付 録
1 発達障害について
2 アタッチメント障害について
あとがき
索 引
別府 悦子[ベップ エツコ]
編集
香野 毅[コウノ タケシ]
編集
内容説明
生きづらさを抱える子どもや大人には多様なニーズがあり、ときにその重なりや思いもよらぬ理由から、困難な事例が生じることがある。教育・保育・心理・福祉・医療の現場に携わる人たちは、そうした事例に懸命にかかわり、自身の支援のあり方を確認しながら、発達支援への糸口を模索する。結果、苦い教訓が残ることもある。本書は、そうした現場での試行錯誤をリアルに描き、今できるよりよい支援に必要なことを、発達臨床の視点から考える。
目次
支援が困難な事例(シビアケース)のとらえ方
自閉スペクトラム症児の困難事例の理解と支援1―遊戯療法と母親面接
自閉スペクトラム症児の困難事例の理解と支援2―学童クラブでの集団活動
自閉スペクトラム症児・者の困難事例の理解と支援―発達のアンバランスに注目して
ろう学校の重複障害学級での困難事例の理解と支援―「天敵」がかけがえのない友になるとき
医療的ケアを必要とする重症心身障害児の困難事例の理解と支援―肢体不自由特別支援学校での実践
学童期における困難事例の理解と支援―ソーシャルワークの観点から
思春期・青年期における困難事例の理解と支援―生活指導と集団づくり
強度行動障害者の困難事例の理解と支援―障害者施設での実践
支援の困難を生み出す保育の構造的な課題―巡回相談の現場から
災害時における障害児・者や家族の理解と支援
支援が困難と感じるとき―児童精神科医の立場から
著者等紹介
別府悦子[ベップエツコ]
東京学芸大学大学院連合学校教育学研究科博士課程修了、博士(教育学)。臨床心理士、臨床発達心理士。現在、中部学院大学教育学部・大学院人間福祉学研究科教授
香野毅[コウノタケシ]
九州大学大学院教育学研究科博士後期課程退学。臨床心理士、日本リハビリテイション心理学会スーパーバイザー。現在、静岡大学教育学部教授(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
saiikitogohu
しいかあ