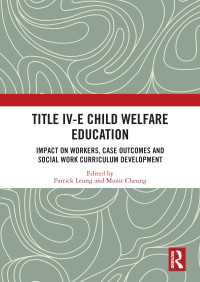出版社内容情報
「この国のかたち」への探究、 そして近代日本の原点…使節団の光と影とは。 「米欧亜回覧の会」20周年記念出版。明治4年から6年にかけて「この国のかたち」を求めて米欧諸国に派遣された岩倉使節団には、いかなる人々が集っていたのか。彼らはアメリカやヨーロッパで何を見、何を持ち帰ったのか。「未来は歴史の中に在る」といわれるが、現代日本を覆う閉塞感を打ち破る鍵が、この群像たちの思想と営為の中に見つけることができるのではなかろうか。「米欧亜回覧の会」設立20周年記念出版。
まえがき
第?部 岩倉使節団の群像
第1章 岩倉使節団は徳川文明の凱旋門である(芳賀 徹)
1 空前絶後の使節団と報告書
2 後ろ姿から見る岩倉使節団
3 徳川人こそが明治国家をつくった
4 岩倉使節団は徳川日本の凱旋門
5 久米はなぜ、見事な見聞録を書けたか
6 愉悦の仙境・ヴェネチアの恍惚
第2章 知られざる岩倉使節団の群像(小野博正)
1 歴史的大英断の岩倉使節団
2 世界的にも評価の高い、公式報告書『特命全権大使 米欧回覧実記』
3 世界史的時代背景とそこで出会った人々
4 使節団の構成──大使本隊、各省派遣組、随行する留学生
5 使節団員が「米欧回覧の旅」から学んだもの
第3章 大使・副使たち──岩倉具視・木戸孝允・大久保利通・伊藤博文・山口尚芳(泉 三郎)
1 大使・岩倉具視
2 副使・木戸孝允
3 副使・大久保利通
4 副使・伊藤博文
5 副使・山口尚芳
第4章 『米欧回覧実記』の編著者・久米邦武、晩年の境地(M・ウィリアム・スティール)
1 米欧での発見──歴史と未来への関心
2 進歩に関する疑問
3 歴史の生き証人、大変化の九十年を回顧する
4 ヨーロッパ戦乱についての久米の深い憂慮
5 歴史より観たる世界の平和
第5章 林董──箱館戦争の戦士から日英同盟の立役者へ(岩崎洋三)
1 父・佐藤泰然の導きと英学修業
2 帰国、榎本武揚に従い箱館戦争へ
3 岩倉使節団に随行、工学技術教育に協力
4 いよいよ外交の本舞台へ
5 画期的な日英同盟の締結へ
第6章 金子堅太郎──日本文明の伝播者・広報外交の先駆者(吹田尚一)
1 アメリカ留学から官途昇進の途
2 日露戦争下の広報外交
3 プレゼンテーションで訴えた代表的なキーポイント
4 友情と政治の論理
5 日本の興隆に、西洋列強は警戒心を募らせる
6 日米の親善と『明治天皇紀』や『明治維新史』の編纂に尽力
第7章 田中光顕──影の元老ともいうべき黒幕的な巨魁(小野寺満憲)
1 土佐藩士、尊王攘夷運動参画と長州との関わり
2 岩倉使節団の大蔵省理事官(戸籍頭兼会計長)となる
3 帰国後の各方面での目覚ましい活躍
4 天皇家に恒産を、その管理と蓄積に貢献か
5 理想的な君民共治国家樹立への強い使命感
第8章 團琢磨──鉱山技師から三井財閥の総帥・財界のトップへ(桑名正行)
1 黒田藩士の少年、アメリカ留学で鉱山技師へ
2 三池炭鉱での大活躍
3 三井財閥の総帥、そして「日本の顔」へ
4 「英米訪問実業団」を率い、世界一周の旅へ
第9章 吉原重俊──薩摩のボッケモン、初代日本銀行総裁へ(吉原重和)
1 薩摩藩士、イエール大学へ
2 岩倉使節団へ参加、引っ張りだこの仕事ぶり
3 大蔵省・外務省の官僚として東奔西走の活躍
4 日本銀行初代総裁就任
5 文明開化の戦士──激務の中に殉死?
第10章 渡邉洪基──明治社会のマルチ・オーガナイザー(赤間純一)
1 渡邉洪基と伊藤博文──明治一〇年代の構図
2 外交官としてのウィーンでの体験から「三十六会長」へ
3 集会条例への関与と「治国平天下の学」の提唱
4 帝国大学成立の背景と伊藤博文の国家ヴィジョン
5 初代帝国大学総長へ、「知と実学」の展開
6 伊藤博文の「教育構想」を支えたマルチ・オーガナイザー
第11章 安場保和──地方行政の国士的キーマン(芳野健二)
1 幕末維新期の活躍
2 岩倉使節団の一員として随行
3 帰国後、福島で地域開発
4 地方行政に徹して──愛知、福岡、北海道をめぐる
5 大久保の信頼厚く、地方行政のキーマンとして活躍
第12章 井上毅──明治国家の骨格を造った思想家・大法制家(小野博正)
1 肥後藩士、明治国家へ出仕
2 岩倉使節団の後発隊に参加、仏独で学習
3 帰国後、政府首脳へ次々と接近、一四年の政変では大活躍
4 大日本帝国憲法──教育勅語ならびに民法典の制定に尽力
5 重要案件の諮問役、スーパー法制官僚へ
第13章 山田顕義──ナポレオンに傾倒、軍事家から法律家へ(根岸 謙)
1 軍事家として文武両道のナポレオンに憧れる
2 法律家としての研鑽、そして司法大臣へ
3 日本固有の法を目指し、日本法律学校(後の日本大学)を創立
4 山田の一貫した志
第14章 田中不二麿──国民主義の教育を志向(大森東亜)
1 尾張藩士から明治新政府へ
2 欧米教育事情の精細な報告書『理事功程』の刊行
3 文部省顧問ダヴィッド・モルレーの招聘
4 「学制」実施推進と国民主義志向の「教育令」制定
5 文部行政の基本レールを敷く
第15章 新島襄──同志社創立・キリスト教主義教育・社会福祉(多田直彦)
1 安中藩士・新島の価値観形成に影響を与えたもの
2 岩倉使節団に巡り合い、キーマンからの高い評価、旅券と米欧視察を得る
3 新島が考えた「日本近代化」は教育事業であった
4 新島襄の教育目的と指導方針
5 同志社の生んだ多彩な人物と「福祉」の人脈
6 同志社と社会福祉
第16章 津田梅子ら女子留学生たち──女子教育のパイオニア(畠山朔男)
1 女子留学生派遣の背景
2 五人の女子留学生とその親たち
3 戸惑うアメリカでの生活
4 津田梅子、山川捨松、永井繁子の学生生活
5 帰国後の永井繁子と山川捨松
6 津田梅子、苦難を越えて「夢」の実現へ
第17章 長与専斎──医療法制・衛生行政の父(西井易穂)
1 代々続く医家に生まれ、緒方洪庵やポンペらに学ぶ
2 ドイツとオランダで「公衆衛生学」を学ぶ
3 医療近代化の基本方針の制定、猛威を奮うコレラ対策に尽力
4 医学校・薬学校の創設、海水浴場の開設
5 後進の人材支援、そして「医の倫理」を説く
第18章 畠山義成──『米欧回覧実記』の影の記者・文部行政の先駆者(村井智恵)
1 イギリス留学、渡米とハリス・コンミューン
2 ラトガース大学とその周辺
3 岩倉使節団に加わる
4 帰国、学監モルレーとの縁、開成学校・博物館・図書館など
5 フィラデルフィア万国博覧会
第19章 岩倉使節団は明治国家に何をもたらしたか──その光と影(パネル・ディスカッション)(五百旗頭薫/芳賀 徹/M・ウィリアム・スティール/マーティン・コルカット/泉 三郎/小野博正)
1 岩倉使節団の「光と影」は七変化
2 派遣組と残留組、第一世代と第三世代、イギリスかドイツか
3 西洋文明の光と影、表と裏
第?部 歴史のなかに未来が見える
第20章 日本近代150年をどう見るか──「起承転結」の試み(保阪正康)
1 80年の「軍事」と70年の「非軍事」
2 「起承転結」という時代区分で考える
3 欧米の軍事学と日本の軍事学
4 近代150年の反省と教訓
第21章 岩倉使節団から150年──いま日本に何が必要か(五百旗頭真)
1 岩倉使節団は東西文明にブリッジを架ける大事業だった
2 日本史における成功と失敗
3 日本歴史の「起承転結」、敗戦から学ぶDNA
4 日露戦争後と第一次世界大戦後が大きな岐路だった
5 戦後日本、廃墟からの復興、占領軍の方針
第22章 日本の価値観──三層・二元構造について(山折哲雄)
1 環境・風土から見た三層構造
2 政治経済から見た権威の二元体制
3 美意識の観点から見た二重構造
第23章 美味し国・ニッポン(近藤誠一)
1 日本の歴史1500年の「起・承・転・結」
2 岩倉使節団の学び
3 日本が歩むべき道は何か
4 自然と伝統に抱かれた「美味し国」を取り戻そう
第24章 岩倉使節団の世界史的意義──地球時代の日本の未来像を求めて(パネル・ディスカッション)(泉三郎/芳賀 徹/保阪正康/近藤誠一/アレックス・カー/橘木俊詔/塚本 弘)
1 明治創業世代はどんな考えを抱いていたか
2 明治人の挑戦、大正人の夢、昭和人の未来像
3 科学技術と産業経済は道具、人類の平和と幸福のために
4 世界中がモデルにしたがる国、「自然・伝統・文明が響きあう国」へ
資料 岩倉使節団団員ミニ列伝(小野博正)
1 本隊(24名)
2 各省派遣理事官・随行員(38名)
3 使節首脳随従者と留学生(27名)
米欧亜回覧の会設立20周年記念グランドシンポジウム「岩倉使節団の世界史的意義と地球時代の日本の未来像」プログラム
人名索引
米欧亜回覧の会[ベイオウアカイランノカイ]
編集
泉 三郎[イズミ サブロウ]
編集
内容説明
明治四年から六年にかけて「この国のかたち」を求めて米欧諸国に派遣された岩倉使節団には、いかなる人々が集っていたのか。彼らはアメリカやヨーロッパで何を見、何を持ち帰ったのか。「未来は歴史の中に在る」といわれるが、現代日本を覆う閉塞感を打ち破る鍵が、この群像たちの思想と営為の中に見つけることができるのではなかろうか。「米欧亜回覧の会」設立二〇周年記念出版。
目次
第1部 岩倉使節団の群像(岩倉使節団は徳川文明の凱旋門である;知られざる岩倉使節団の群像;大使・副使たち―岩倉具視・木戸孝允・大久保利通・伊藤博文・山口尚芳;『米欧回覧実記』の編著者・久米邦武、晩年の境地;林董―箱館戦争の戦士から日英同盟の立役者へ ほか)
第2部 歴史のなかに未来が見える(日本近代一五〇年をどう見るか―「起承転結」の試み;岩倉使節団から一五〇年―いま日本に何が必要か;日本の価値観―三層・二元構造について;美味し国・ニッポン;岩倉使節団の世界史的意義―地球時代の日本の未来像を求めて(パネル・ディスカッション))
資料 岩倉使節団団員ミニ列伝
著者等紹介
泉三郎[イズミサブロウ]
1935年東京都生まれ。1959年一橋大学経済学部卒業。不動産業などの経営を経て著述活動。1976年から岩倉使節団の足跡をフォローし、約8年で主なルートを辿り終える。現在、特定非営利活動法人「米欧亜回覧の会」理事長。ノンフィクション作家(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
BLACK無糖好き
bapaksejahtera