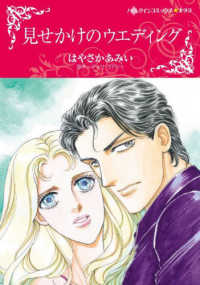出版社内容情報
「みんなが同じ」を前提にしない保育とは? 明日から、遊び心をもって保育を楽しむための本本書では,目の前の子ども同士や子どもと保育者との間で生まれるやりとりや気持ちを大事にして,臨機応変に保育をつくりだしていく「インクルーシブ保育」の実際を伝える。
第?部で「みんなが同じ」であることを前提としない「インクルーシブ保育」の考え方を伝える。第?部では,実践事例をとりあげ,面白い活動が生まれる中でクラス集団の関係性や子ども一人ひとりの姿,保育者自身の認識などが変化していく過程を伝える。第?部では,インクルーシブ保育と従来の障がい児保育や統合保育とのちがいについてあらためて検討し,これからの保育の実践や研究のあり方について考察する。
まえがき
第?部 統合保育からインクルーシブ保育の時代へ
第1章 同質性(同じ)を前提とする保育から多様性の尊重へ(浜谷直人)
1 同質性を前提とした(「同じ」を大事にする)保育形態(Aタイプの保育実践形態)
2 多様性を尊重する保育実践の一例(Bタイプの保育実践形態)
3 インクルーシブ保育時代の実践は統合保育時代の実践となにがどう違うのか?
4 計画をもとに臨機応変に子どもの気持ちを尊重して保育を創り上げる保育形態(Cタイプの保育実践形態)
5 インクルーシブ保育時代における行事の取り組み
6 局所での楽しさがクラスに広がって集団活動になる
7 インクルーシブな保育実践は一回性を特徴とし再現することはできない
第?部 多様性がいきる活動と対話が生まれた実践
第2章 ファンタジーの世界を遊びこんで互いに認め合えた仲間関係(三山 岳)
1 生活発表会で喜び合った子どもの成長
2 みんながばらばらな状態でのスタート
3 保育者の反省をうながした「あかこの大脱走ファンタジー」
4 保育者主導の危うさに気づいた「へびおんなごっこ」
5 ねずみばあさんパニック!
6 ねずみばあさんへの贈り物になったうろこのドレス
7 冒険ファンタジーから生み出された子どもたちの変化
8 実践のまとめ
第3章 日々の活動を通して一人ひとりを対話でつなぐ(五十嵐元子)
1 劇づくりを通して垣間見た子ども同士のつながり
2 固定化する仲間関係と排除の構造
3 手探りの保育の中で──日々の活動と話し合いから見る子どもの姿
4 おたまじゃくしの世話をきっかけにユタカ君が関係を広げる
5 排除の状態にあったマサオ君と他の子どもとの関係性を変える
6 からかわれやすいメグミちゃんが他の子どもに認められるまで
7 好きな活動を選びつながり合う──アトラクションごっこの取り組み
8 他の子を排除していたリュウジ君の仲間関係の変化
9 クラスの一人ひとりが仲間──劇遊びで明らかになった子ども同士の結びつき
10 実践のまとめ──日々の活動や遊びを通して子どもの関係を組み替え,子ども同士の対話的な関係をつくる保育
第4章 保育者間の対話が子ども理解を豊かにする園内研修──クラス関係図をつくりエピソードで語り合う(芦澤清音)
1 インクルーシブ保育を支える同僚性
2 子どもの姿を語り合う場としてのケース検討会
3 ケース検討会の実際──対話を豊かにする保育エピソードとクラス関係図
4 ケース検討会はどのような場なのか
5 同僚性と対話が生み出すインクルーシブ保育の可能性
第?部 インクルーシブ保育時代の実践と研究のあり方
第5章 活動への参加とインクルーシブ保育──ごっこ遊びとルール遊びにおける参加と排除(浜谷直人)
1 ごっこ遊びにおける対等な参加
2 ルール遊びにおける対等な参加
第6章 見通しが不確実な中で保育を創造する──不確実さへの耐性と責任の問題(浜谷直人)
1 「甘えさせている」のか「適切な保育をしている」のかの線引きに悩む──職員間の見方の違い
2 「正しく」保育しようとする実践と「楽しく」保育しようとする実践
3 「最善」の保育とは?
4 保育実践の方向を左右する人間関係の特徴
5 問責状況では視野狭窄が生じる
6 問責志向では排除の力学が働くが,免責することでインクルーシブな状況が生まれる
7 管理モード
8 ゆとりモードとファンタジー・ユーモア
9 保育者が子どもの活動から排除されている
10 「想定外」が楽しいドラマを生み出しインクルーシブな状況が生まれる
第7章 インクルーシブ保育時代までの歴史とインクルーシブ保育の実践上の課題(浜谷直人)
1 障がい児保育の時代
2 統合保育の時代
3 インクルーシブ保育の時代──多様性を前提として価値とする保育を創造する
4 インクルーシブ保育の共通理解に向けて
5 インクルーシブ保育実践の現状と課題
あとがき
浜谷 直人[ハマタニ ナオト]
著・文・その他
芦澤 清音[アシザワ キヨネ]
著・文・その他
五十嵐 元子[イガラシ モトコ]
著・文・その他
三山 岳[ミヤマ ガク]
著・文・その他
内容説明
本書では、目の前の子ども同士や子どもと保育者との間で生まれるやりとりや気持ちを大事にして、臨機応変に保育をつくりだしていく「インクルーシブ保育」の実際を伝える。第1部で「みんなが同じ」であることを前提としない「インクルーシブ保育」の考え方を伝える。第2部では、実践事例をとりあげ、面白い活動が生まれる中でクラス集団の関係性や子ども一人ひとりの姿、保育者自身の認識などが変化していく過程を伝える。第3部では、インクルーシブ保育と従来の障がい児保育や統合保育とのちがいについてあらためて検討し、これからの保育の実践や研究のあり方について考察する。
目次
第1部 統合保育からインクルーシブ保育の時代へ(同質性(同じ)を前提とする保育から多様性の尊重へ)
第2部 多様性がいきる活動と対話が生まれた実践(ファンタジーの世界を遊びこんで互いに認め合えた仲間関係;日々の活動を通して一人ひとりを対話でつなぐ;保育者間の対話が子ども理解を豊かにする園内研修―クラス関係図をつくりエピソードで語り合う)
第3部 インクルーシブ保育時代の実践と研究のあり方(活動への参加とインクルーシブ保育―ごっこ遊びとルール遊びにおける参加と排除;見通しが不確実な中で保育を創造する―不確実さへの耐性と責任の問題;インクルーシブ保育時代までの歴史とインクルーシブ保育の実践上の課題)
著者等紹介
浜谷直人[ハマタニナオト]
東京大学大学院教育学研究科博士課程満期退学。首都大学東京人文科学研究科教授
芦澤清音[アシザワキヨネ]
東京都立大学大学院人文科学研究科博士課程単位取得退学、博士(教育学)。帝京大学教育学部教授。臨床心理士、臨床発達心理士
五十嵐元子[イガラシモトコ]
東京都立大学大学院人文科学研究科博士課程単位取得退学。帝京短期大学こども教育学科専任講師。臨床心理士
三山岳[ミヤマガク]
東京都立大学大学院人文科学研究科博士課程単位取得退学、博士(教育学)。愛知県立大学教育福祉学部准教授。臨床心理士、臨床発達心理士(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。