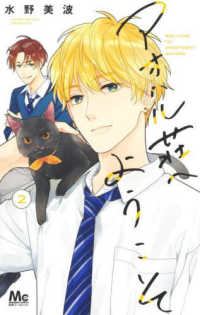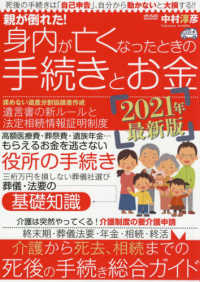出版社内容情報
新しい?地理的現実?を分析するために。経済地理学は今、どこまで到達したのか。経済学と地理が卯、方法論の統合を試みる。日本における経済地理学は、経済学の観点からの分析と、地理学の知見に依拠した考察を重視する学統に分かれて発展してきたが、本書は双方の学統を統一する可能性を模索するものである。経済循環の「空間的組織化」論という見地から、カール・ポランニーの「二重運動」論に依拠し国民経済の地域構造論を再構築することで、二系列の議論の並存という経済地理学を悩ませてきた事態を打開することを目指す。
序
序 章 経済地理学のために
1 本書の狙い
2 学説史的な基礎づけの強化――第一の課題
3 方法論の再構成――第二の課題
4 「二視角の統一」に向けて――第三の課題
5 「現状分析」の知としての経済地理学
補註 「地理学的思考」について
第?部 経済地理学の根本問題
第1章 地域構造論の新展開――「経済循環」視点の再検討に向けて
1 “地理的現実”の大転換
2 「経済の地域的循環」への着目
3 “産業論的パースペクティブ”の意義と問題点
4 経済循環の「空間的分岐」視点への転回
5 新展開の方向性
補註 限られた「資本財の転換可能性」が意味すること
第2章 経済地理学の「理論」についての考察――その位置づけをめぐって
1 アポリアとしての「理論」の位置づけ
2 「国民経済的視角」と「地域的視角」の統一という収斂方向
3 経済学と地理学の「学際領域の学問」ということの含意
4 理論と実証を結ぶもの――「経験的理論」としての地域構造論
5 経済地理学「復権」の条件
第3章 「未完のプロジェクト」としての地域構造論――市場社会における空間的組織化の構図
1 「地域」認識の革新を完遂するために
2 「経済循環」視点の徹底化が意味するもの
3 「二重運動」視点に基づく地域像の再検討
4 「空間的組織化」視点からみた市場社会における「地域」の生成
5 新しい“地理的現実”解明の鍵
第4章 サービス経済化の地理学――空間的組織化における「貯蔵」「輸送」「通信」の役割
1 “地理的現実”を変容させる二つの動力
2 サービス経済化をめぐる論議が迷走する理由
3 なぜ「貯蔵も輸送もできない」点を重視するか
4 経済循環の空間的組織化という視点
5 グローバル経済化への「対抗力」としての役割
第5章 「生産の地理学」を超えて――サービス経済化が地理学に問いかけているものは何か
1 「知識産業」に牽引されたサービス経済化
2 「認識論的障害」としての主導産業=「知識産業」説
3 “情報化社会”と“サービス社会”の「二重基調」
4 サービス経済化の地理的インパクト――「空間的組織化」論による解明
5 求められる経済循環の地理学への方向転換
第?部 国土政策論の再構築
第6章 「マクロ空間政策」としての国土政策――「ボーダーレス・エコノミー」の歴史的位相
1 「プラザ合意」の意義
2 現代資本主義の空間的フレームワーク
3 「マクロ空間政策」の成立と展開
4 変容する“マクロ空間”
5 空間論的アプローチの重要性
第7章 政策現象としての地域開発――方法論的再検討に関する覚書
1 政策論研究の社会科学化に向けて
2 地域開発をめぐる研究の二方向
3 「実践的要求」から出発する研究スタイルの難点
4 「実践的要求の基礎に向けて分析を進める」研究スタイルへの転換
5 社会科学としての焦点は「政策形成」過程の解明にある
補註 「問題地域」論の基礎としての山中「問題性」論
第8章 「国土政策」研究における経済地理学の役割――「構造―問題―政策」図式による地域構造論の拡充
1 「理論・歴史・政策」説への疑念
2 政策論研究の現状
3 「展望的」政策研究が看過したもの
4 経済地理学からの逆照射
5 問題群への注目による「地域構造」把握の立体化
第9章 戦後日本における国土政策展開の初期条件――「開発主義」対「貿易主義」論争とは何だったのか
1 「理念」と「現実」という問題設定の難点
2 川島哲郎の「徹底した産業政策」説
3 敗戦後の日本経済――緊急避難的「自給化」の展開
4 復興軌道をめぐる議論の経緯――「開発主義」から「貿易主義」への転回
5 「負の遺産」によって規定された国土政策の展開方向
第10章 戦後高度成長期の立地政策――「全総計画」始動のバックグラウンドを読み解く
1 歴史的勃興期の主役「太平洋ベルト」
2 戦後立地政策の「揺籃期」
3 「太平洋ベルト」構想の登場――国民的関心事となった立地
4 全総計画ついに始動す――「拠点開発」構想という“解”
5 立地政策の有効性を裏づけた「キャッチアップ型」成長
終 章 経済地理学の基礎にあるもの
1 関係論的視座への収束
2 ブラーシュ地理学の“ミッシング・リンク”
3 なぜ経済学と地理学で世界の「見え方」が違うのか?
4 資本主義社会という対象の特殊性
5 経済地理学の基礎にあるもの
6 新しい“地理的現実”の解明に向けて
補註 政策論研究をめぐる社会科学的な態度について
附論 初期論稿二篇
初期論稿1 経済地理学の方法に問する覚書――矢田俊文の「地域構造」論をめぐって
1 はしがき
2 経済地理学の混迷と「パラダイム転換」
3 矢田「地域構造」論の意義と問題点
4 経済地理学研究の基準――資本主義の発展段階と「地域差の処理機構」
5 むすび
初期論稿2 「地域構造」分析・序説
1 はしがき
2 地域経済成長をめぐる諸説の検討
3 「地域構造」分析への転回と未決問題
4 経済基盤脱による「地域構造」論再構成の試み
5 むすび
補註 マルクスの「時間による空間の否定」について
附論解題
跋文
文献一覧
人名索引
事項索引
加藤 和暢[カトウ カズノブ]
著・文・その他
内容説明
日本における経済地理学は、経済学の観点からの分析と、地理学の知見に依拠した考察を重視する学統に分かれて発展してきた。本書では双方の学統を統一する可能性を模索する。経済循環の「空間的組織化」論という見地から、カール・ポランニーの「二重運動」論に依拠し国民経済の地域構造論を再構築することで、二系列の議論の並存という経済地理学を悩ませてきた事態を打開することを目指す。
目次
経済地理学のために
第1部 経済地理学の根本問題(地域構造論の新展開―「経済循環」視点の再検討に向けて;経済地理学の「理論」についての考察―その位置づけをめぐって;「未完のプロジェクト」としての地域構造論―市場社会における空間的組織化の構図;サービス経済化の地理学―空間的組織化における「貯蔵」「輸送」「通信」の役割;「生産の地理学」超えて―サービス経済化が地理学に問いかけているものは何か)
第2部 国土政策論の再構築(「マクロ空間政策」としての国土政策―「ボーダーレス・エコノミー」の歴史的位相;政策現象としての地域開発―方法論的再検討に関する覚書;「国土政策」研究における経済地理学の役割―「構造‐問題‐政策」図式による地域構造論の拡充;戦後日本における国土政策展開の初期条件―「開発主義」対「貿易主義」論争とは何だったのか;戦後高度成長期の立地政策―「全総計画」始動のバックグラウンドを読み解く)
経済地理学の基礎にあるもの
附論 初期論稿二篇(経済地理学の方法に関する覚書―矢田俊文の「地域構造」論をめぐって;「地域構造」分析・序説)
著者等紹介
加藤和暢[カトウカズノブ]
1954年生まれ。1978年北海学園大学大学院修士課程修了、経済学修士。1983年北海道大学大学院農学研究科博士後期課程単位取得退学。日本学術振興会奨励研究員。1984年北海学園北見大学商学部専任講師。1986年同助教授。1988年釧路公立大学経済学部助教授(地域開発論・経済地理)。1995年同教授(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。