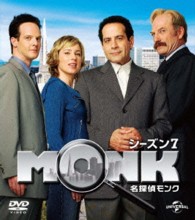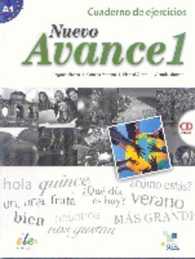出版社内容情報
文化人類学をより深く、詳しく学びたい読者のために 24のトピックから知る最前線の研究本書の目的は,文化人類学の基礎を学んだ学生を対象に,同分野をより深く掘り下げて解説すると同時に,新たな研究動向についても紹介することにある。全体を2部に分けて,第?部「基本領域」では,姉妹書の綾部恒雄・桑山敬己編『よくわかる文化人類学 第2版』(ミネルヴァ書房,2010年)の内容を詳述かつアップデートし,第?部「新たな展開」では最新の理論やテーマを取り上げる。
真剣に学びたい学生のために,学界を代表する研究者が力を結集して書いた入魂の一冊!
まえがき
第?部 基本領域
第1章 文化相対主義の源流と現代(桑山敬己)
1 文化相対主義の登場と発展
2 文化相対主義批判の古典的事例──言語相対論をめぐって
3 文化相対主義の現代的諸相
4 課題と展望
第2章 言語人類学(名和克郎)
1 前史および古典期
2 コミュニケーションの民族誌
3 現代言語人類学の展開
4 言語人類学の主張
5 課題と展望
第3章 狩猟採集社会──その歴史,多様性,現状(岸上伸啓)
1 狩猟採集社会の歴史
2 多様な狩猟採集社会
3 21世紀の狩猟採集社会──カナダ・イヌイット社会
4 狩猟採集の現代的な意義
5 課題と展望
第4章 文化と経済(山本真鳥)
1 贈与交換と互酬性
2 モラル・エコノミー
3 地域通貨
4 ジェンダーと経済
5 文化と資本主義経済
6 課題と展望
第5章 家族と親族(河合利光)
1 家族・親族研究の開始と展開
2 グローバル化の中の家族と親族
3 親族研究における西洋的二元論の克服
4 世界内存在としての身体と家族・親族
5 課題と展望
第6章 ジェンダーとセクシュアリティ(宇田川妙子)
1 ジェンダーの人類学,ジェンダー視点の人類学
2 ジェンダーとセックス
3 女性の可視化という問題
4 ジェンダーと権力
5 セクシュアリティ,トランスジェンダー,様々な性のかたち
6 課題と展望──視点としてのジェンダー
第7章 同時代のエスニシティ(綾部真雄)
1 誰がエスニックか
2 エスニシティ前夜
3 論 争
4 定義と定位
5 同時代のエスニシティ
6 課題と展望
第8章 法と人間(石田慎一郎)
1 争論の中での法の発見
2 争論を文脈化する──法との接点において働く力
3 他者を知る法理論──法のプルーラリズム/オルタナティブ
4 法の確定性を支えるメカニズム──法人類学のもう一つの筋書き
5 課題と展望──法人類学のさらなる筋書き
第9章 政治・紛争・暴力(栗本英世)
1 伝統社会の暴力と人権問題
2 東アフリカ牧畜社会の武力紛争
3 現代の民族紛争と内戦
4 課題と展望──戦争と平和という連続体
第10章 宗教と世界観(片岡 樹)
1 文化人類学と宗教
2 宗教とは何か
3 世界を意味づける
4 再び宗教とは何か
5 課題と展望
第11章 儀礼と時間(松岡悦子)
1 人類学における儀礼研究
2 リミナリティのもつ力──ヴィクター・ターナー
3 分類と境界
4 象徴研究とその先へ
5 課題と展望──グローバル社会における儀礼と政治
第12章 医療と文化(白川千尋)
1 非西洋医療への関心
2 多元的医療論
3 非西洋医療をめぐるグローバルな動向
4 病気のとらえ方
5 課題と展望
第13章 グローバリゼーションと移動(湖中真哉)
1 グローバリゼーションの人類学
2 グローバリゼーションとは何か──歴史化的転回
3 さまよえるグローバリゼーション研究──否定論的転回
4 ローカリティとフィールドの消滅──連接論的転回
5 グローバルなものとローカルなもの──存在論的転回
6 課題と展望──ポスト・グローバリゼーション的転回
第14章 開発と文化(関根久雄)
1 普遍性と個別性
2 言説としての開発
3 感情によって揺れる開発
4 「持続可能な開発」と文化
5 課題と展望
第15章 観光と文化(川森博司)
1 観光現象と文化人類学
2 観光のまなざしと生活文化
3 地域イメージと演じられる文化
4 情報化時代における場所の意味
5 課題と展望
第16章 民族誌と表象・展示(高倉浩樹)
1 民族誌とは何か
2 人類学と民族誌記述の歴史
3 民族誌の発展
4 民族誌批判
5 民族誌の可能性
6 課題と展望
第17章 フィールドワーク論(佐川 徹)
1 人類学的フィールドワークの特徴
2 フィールドワークの現在
3 フィールドワークにともなう倫理
4 フィールドワークで遭遇する危険と困難
5 課題と展望
第?部 新たな展開
第18章 構造主義の現代的意義(出口 顯)
1 構造の定義
2 文化と自然の連続
3 主体の解体,作者の死
4 神話が考える
5 構造主義の倫理
6 課題と展望
第19章 「もの」研究の新たな視座(床呂郁哉)
1 「もの」研究の系譜
2 近年の人類学における「もの」への回帰
3 「もの」研究のいくつかの視点
4 脱人間中心主義的人類学の可能性
5 課題と展望
第20章 災害とリスクの人類学(木村周平)
1 生活・環境・災害
2 被災(害)者という対象
3 災害というプロセス
4 リスクに備える
5 課題と展望
第21章 人とヒト──文化人類学と自然科学の再接合(田所聖志)
1 文化人類学の対象とする人とヒト
2 文化人類学からの「再接合」
3 自然科学からの接近
4 科学技術社会論と「再接合」
5 課題と展望
第22章 映像と人類学(田沼幸子)
1 映像と人類学の黎明期
2 科学と制度化
3 革命とアヴァンギャルド
4 共有」とは?──ネイティヴの視点から
5 課題と展望
第23章 認識論と存在論(綾部真雄)
1 社会科学の通奏低音
2 人類学と認識論
3 存在論的転回
4 パースペクティヴィズムの外延
5 課題と展望
第24章 日本研究の現在──医療人類学の視点から(北中淳子)
1 異なる近代としての日本──科学・医療人類学的視座
2 日本の医療研究──象徴主義と社会構成主義的アプローチ
3 ライフサイクルの医療化論
4 精神医学の人類学
5 課題と展望
人名索引
事項索引
桑山 敬己[クワヤマ タカミ]
編集
綾部 真雄[アヤベ マサオ]
編集
内容説明
本書の目的は、文化人類学の基礎を学んだ学生を対象に、同分野をより深く掘り下げて解説すると同時に、新たな研究動向についても紹介することにある。全体を2部に分けて、第1部「基本領域」では、姉妹書の綾部恒雄・桑山敬己編『よくわかる文化人類学第2版』(ミネルヴァ書房、2010年)の内容を詳述かつアップデートし、第2部「新たな展開」では最新の理論やテーマを取り上げる。真剣に学びたい学生のために、学界を代表する研究者が力を結集して書いた入魂の一冊!
目次
第1部 基本領域(文化相対主義の源流と現代;言語人類学;狩猟採集社会―その歴史、多様性、現状;文化と経済;家族と親族 ほか)
第2部 新たな展開(構造主義の現代的意義;「もの」研究の新たな視座;災害とリスクの人類学;人とヒト―文化人類学と自然科学の再接合;映像と人類学 ほか)
著者等紹介
桑山敬己[クワヤマタカミ]
1955年東京生まれ。東京外国語大学英米語学科、同大学院地域研究研究科修了。カリフォルニア大学ロサンゼルス校人類学部博士課程修了(Ph.D.)。ヴァージニア・コモンウェルス大学助教授、北海道大学大学院文学研究科教授などを経て、関西学院大学社会学部教授、北海道大学名誉教授
綾部真雄[アヤベマサオ]
1966年福岡県生まれ。筑波大学第二学群比較文化学類卒。東京都立大学大学院社会科学研究科博士前期課程修了。チェンマイ大学社会学部客員研究員を経て、東京都立大学大学院社会科学研究科博士後期課程単位取得退学。成蹊大学文学部国際文化学科専任講師、助教授を経て、首都大学東京大学院人文科学研究科教授。博士(社会人類学)(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
いまにえる
文狸
かぺら