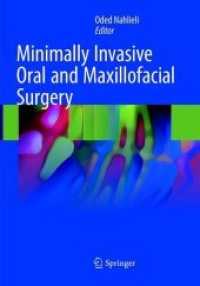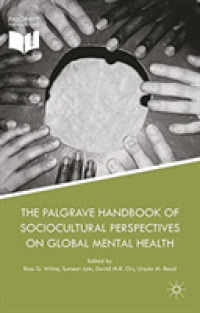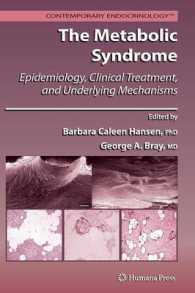出版社内容情報
教職を目指す大学生に向け、国語教育についてやさしく具体的に解説された入門書。現場をイメージしながらわかりやすく学べる新学習指導要領に沿った「話すこと・聞くこと・書くこと・読むこと」などの項目を踏まえ、国語教育の基礎から、単元デザインや学習指導案の作成とその評価など、これを読めばすぐにでも小学校の教壇に立てるような実践的な内容を詳細に取り上げた。
そのほか、言葉とコミュニケーション、アクティブラーニング、情報の扱い方、言語文化、書写、読書指導など、豊富な資料や図版を使ってわかりやすくポイントを押さえた解説で学びを深める入門書。
はじめに
第1章 国語科教育の目標と内容
1 言葉とコミュニケーション
2 言葉の獲得とコミュニケーション
3 言葉の働き
4 国語科教育の目標と内容
第2章 国語科教育の方法
1 言語活動の充実
2 アクティブラーニング
3 ICT教育
第3章 国語科の単元デザインと授業構想
1 「単元」の今日的意義
2 単元デザインおよび指導と評価の要諦
3 「単元」で育てるということ??内在する教育観
第4章 国語科学習指導案
1 学習指導案を書く目的
2 学習指導案の内容
3 国語科学習指導案の実際
第5章 「話すこと・聞くこと」の学習指導
1 「話すこと・聞くこと」の学習指導の基礎
2 話し言葉の位置づけ
3 新学習指導要領における話し言葉の位置づけ
4 「話すこと・聞くこと」領域の学習指導の実際
第6章 「書くこと」の学習指導
1 「書くこと」の学習指導において教師は何を目指すのか
2 「書くこと」の指導は一筋縄ではいかない
3 題材を工夫して書くことに日常的に取り組ませる
4 他者の文章を分析し良さを実感する場を設ける
5 教師があらゆることを抱え込まないようにする
6 「書くこと」の指導時間数は定められている
7 評価は「書くこと」の指導事項の達成状況によって行う
第7章 「読むこと」の学習指導??文学的文章
1 文学を読むことの学習で大切なこと
2 書かれてあることを理解すること
3 「読むこと」の落とし穴
4 文学を読む楽しみ
5 文学を読むことの意義
第8章 「読むこと」の学習指導??説明的文章
1 学習指導要領の意義
2 学習目標(指導事項)
3 教材,言語活動,手立て
4 具体的な教材で考える単元づくり??中学年教材で考える
5 各学年における単元づくり
6 新学習指導要領を味方にしよう
第9章 言葉の特徴や使い方に関する学習指導
1 「言葉の働き」について
2 「言葉の特徴(仕組み)」について
3 「言葉の使い方」について
第10章 情報の扱い方に関する学習指導
1 「情報の扱い方に関する事項」とは何か
2 各学年の「情報の扱い方」に関する事項の指導
3 単元に組み込んだ計画の一例
第11章 伝統的な言語文化に関する学習指導
1 伝統的な言語文化とは
2 伝統的な言語文化に関する学習を構想する
3 「伝統」とつきあうこと
第12章 書写の学習
1 「文字を書くこと」の学習としての書写
2 これからの書写学習に求められる視点
3 これからも工夫が求められる指導
第13章 読書指導
1 読書とは
2 読書指導の新学習指導要領での位置づけ
3 読書指導の目的
4 読書指導の方法
5 読書指導を行う教師として
小学校学習要領(抄)
索 引
原 清治[ハラ キヨハル]
監修
春日井 敏之[カスガイ トシユキ]
監修
篠原 正典[シノハラ マサノリ]
監修
森田 真樹[モリタ マサキ]
監修
井上 雅彦[イノウエ マサヒコ]
編集
青砥 弘幸[アオト ヒロユキ]
編集
目次
国語科教育の目標と内容
国語科教育の方法
国語科の単元デザインと授業構想
国語科学習指導案
「話すこと・聞くこと」の学習指導
「書くこと」の学習指導
「読むこと」の学習指導―文学的文章
「読むこと」の学習指導―説明的文章
言葉の特徴や使い方に関する学習指導
情報の扱い方に関する学習指導〔ほか〕
著者等紹介
井上雅彦[イノウエマサヒコ]
1960年生まれ。現在、立命館大学大学院教職研究科教授。主著に『伝え合いを重視した高等学校国語科カリキュラムの実践的研究』(渓水社、2008年)、『ディベートを用いて文学を‘読む’―伝え合いとしてのディベート学習活動』(明治図書、2001年)
青砥弘幸[アオトヒロユキ]
1981年生まれ。現在、佛教大学教育学部講師
原清治[ハラキヨハル]
佛教大学教育学部教授
春日井敏之[カスガイトシユキ]
立命館大学大学院教職研究科・文学部教授
篠原正典[シノハラマサノリ]
佛教大学教育学部教授(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。