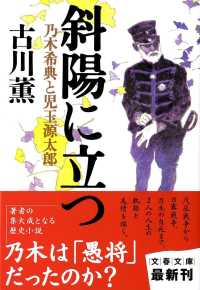内容説明
教育福祉論は、教育と福祉の連携、すなわち人間の豊かな発達と生活基盤の安定を同時に保障する必要性を訴えてきた。しかしながら、今日においても、貧困や差別といった諸問題から、それが実現されていない状況が続いている。本書では、教育と福祉が連携して、すべての子ども・若者の豊かな人間発達を保障するためにはどうすればよいのか、歴史的・原理的な展開を踏まえて、教育改革と地域づくりの視点から明らかにする。
目次
序章 教育福祉とは何か
第1章 教育福祉の理論
第2章 戦後日本における「教育と福祉」
第3章 「教育と福祉」の国際的な流れ
第4章 教育福祉で教育の改革を
第5章 教育福祉で福祉のまちづくりを
終章 教育福祉の実践のために
著者等紹介
辻浩[ツジユタカ]
1958年生まれ。1990年名古屋大学大学院教育学研究科博士課程後期課程単位取得退学(教育修士)。現在、日本社会事業大学社会福祉学部教授(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ゆう。
27
本著は、教育福祉論について、その系譜や歴史、実践を捉えることで、今日的な到達点を明らかにしようとした本です。すべての人間の豊かな発達と生活基盤の安定のために、教育と福祉はどのように連携していけばいいのか考察されていました。小川利夫の教育福祉論について詳細に論じられており、とても勉強になりました。小川利夫も著者も含め、社会教育の分野から福祉を捉えたところにこれまでの教育福祉論の特徴があるのかなと思いました。今日的に教育福祉論をどのように発展させていくのかは大きな課題でもあるのかなと思いました。2018/04/27
saiikitogohu
1
「スクールソーシャルワーカーの配置…二つの傾向…学校経営的な視点から校内で多職種が連携し、スクールソーシャルワーカーがそのコーディネートを行うという動きがあり、他方で、地域の力も活用して子どもと家族の問題を解決ないし緩和しようという動きがある。例えば、貧困に着目した時、いじめが起きないように校内で対策を立てることは前者であり、地域で営まれている子ども食堂や学習教室、世代間交流の機会を積極的に活用するような実践は後者である」6「完全雇用、住宅手当、社宅、扶養家族手当、医療保険、企業年金…」続2020/10/26
まりも
0
パラ読み2018/11/10
-
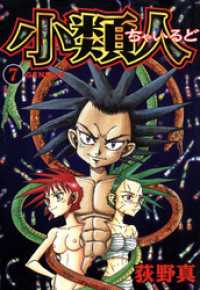
- 電子書籍
- 小類人 第7巻