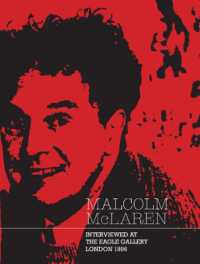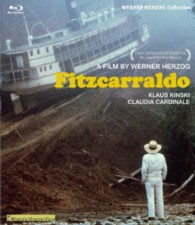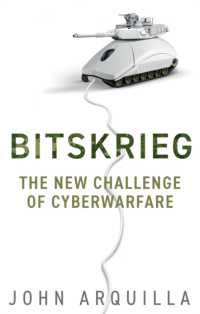内容説明
足利義持(一三八六~一四二八)室町幕府四代将軍。カリスマ的な父義満の跡を継ぎ、その「偉業」を転換していった足利義持。反動政策の背景には、国内外にわたり山積する諸問題があった。禅宗と儒学に精通した一級の知識人でもあった義持は、高邁な理想と過酷な現実のはざまで葛藤しながら、室町幕府をいかに確立へと導いたのか。
目次
序章 動乱の傷跡―生誕前
第1章 青春の日々―一〇代前後
第2章 親政の開始―二〇代前半
第3章 政道の刷新―二〇代後半
第4章 内外の憂患―三〇代前半
第5章 治世の試練 三〇代後半
第6章 応永の黄昏―四〇代前半
終章 守成の追憶―死去後
著者等紹介
吉田賢司[ヨシダケンジ]
1974年京都府生まれ。2004年龍谷大学大学院文学研究科博士課程単位取得満期退学。帝京大学講師を経て、龍谷大学文学部准教授。博士(文学)。専攻は日本中世史(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
Toska
19
地味なイメージの義持さんだが、実は吉川弘文館の人物叢書とミネルヴァ日本評伝選という伝記界の双璧を制した超大物。先に読んだ人物叢書版に続き、本書の完成度も高い。明晰な文体で読みやすく、義持の多彩な業績が要領よくまとめられ、その内面にも鋭く切り込んでいる。統治者としての才能と高度な文化的センス、そして何より厚い信仰心。仁政を心がけながら時に酷薄な顔を見せ、慈悲の心が却って事態を悪化させることも。過酷な現実との格闘、苦悩、挫折。読み終える頃には、主人公に対する不思議な共感を覚える優れた評伝。2025/06/24
浅香山三郎
19
ここ十数年で、応仁の乱前迄の室町幕府についての研究が進んでゐる。著者もその牽引者の一人で、堅実な仕事をされてゐるが、本書は足利義持の評伝といふ形で、幕府の性格を位置付ける。とくに、後小松上皇など朝廷や庭臣等との関係、堅実な政治手腕、義持を取り巻く大名や側近などを過不足無く描く。足利家当主=室町殿を体制の中で摂関家並の家格として確立するなど、改めて義持期の面白さが実感された。2018/07/09
MUNEKAZ
6
父・義満の路線を否定するのでなく、現実的なところに落とし込んでいく姿が印象的。とくに朝廷との関係では自身を「関白」に(強引に)擬すことで、その後の室町殿の家格を決定したというのは興味深かった。また調整型の政治家らしく、斯波義将・畠山満家・細川満元といった幕府首脳の存在感が大きいのも面白い。義持の統治者としての強烈な使命感と、彼らのような気骨ある守護大名たちがいたからこそ、幕府の安定期がもたらされたのであろう。2017/06/10
吃逆堂
4
言葉は少々難解だが、国際問題から国内情勢まで、個別の事件や事象を大枠の政治史の流れに丁寧に位置づけており、室町政治史の概説書としても良書。このまま義教期も!と思ってしまう。2017/10/30
ようはん
3
義満〜義教辺りの時代は戦乱が多かった室町時代の中では比較的安定期というイメージはあったが、この本を読んで見ると関東方面は完全に不穏であり対外的にも応永の外寇等で対明・朝鮮関係はかなりの緊張関係と義持時代ですら激動の時代であった事がよく分かる。晩年は次代の義教時代に禍根を残したのがマイナスであったが朝廷や守護大名との連携には成功し義教のような破滅をきたさなかった義持はもっと評価されるべきである。2019/04/01