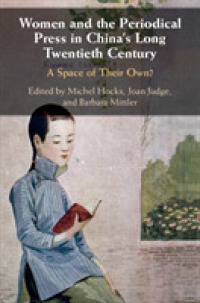出版社内容情報
夢・描画・現代美術の作品の語らいをラカンらの精神分析概念で辿る、主体の存在構造を解く鮮烈な表現論。(解説・新宮一成)無意識言語の不可視の形と現代美術の不可聴域の声を統合し得た本書は、構造論的精神分析の範を成す希有の達成である。[新宮一成(精神科医)推薦]
ことばにならないことばで、誰が何をどのように語っているのか。私たちの表現や表象作用としての夢・描画・現代美術の作品たちの語らいを、具体的なエピソード・作品とともに、フロイト、ラカンの精神分析概念によって辿り、その主体生成の原点へと迫る。誰もが抱き得る自分とは何かという問いは、精神分析と現代美術の交点として浮かび上がる。「私」という表現する存在構造を解く鮮烈な表現論。巻末に解説・新宮一成(精神科医)。
序 章 表現されることとすることへの問い――いのちと存在を発見する
私たちの精神活動と話す主体の表現
表象の造形が話すということ
夢という表象――精神分析という窓から
さまざまな夢の相
第1章 夢の語らい――イメージたちがつくる動きとそのかたち
死者が話す夢
フロイトの夢
夢で繰り返される構造
フキタンポポの夢の構造
夢の中のトポロジー
覚醒の主体と往還運動
欲動と同一化
誰でもない私,誰かとしての私
第2章 鏡像段階と寸断された身体――存在のはじまりにおけるバラバラとまとまり
つねに,もう事ははじまっているのだから
寸断された身体をめぐって
メラニー・クラインの概念――良い乳房・悪い乳房
クラインから再びラカンへ
逃げ去るファルスと寸断された身体
対象aと一の線
第3章 内と外にある危機――内面と歴史,その解体の表象たち
主体が蹂躙される世界
無意味へと向かう旅
チューリヒ・ダダ――キャバレー・ヴォルテール
言葉を見放すことと虚無
フロイトの無常
巨人の出現
鏡像と「機械」
第4章 行為とその対象――子どもの描画場面における主体性の位置変換
ある描線
象徴による乗り越え
投射と表象
抽象化と固有の言語
描画の中で起こった主体の位置変換
描画の過程と言語活動の関わり
主体の位置変換と身体性の在処
関係性の変換と象徴化
第5章 抽象の意味と構造――こころの軌跡をかたちにする
意味とかたち
カンディンスキーの抽象
芸術における精神的なもの
汝ひとりにとって
抽象と同時代性
内的必然性
画中を逍遥させる
無意識の受容
「現実」を超える芸術運動と精神分析
クルト・シュヴィッタース――こころの中の現実
「偶然の詩論」
抽象の意味
主体生成の動き
第6章 〈見る/見られる〉のマトリックス――みる,みられる,みせられる,そしてじぶんをみる
見ていることは見られていることでもある
スクリーンと双極構造
意識の唯物論的定義
「狼男」の夢における〈見る/見られる〉の双極構造
〈見る/見られる〉のマトリックス
マトリックスの文法
「目覚め」としてのセッションの終わり
ある日の精神分析――多声部の音楽のような語らい
残される主体と目覚めに出発する主体
目覚める主体を他者に託して自らは眠りゆくということ
第7章 固有の言語の語らい――みることのことば,みられるもののことば
パリにおけるマルセル・デュシャンの試み
『裸体』から『大ガラス』へ
意識の運動そしてレディ・メイド
インストラクション・アート
コンセプチュアル・アート――コスースの「椅子」
1つと3つの存在
自己言及的な領域
インスタレーションにおける語らい
ふたりとふたつの時計
「不在」を写す写真から血液のビーズへ
キャンディーの積み重なり
作品の実体性と私秘性の空間
同一化の感覚と二つの動き,そして無音の声部としての鑑賞者
失われゆくもの,そして私秘性の内側へ
問いの営み
初出一覧
おわりに
解 説(新宮一成)
人名索引
事項索引
岡田 彩希子[オカダ アキコ]
2017年3月現在京都大学大学院人間・環境学研究科博士後期課程修了、博士(人間・環境学)
新宮 一成[シングウ カズシゲ]
2017年3月現在 京都大学名誉教授、奈良大学社会学部教授
内容説明
ことばにならないことばで、誰が何をどのように語っているのか。私たちの表現や表象作用としての夢・描画・現代美術の作品たちの語らいを、具体的なエピソード・作品とともに、フロイト、ラカンの精神分析概念によって辿り、その主体生成の原点へと迫る。誰もが抱き得る自分とは何かという問いは、精神分析と現代美術の交点として浮かび上がる。「私」という表現する存在構造を解く鮮烈な表現論。
目次
序章 表現されることとすることへの問い―いのちと存在を発見する
第1章 夢の語らい―イメージたちがつくる動きとそのかたち
第2章 鏡像段階と寸断された身体―存在のはじまりにおけるバラバラとまとまり
第3章 内と外にある危機―内面と歴史、その解体の表象たち
第4章 行為とその対象―子どもの描画場面における主体性の位置変換
第5章 抽象の意味と構造―こころの軌跡をかたちにする
第6章 “見る/見られる”のマトリックス―みる、みられる、みせられる、そしてじぶんをみる
第7章 固有の言語の語らい―みることのことば、みられるもののことば
著者等紹介
岡田彩希子[オカダアキコ]
京都大学大学院人間・環境学研究科博士課程修了。2016年3月、博士(人間・環境学)。専門は現代美術・精神分析。構造分析研究会に所属
新宮一成[シングウカズシゲ]
精神科医。京都大学医学部卒業。京都大学大学院人間・環境学研究科教授を経て、京都大学名誉教授、奈良大学社会学部教授。精神分析の視点から妄想や幻覚などの精神病理的体験の理解に努める。構造分析研究会主宰(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。