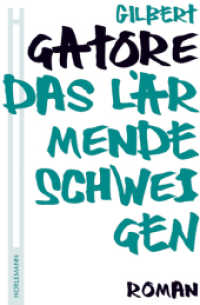出版社内容情報
天台座主にして征夷大将軍の皇族武将、鎌倉倒幕に駆けた28年の数奇な人生。護良親王(1308~1355)鎌倉時代後期の皇族
皇族武将護良親王は、南北朝動乱期に一代の軍事英雄として華々しく登場した。だが、護良の足跡には謎が多い。本書では内乱期中世を疾風のように生きぬいた護良のすべてを、大胆な史料の読み直しを通して明らかにする。
朱に染まる護良親王――プロローグ
第一章 不思議の門主
1 武力信奉の天台座主
2 軍を告げる太鼓の響き
第二章 京と鎌倉
1 武力志向の伏流
2 衰える鎌倉の力
第三章 忍び忍びに
1 護良の蜂起
2 般若寺に逃れる
3 熊野、南大和の山岳活動
第四章 護良と楠木、赤松
1 姿をみせる反乱軍勢
2 吉野山に挙兵する
3 畿南の戦乱、赤松を動かす
第五章 落ちぬ六波羅
1 京都へ攻め上る赤松軍
2 落ちるのは金剛山か六波羅か
3 決め手となる足利の六波羅攻撃
第六章 征夷大将軍
1 護良の新たな戦い
2 武家の軍事制度を引き継ぐ
3 三つ巴の暗闘――後醍醐・護良・尊氏
第七章 父子愛憎
1 鎌倉へ流される
2 京の陰謀と地方の蜂起
3 非業の最期
第八章 護良の怨念
1 尊氏の反逆に倒れる後醍醐政権
2 護良の遺子大塔若宮
3 不思議なりし御謀叛
参考文献
あとがき
護良親王略年譜
人名・事項索引
新井 孝重[アライ タカシゲ]
2016年8月現在 獨協大学経済学部教授(日本社会史)
内容説明
護良親王(一三〇八~一三三五)鎌倉時代後期の皇族。皇族武将護良親王は、南北朝動乱期に一代の軍事英雄として華々しく登場した。だが、その足跡には謎が多い。本書では内乱期中世を疾風のように生きぬいた護良のすべてを、大胆な史料の読み直しを通して明らかにする。
目次
第1章 不思議の門主
第2章 京と鎌倉
第3章 忍び忍びに
第4章 護良と楠木、赤松
第5章 落ちぬ六波羅
第6章 征夷大将軍
第7章 父子愛憎
第8章 護良の怨念
著者等紹介
新井孝重[アライタカシゲ]
1950年埼玉県生まれ。1973年早稲田大学第一文学部卒業。1983年早稲田大学大学院文学研究科博士後期課程修了、博士(文学)。現在、獨協大学経済学部教授(日本社会史)(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
こぽぞう☆
鯖
いきもの
Minoruno
ほうすう
-

- 電子書籍
- 冥途地獄学園 1 ヤングジャンプコミッ…