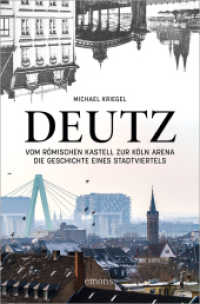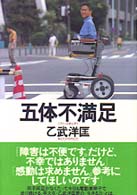出版社内容情報
書の美しさはどこから来るのか。はじめて解き明かされた筆蝕の美学![解説:高階秀爾]刻ることから始まった書の歴史は、楷・行・草書体の成立とともに、筆と墨と紙の芸術としての書の美を生みだした。〈書は美術ならず〉論争以来の書論を再検討し、甲骨文から前衛書までの書の表現を構造的に解き明かす![解説:高階秀爾]
序 書とはどういう芸術か??筆蝕の美学
はじめに
序 章 書はどのようなものと考えられて来たか
第一章 書は筆蝕の芸術である??書の美はどのような構造で成立するか
第二章 書は筆・墨・紙の芸術である??書の美の価値はなぜ生じるのか
第三章 書は言葉の芸術である??書は何を表現するのか
第四章 書は現在の芸術でありうるだろうか??書の再生について
書??筆蝕の宇宙を読み解く
第一講 書の表現の根柢をなすもの??筆蝕について?
第二講 反転しあう陰陽の美学??筆蝕について?
第三講 垂線の美学??書と宗教
第四講 整斉、参差、斉参??旋律の誕生
第五講 書のなかの物語??旋律の展開
第六講 折法の変遷と解体??リズムについて
第七講 表現行為としての書??書と織物
第八講 書のダイナミックス??筆勢について
第九講 結字と結構??書と建築
第十講 ムーブメントとモーション??書と舞踊
第十一講 甲骨文、金文、雑体書??書とデザイン
第十二講 余白について??書と環境
九楊先生の文字学入門
はじめに
第一講 表 現
第二講 動 詞??筆蝕すること
第三講 場
第四講 主 語
第五講 述 語
第六講 単 位??筆画
第七講 変 化
第八講 接 続??連綿論
第九講 音 韻??筆蝕の態様
第十講 形 容
第十一講 接 辞
第十二講 構 文
講義レジュメ
凡 例
解 題
解 説 弁証法の美学??書の表現をささえるもの(高階秀爾)
石川 九楊[イシカワ キュウヨウ]
書家・評論家
内容説明
刻ることから始まった書の歴史は、楷・行・草書体の成立とともに、筆と墨と紙の芸術としての書の美を生みだした。“書は美術ならず”論争以来の書論を再検討し、甲骨文から前衛書までの書の表現を構造的に解き明かす!
目次
序 書とはどういう芸術か―筆蝕の美学(書はどのようなものと考えられて来たか;書は筆蝕の芸術である―書の美はどのような構造で成立するか;書は筆・墨・紙の芸術である―書の美の価値はなぜ生じるのか ほか)
書―筆蝕の宇宙を読み解く(書の表現の根柢をなすもの―筆蝕について1;反転しあう陰陽の美学―筆蝕について2;垂線の美学―書と宗教 ほか)
九楊先生の文字学入門(表現;動詞―筆蝕すること;場 ほか)
著者等紹介
石川九楊[イシカワキュウヨウ]
1945年福井県越前市生まれ。京都大学法学部卒業。京都精華大学教授、同大学文字文明研究所所長等を歴任。現在、書家、評論家、京都精華大学客員教授。主著、『書の終焉』同朋舎出版、1990年、サントリー学芸賞受賞。『日本書史』名古屋大学出版会、2001年、毎日出版文化賞受賞。『近代書史』名古屋大学出版会、2009年、大佛次郎賞受賞(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。