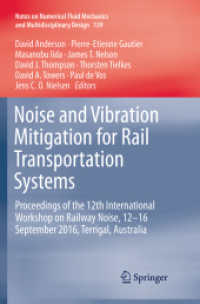出版社内容情報
エピソードを記述し、読み合い、語り合う。そこから見えてくる、保育という営みに込められた保育者と子どもたちの思い。9か園、延べ40名を超える保育者たちが、2年の歳月をかけて編み上げた60のエピソード記述。そこから、子どもを理解するということの意味、保育者が子どもの傍らにいることの意味、子どもが保育者とともに保育の場を生きることの意味を考えていく。また本書全体を通して、保育をエピソード記述によって省みることの重要性と、一方でエピソード記述を描くことの難しさが提示されており、そこからはエピソード記述に基づく保育実践に取り組む糸口も見えてくる。
まえがき
第1章 “しる”と“わかる”とエピソード記述
1 子どもが世界と出会う保育の場と保育者の仕事
2 なぜ、保育の場の子ども理解にエピソード記述は有効なのか
第2章 感性的子ども理解=“わかる”がなぜ重要なのか
1 ぎこちない抱っことしっくり抱っこ
2 “抱っこしなければ”が“抱っこしていたい”に変わる
3 子どもが気持ちを伝えてくれる瞬間を見逃さない
第3章 保育の場のエピソードを記述する、読み合う
1 保育者がエピソード記述に向かうとき
2 記述する、リライトする
3 エピソード記述を読み合う
第4章 実習ノートとエピソード記述
1 実習ノートを読む
2 エピソード「なっちゃんの赤いほっぺ」を読む
3 複数の“読み”の可能性
第5章 “しる”と“わかる”を相補的な関係に位置づける
1 “しる”と“わかる”の相補的関係
2 保育セッションと不文の指導案を再考する
3 鍵概念を整理する──まとめにかえて
あとがき
室田 一樹[ムロタ イツキ]
著・文・その他
内容説明
9か園、延べ40名を超える保育者たちが、2年の歳月をかけて編み上げた60のエピソード記述。そこから、子どもを理解するということの意味、保育者が子どもの傍らにいることの意味、子どもが保育者とともに保育の場を生きることの意味を考えていく。また本書全体を通して、保育をエピソード記述によって省みることの重要性と、一方でエピソード記述を描くことの難しさが提示されており、そこからはエピソード記述に基づく保育実践に取り組む糸口も見えてくる。
目次
第1章 “しる”と“わかる”とエピソード記述(子どもが世界と出会う保育の場と保育者の仕事;なぜ、保育の場の子ども理解にエピソード記述は有効なのか)
第2章 感性的子ども理解=“わかる”がなぜ重要なのか(ぎこちない抱っことしっくり抱っこ;“抱っこしなければ”が“抱っこしていたい”に変わる;子どもが気持ちを伝えてくれる瞬間を見逃さない)
第3章 保育の場のエピソードを記述する、読み合う(保育者がエピソード記述に向かうとき;記述する、リライトする;エピソード記述を読み合う)
第4章 実習ノートとエピソード記述(実習ノートを読む;エピソード「なっちゃんの赤いほっぺ」を読む;複数の“読み”の可能性)
第5章 “しる”と“わかる”を相補的な関係に位置づける(“しる”と“わかる”の相補的関係;保育セッションと不文の指導案を再考する;鍵概念を整理する―まとめにかえて)
著者等紹介
室田一樹[ムロタイツキ]
1955年8月18日、京都市生まれ。1980年3月、國學院大學大学院修士課程文学研究科神道学専攻単位修得退学。同年4月、岩屋保育園園長就任。2002年12月、岩屋神社宮司就任。元皇學館大学社会福祉学部准教授。現在、社会福祉法人岩屋福祉会岩屋こども園アカンパニ理事長/園長・岩屋神社宮司(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。