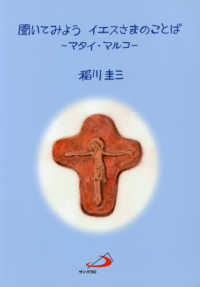出版社内容情報
幸福が訪れない世界で、私たちはなぜ明日もう一日生きてみようと考えるのか? まちづくりとは、希望を場所に刻印することなのだまちづくりを問うことは、私たちがなぜ生きているかを問うことだ。なぜなら、まちは「世界は生きるに値するか?」という問いの参照先だからだ。
私たちは幸福になれないことが約束されているにもかかわらず、なぜ明日もう一日生きてみようと考えるのか?私たちはただ一つの生きる動機付けである希望をまちから与えられることでかろうじて生きていける。まちづくりとは、その希望を場所に刻印することなのだ。
まえがき(代官山ステキなまちづくり協議会 野口浩平)
第一章 まちづくりとは何か
空間が異方的なまち
身体化した感覚地理
祝祭的な時空の体験
逃げ場がなく苦しい
微熱感に満ちたまち
我有化によって抗う
どこでもない場所へ
場所が自分を変える
心と環境の応答関係
目黒付近の昭和初期
共存した自然とまち
混沌がもたらす幸い
IT化と感情の劣化
見えない化での抗い
システムの先鋭化へ
第二章 よいまちとは何か
都市におけるアート
耳元に戦ぐ琉球の風
日常の構造が変わる
コルビュジエの衝撃
スケール感の奇妙さ
多様性を回復させる
日常に不可欠な雑音
計算不可能性の設計
ニーズに応じぬ権力
街区は多い方がいい
意志するべき複雑性
「近代」を使い尽くせ
オーセンティシティ
人間スケールの超出
ヨーロッパに見習え
コミュニティ空洞化
感情の劣化への注目
感情に鈍感な社会学
例外的なパーソンズ
アリストテレス以降
頓挫したエリート論
ファシリテーターへ
少子高齢化と人本意
ミクロな再生可能性
埋め込む価値の伝承
反アイデンティティ
行政が共同体を支援
感情エリートが必要
価値を組込む行政へ
適応主義者への折伏
第三章 よいまちは実現するか
身体的領域の外側へ
ルソーとシュミット
近代の根本的な矛盾
普遍主義はローカル
社会の中にある科学
共同体が技術を評価
民主の科学化への道
科学の民主化への道
感情の働きの相対化
超越と、共同体の自立
ルールか信頼醸成か
ホッブズと信頼問題
換骨奪胎された普遍
思考停止の独立運動
まちづくりの物象化
小さな政府への、誤解
震災復興の重要視点
経済原則の一人歩き
第四章 まちづくりは幸福を実現するか
塀がないから安全だ
期待し合わない人々
ナンパ系とオタク系
〈自己〉の時代とは?
現実と虚構の等価化
社会的文脈の消去へ
性的退却の二〇年間
性的退却の背景とは
自己防衛化の回避策
変性意識は近代の敵
新人類世代への期待
超越系の人間の実存
超越系を欠けば滅ぶ
超越系への拘束用具
切れたリレーション
超越に再び開かれよ
帰属感覚が失われた
ノスタルジーの正体
終わりなき日常とは
日常が輝かない理由
「ここの読み替え」へ
脳だけで生きるのか
本来性に向かう運動
受苦的疎外論の地平
存在価値こそ公共的
地獄絵になる未来像
人間中心主義の限界
生き物としての場所
社会という荒野から
対談を終えて(蓑原 敬)
あとがきにかえて――まちづくりイベントに降臨したメルツバウ(宮台真司)
1 私たちはいまどんな時代を生きているか
2 音体験は時代につれて大きく変わりゆく
3 「蝕の時代」にはメルツバウを聴くと良い
4 〈世界〉はそもそもデタラメであるとは
索 引
代官山ステキなまちづくり協議会[ダイカンヤマステキナマチヅクリキョウギカイ]
蓑原 敬[ミノハラ ケイ]
2016年3月現在蓑原計画事務所代表。神戸芸術工科大学客員教授
宮台 真司[ミヤダイ シンジ]
2016年3月現在首都大学東京教授
内容説明
幸福が訪れない世界で、私たちはなぜ明日もう一日生きてみようと考えるのか?まちづくりとは、希望を場所に刻印することなのだ。
目次
第1章 まちづくりとは何か(空間が異方的なまち;身体化した感覚地理 ほか)
第2章 よいまちとは何か(都市におけるアート;耳元に戦ぐ琉球の風 ほか)
第3章 よいまちは実現するか(身体的領域の外側へ;ルソーとシュミット ほか)
第4章 まちづくりは幸福を実現するか(塀がないから安全だ;期待し合わない人々 ほか)
あとがきにかえて―まちづくりイベントに降臨したメルツバウ(私たちはいまどんな時代を生きているか;音体験は時代につれて大きく変わりゆく ほか)
著者等紹介
蓑原敬[ミノハラケイ]
1933年生まれ。1958年東京大学教養学部アメリカ科卒業。1960年日本大学理工学部建築科卒業、建設省入省。現在、蓑原計画事務所代表
宮台真司[ミヤダイシンジ]
1959年生まれ。1990年東京大学大学院社会学研究科博士課程社会学博士学位取得。社会学博士。東京大学教養学部助手、東京外語大学専任講師などを経て、首都大学東京都市教養学部教授(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
はすのこ
takahiroyama3
ぷほは
yokkoishotaro