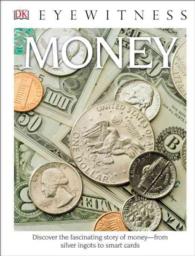内容説明
子どもの心の発達のしくみを理解し、保育・教育の実践や自閉症理解を深めるために、「心の理論」の最先端の研究から発達の基礎を捉えなおす。本書は、季刊『発達』135号の特集内容に最新の知見をくわえ、また新たな章を組み入れ再構成したもので、多角的・重層的に「心の理論」を捉え、子どもたちの多様な発達の姿をわかりやすく説明する。
目次
1 心の発達のしくみを理解するために(いまなぜ「心の理論」を学ぶのか;「心の理論」と表象理解―2~4歳児はどんな心の世界に生きているか;「心の理論」と実行機能―どのような認知機能が誤信念課題に必要か?;ミラーシステムと「心の理論」―認知神経科学的アプローチ;「心の理論」の発達の文化差―日本・韓国・オーストラリアの比較から)
2 保育・教育の現場で子どもを理解するために(乳児期の「心の理論」―赤ちゃんはどこまでわかっている?;幼児期の“心の理解”―心を理解するということが“問題”となるとき;児童期の「心の理論」―大人へとつながる時期の教育的視点をふまえて;「心の理論」と感情理解―子どものコミュニケーションを支える心の発達;「心の理論」と教示行為―子どもに教えるのではなく子どもが教える;「心の理論」と保育―保育のなかの子どもたちにみる心の理解;「心の理論」の訓練―介入の有効性)
3 自閉症児を理解するために(自閉症児の「心の理論」―マインド・ブラインドネス仮説とその後の展開;自閉症スペクトラム指数(AQ)と「心の理論」
自閉症児と情動―情動調整の障害と発達
自閉症と三項関係の発展型としての「心の理論」
自閉症児への心の読み取り指導
自閉症児の善悪判断)
著者等紹介
子安増生[コヤスマスオ]
京都大学大学院教育学研究科博士課程中退。博士(教育学)。現在、京都大学大学院教育学研究科教授(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
-

- 和書
- 基礎システム工学