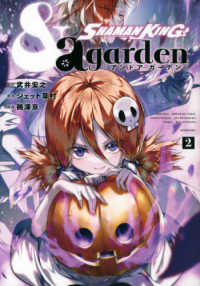出版社内容情報
大人との関係の中で子どもたちの描画活動を支える実践をしてきた著者が、詳細なエピソード記述からその過程を丁寧に読み解く本書からは、保護者には子育てのヒントが、保育者には保育のヒントが、研究者には新しい研究の視点と研究方法のヒントが得られるに違いありません。――鯨岡 峻氏(京都大学名誉教授)
育ちの初期段階で「描く」ことを通して子どもの内面で育まれるものとは何でしょうか? また、小さな手で描かれる「痕跡の描画」がだんだんと「絵」に近づく過程からは、どのような育ちの姿が捉えられるのでしょうか? 本書では、大人との関係の中で子どもの描画活動を充実させる実践をしてきた著者が、詳細なエピソード記述からその過程を丁寧に読み解きます。
本書を読んで──推薦のことば
はじめに
本書のエピソードについて
第1章 描画のはじまり
1 初めて描く──手を動かした痕を見つける
2 目の前の景色を変える──自分の意思で描く
3 見ていてほしい──描きながら振り向く
4 わたしはここにいます──存在を主張する
5 にじみ出る個性──「描く」に向かって力を発揮する
6 「描く」とその周辺の表現から
第2章 「あなた」とのあいだに生まれる「え」
1 「わたし」と「あなた」をつなぐ「もの」──三項関係の中で承認を求める
2 あいだにあるもの──お互いの思いを感じる
3 わくわくする──楽しい気分が作用し合う
4 いっしょに描いて──?一緒に遊ぶ場面をつくる
5 きれいだね──「え」の価値を知る
6 「あなた」とのやりとりから
第3章 主張する「え」
1 どうしてもほしい──自分の意思を押し通す
2 泣いて「わたし」になる──自分の気持ちを表明する
3 わたしだって描く──?線を重ねる
4 「わたしが」してあげる──描き方、遊び方を先導する
5 「わたしが」描きたい──描く主体が「あなた」と分かれる
6 主張する姿から
第4章 ぐるぐる線から構成へ
1 まわせ、まわせ──活動力を発揮する
2 回転させたい──気持ちに従って体を動かす
3 形の発見──形を描いて主張する
4 ぐるぐるを並べたい──円錯画を構成する
5 円錯画を描く姿から
第5章 「わたしたち」から物語をはじめる
1 「わたし」の思い──気持ちがことばになる
2 「わたしたち」をつなぐことば──ことばでつながる
3 「わたしも」話せる──ことばを交わす
4 物語のはじまり──イメージを語る
5 「わたしたち」の絵──イメージをともにして遊ぶ
6 ことばを発し、イメージを語る姿から
第6章 感じる主体として描くということ
1 体と心で感じ取る──両手を使って描く
2 「いま、この場」の喜び──?体の「感じ」を求める
3 力をこめる──だんだん主体を立ち上げる
4 こわいけどやる──感じ方が転換する
5 「感じる」から価値の体験へ
記録──子どもの体験を見つめる大人のプロセス
文献一覧
おわりに
片岡 杏子[カタオカ キョウコ]
著・文・その他
内容説明
育ちの初期段階で「描く」ことを通して子どもの内面で育まれるものとは何でしょうか?また、小さな手で描かれる「痕跡の描画」がだんだんと「絵」に近づく過程からは、どのような育ちの姿が捉えられるのでしょうか?本書では、大人との関係の中で子どもの描画活動を充実させる実践をしてきた著者が、詳細なエピソード記述からその過程を丁寧に読み解きます。
目次
第1章 描画のはじまり
第2章 「あなた」とのあいだに生まれる「え」
第3章 主張する「え」
第4章 ぐるぐる線から構成へ
第5章 「わたしたち」から物語をはじめる
第6章 感じる主体として描くということ
著者等紹介
片岡杏子[カタオカキョウコ]
東京都生まれ。美術教育研究者。東北芸術工科大学大学院修士課程で絵画制作を学び、学校教員、子育て支援施設の職員を経て、東京学芸大学大学院連合博士課程に入学。芸術系教育講座に在籍し、2008年から2年間の学内プロジェクトとして乳幼児親子を対象とする描画活動の縦断観察研究を実施、2010年に単位修得満期退学。2011年、実践研究論文「子どもの表現に、物語はなぜ必要か―2歳の描画遊びの応答から」で第46回教育美術・佐武賞受賞(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。