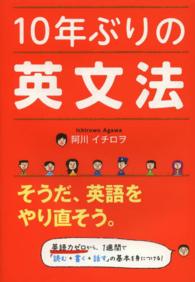出版社内容情報
6人の園長と汐見稔幸氏との対談を通じて、いま求められる保育のグランドデザインについて考えていく“対話”が生み出す保育の未来
いま目の前にいる子どもたちの未来を思い、一緒に語り合ってみませんか?
本書ではまず、保育実践者である六人の園長と長年にわたり保育研究をリードし続けている汐見稔幸氏との対談を通じて、いま求められる保育のグランドデザインについて考えていく。そしてこれらの対談を踏まえ、実践者・研究者それぞれの立場から、子どもの育ちや未来の社会を思い、保育のグランドデザインを描く。そこから見えてくる、保育という営みに込められた子どもたち・社会・未来への願いとは――子どもを思うすべての人に届けたい一冊。
はしがき(久保健太)
序 学習とは何かということを考える:保育のグランドデザインを描くために(久保健太)
第?部 保育のグランドデザインを考える:対談 6人の園長×汐見稔幸
対談1 子どもが、自分の「ドラマ」の主人公として生きるために(鈴木まひろ×汐見稔幸)
【対談を終えて1】 環境に保育者の「願い」や「意図」を埋め込む(鈴木まひろ)
対談2 子どものアートと小さな共同体(室田一樹×汐見稔幸)
【対談を終えて2】 産育習俗から対談をふり返る(室田一樹)
対談3 人類の知恵と保育のグランドデザイン(藤森平司×汐見稔幸)
【対談を終えて3】 保育の質について考える(藤森平司)
対談4 大人主導と子ども主導のバランス(片山喜章×汐見稔幸)
【対談を終えて4】 傾きや偏りを意識しながら(片山喜章)
対談5 地域の文化のなかで保育をするということ(當間左知子×汐見稔幸)
【対談を終えて5】 子どもを大事にする文化を守るために(當間左知子)
対談6 柔らかさを育む柔らかな保育が発信するもの(遠山洋一×汐見稔幸)
【対談を終えて6】 保育士の配置基準と保育のあり方(遠山洋一)
対談を読んで見えてきたこと:その1(島本一男)
対談を読んで見えてきたこと:その2(福田泰雅)
第?部 保育のグランドデザインを描くために
1 「共に創る保育」の実現をめざして(遠山洋一)
2 新たな幼児教育観への転換は「子どもに意見を聴く」ことから(鈴木まひろ)
3 「聴き入ること」から拡がる保育の世界(森 眞理)
終 グランドデザインを論じ合うということ(汐見稔幸)
あとがき(藤森平司)
汐見 稔幸[シオミ トシユキ]
2016年3月現在白梅学園大学・同短期大学学長
久保 健太[クボ ケンタ]
2016年4月現在関東学院大学
内容説明
本書ではまず、保育実践者である六人の園長と長年にわたり保育研究をリードし続けている汐見稔幸氏との対談を通じて、いま求められる保育のグランドデザインについて考えていく。そしてこれらの対談を踏まえ、実践者・研究者それぞれの立場から、子どもの育ちや未来の社会を思い、保育のグランドデザインを描く。そこから見えてくる、保育という営みに込められた子どもたち・社会・未来への願いとは―子どもを思うすべての人に届けたい一冊。
目次
序 学習とは何かということを考える―保育のグランドデザインを描くために
第1部 保育のグランドデサインを考える―対談 六人の園長×汐見稔幸(子どもが、自分の「ドラマ」の主人公として生きるために―鈴木まひろ×汐見稔幸;子どものアートと小さな共同体―室田一樹×汐見稔幸;人類の知恵と保育のグランドデザイン―藤森平司×汐見稔幸;大人主導と子ども主導のバランス―片山喜章×汐見稔幸;地域の文化のなかで保育をするということ―當間左知子×汐見稔幸;柔らかさを育む柔らかな保育が発信するもの―遠山洋一×汐見稔幸;対談を読んで見えてきたこと―その1;対談を読んで見えてきたこと―その2)
第2部 保育のグランドデザインを描くために(「共に創る保育」の実現をめざして;新たな幼児教育観への転換は「子どもに意見を聴く」ことから;「聴き入ること」から拡がる保育の世界)
終 グランドデザインを論じ合うということ
著者等紹介
汐見稔幸[シオミトシユキ]
1947年生まれ。白梅学園大学・同短期大学学長
久保健太[クボケンタ]
1978年生まれ。関東学院大学教育学部専任講師(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
- 評価
京都と医療と人権の本棚
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ゆう。
akiu