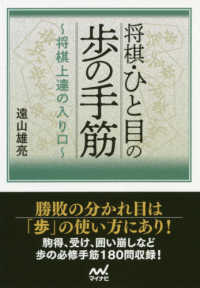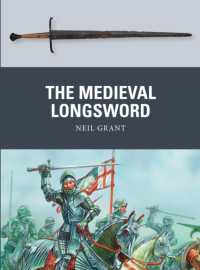内容説明
日本は膨大な財政赤字のなかで年金・医療・介護など社会保障をめぐる問題を抱えている。本書は、その周辺に横たわる貧困・出生率、働き方、教育問題にも目を配り、総合的に日本の社会全体を見通す。これからの社会をつくっていく18歳の若者にもわかりやすく、やさしい語り口でポイントを整理。公共経済学を利用し、今まで見えなかった問題を把握、これからの生き方を模索する試み。
目次
序章 社会保障とはなんだろうか
第1章 社会保障に対するアプローチ
第2章 財政問題をどう考えるか
第3章 年金・医療・介護が抱える問題
第4章 貧困問題にどう対応するか
第5章 子育て支援をめぐる課題
第6章 働くことの意味を問い直す
第7章 経済学で教育を語れるか
第8章 社会の「有り様」をめぐって
著者等紹介
小塩隆士[オシオタカシ]
1960年生まれ。1983年東京大学教養学部卒業。2012年博士(国際公共政策)(大阪大学)。経済企画庁(現内閣府)等を経て、一橋大学経済研究所教授(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 1件/全1件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
1.3manen
32
公共経済学者の本(ⅰ頁)。社会保障は昔からあったわけでなく、社会が産業化するまでは、リスク分散機能は家族、地域社会が担ってきた(2頁)。問題は、社会保障が人口減少させる効果があること(5頁)。本書が類書にないのは、人口動態、低成長時代への移行、非正規拡大という変化を念頭に、社会保障を考えている点(9頁)。先送り負担は、将来世代で負担しきれず、制度はどこかで破綻する。重要なのは、高齢者層向けの給付拡大に若年層が負担上げを受け入れず、日本の将来は危険(21頁)。2016/03/05
Francis
10
公共経済学者が社会保障を論じた本。財政赤字は国民の保有する資産と合わせて考えるべき、消費税の逆進性は所得税の累進度の修正などで十分解消可能なレベル、あるいは日本の少子化は非婚化の要因の方が大きい、など目からうろこの事実がデータを通して見えてくる。自分も社会保障の仕事に携わる身なので、この本の内容はかなり首肯できる内容だった。2017/07/26
Mc6ρ助
4
良書。18歳から、いやすべての有権者、日本に住む人にお勧めしたい。目から鱗はいくつ落ちることか。OECD諸国での比較、相対的貧困率で見て、31カ国中下から五番目(再配分前)、再配分による改善率も下から六番目。要するに日本は先進国のなかで、貧しい国に属し所得の再配分もうまく機能していない・・・(p127,表4-2)。著者自身が自分で考えろ、といっているのだが、考えてどう行動すべきか、その答えをいまの日本は誰も持たないようにみえる。もちろん自分自身も含めて。2016/03/29
りん
0
大学の頃社会保障論が苦手で、でも年金税金を納めている身としては分かっておかないと、と思って初心者向けを読みました。ぱらぱらとめくって読みやすくて選んだものですが、経済学の視点からというのが新鮮で、少子化の原因や今後の財源についてもおもしろいと感じました。尚且つ、根拠として多く提示されるデータもありきたりのものばかりでなくて「へえ、そうなんだ!」と思うものが多かったです。 とにかく、苦手な社会保障をおもしろいと感じられたのが嬉しいです。2018/01/10
-
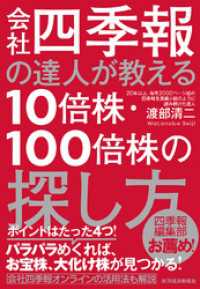
- 電子書籍
- 会社四季報の達人が教える10倍株・10…
-

- 和書
- 力学 - MIT物理