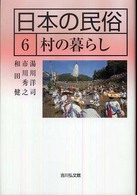内容説明
それはいかなる「戦い」だったのか。核兵器開発、西側同盟、脱植民地化、文化変容…「冷たい戦争」の歴史的要素をめぐる本格的探究。
目次
新しい冷戦認識を求めて―多元主義的な冷戦史の可能性
第1部 西側同盟内関係と冷戦(同盟から冷戦を考える;イギリスの原爆開発と冷戦―一九四五~一九四七年;同盟要因と同盟国の対米影響力―キューバ・ミサイル危機における米英関係;ブラント政権の東方政策と独米関係―一九六九~一九七二年;ヨーロッパ・アメリカ・ポンド―EC加盟と通貨統合をめぐるヒース政権の大西洋外交、一九七〇~一九七四年;天然ガス・パイプライン建設をめぐる西側同盟―一九八一~一九八二年)
第2部 脱植民地化と冷戦(西欧への二つの挑戦―脱植民地化と冷戦の複合作用;東南アジアにおける脱植民地化と冷戦の開始―想像上の共産主義の恐怖はいかにして生成されたか、一九四七~一九四九年;チュニジア・モロッコの脱植民地化と西側同盟;国連組織防衛の論理とカタンガ分離終結―一九六二~一九六三年;コンゴ(ブラザヴィル)共和国をめぐる中台国交樹立競争
冷戦・アパルトヘイト・コモンウェルス―イギリス対外政策と南アフリカへの武器輸出問題、一九五五~一九七五年)
第3部 国内の文化・社会の変容と冷戦(冷戦と文化的なもの;アメリカを超えるジャズと冷戦;戦後ドイツ音楽文化と冷戦―占領期ベルリンにおけるアメリカの音楽政策、一九四五~一九四九年;冷戦とプロテスタント教会―東ドイツ国家による教会政策の展開と「社会主義の中の教会」;スペイン内戦・冷戦・民主化―アメリカの労働組合と対スペイン政策)
著者等紹介
益田実[マスダミノル]
1965年山口県生まれ。1994年京都大学大学院法学研究科退学。博士(法学)。現在、立命館大学国際関係学部教授
池田亮[イケダリョウ]
1970年大阪府生まれ。2006年ロンドン大学ロンドン・スクール・オブ・エコノミクス(LSE)国際関係論博士課程修了。Ph.D.(国際関係史)。現在、関西外国語大学英語キャリア学部准教授
青野利彦[アオノトシヒコ]
1973年広島県生まれ。2007年カリフォルニア大学サンタ・バーバラ校歴史学研究科博士課程修了。Ph.D.(歴史学)。現在、一橋大学大学院法学研究科准教授
齋藤嘉臣[サイトウヨシオミ]
1976年福岡県生まれ。2005年神戸大学大学院法学研究科博士後期課程修了。博士(政治学)。現在、京都大学大学院人間・環境学研究科准教授(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
わび
たけふじ
たけふじ
-
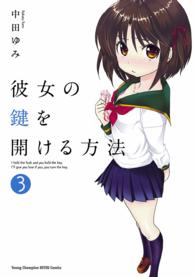
- 電子書籍
- 彼女の鍵を開ける方法 〈3〉 ヤングチ…