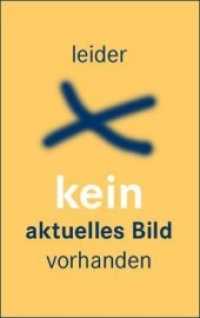内容説明
光厳天皇(一三一三~一三六四)北朝第一代天皇。南北朝の動乱の中で、皇統の正嫡として生まれた責任を誠実に果たそうとしながら、乱世の渦に巻き込まれて波瀾に満ちた生涯を送った光厳天皇。最後には山寺で一禅僧として静かに生を終えた一人の「人」の姿を描く。没後六百五十年記念出版。
目次
第1章 両統迭立
第2章 量仁親王の誕生と修学
第3章 春宮の時代
第4章 天皇の時代
第5章 太上天皇の時代
第6章 治天の君の時代
第7章 貞和五年・光厳院の目
第8章 幽囚の時代
第9章 禅僧の時代
著者等紹介
深津睦夫[フカツムツオ]
1953年岐阜県生まれ。名古屋大学大学院文学研究科修了。博士(文学)。現在、皇學館大学教授。専攻は中世和歌史(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
MUNEKAZ
13
北朝の初代天皇の評伝。後醍醐天皇や足利尊氏に運命を翻弄されながらも、持明院統の正統として、北朝の治天の君として父母から託された役割を律義に貫き通す姿勢は、影の薄いこの帝の矜持を見るようで興味深い。ライバル後醍醐帝が無念を抱え吉野で生を終えたのに対し、自らの役割を終え山寺で一人の禅僧として平穏に入寂を迎えたことは感動的ですらある。『風雅和歌集』の編纂や琵琶の伝承など著者の専門を生かした文化面での考察も面白かった。2020/02/03
KF
11
南北朝時代となると後醍醐天皇、楠木正成と南朝寄りの読物が多い。幕府の足利尊氏についても良く読んでいくと北にも南にも着いて乱世を乗り切って行っている。その中で北朝方の持明院統について書かれた書物は比較的少ないと思う。吉川英治の私本太平記も北朝方と言うより足利方だった。今回この北朝の「初代」天皇について読んでみて、これまで全く教育の場で触れられた事が無かったことを痛感した。難しい時代を担う羽目になった所から、偉大な生き方を残していった事が伝わってきた。日本史の立場では裏側の皇室だが人格の気高さを感じられた。2022/05/31
浅香山三郎
11
中世和歌の研究者による評伝。歿後650年の2014年に刊行された。本書を読む迄、光厳天皇が歌人として、日本文学の側でこれ程重視されてゐる人だといふことを知らなかつた。『風雅和歌集』といふ勅撰集を読み解き、歌集のなかに反映された光厳院のよしとする秩序や、武士の歌を採るといふ意識を探る。持明院統の家長(治天の君)としての意識と、花園院に対する複雑な感情(直仁親王の出生と立坊)、南朝軍による拉致など、その人生は波乱に富み、後醍醐天皇の影に隠れてやや地味にも映る光厳院もまた、魅力的な人であつたことが分かる。2021/12/13
mk
6
南北朝の皇統対立の荒波に人生を揺るがされながらも、激動の時代を生き抜いた北朝初代天皇の評伝。勅撰和歌集研究の専門家である著者が、深い精神性を評価されてきたその詠歌や残された文書の手堅い読解を通じて、後醍醐天皇と並ぶもう1人の帝王の等身大の人生を丁寧に描く。『太平記』の歴史観の下では脇役にしか映らない光厳院の波乱の生涯を知ることは、南北朝時代を見直す視点を与えてくれる。最晩年の一禅僧としての生き様も静かだが強烈。本書も引用するこの和歌も深い印象を残す。「心とてよもにうつるよ何ぞこれただ此の向ふともし火の影」2018/08/06
Minoruno
4
持明院派、大覚寺派の皇位を巡る複雑な駆け引きや鎌倉幕府との関係性、治天の君となった後の政治体制など持明院派・北朝側から見た鎌倉〜南北朝の変遷が面白かった。どうしても後醍醐天皇の存在感が強いが、こちらも相当激動の人生を送っている。著者の専門が中世和歌ということで、勅撰和歌集「風雅集」の詳細な解説や、光厳天皇が重要視した琵琶の伝承など文化面からの考察が非常に勉強になった。2017/02/28