内容説明
国立競技場はどのように生まれ変わり、その後、どのような歴史を辿っていくのか…。サッカージャーナリストの第一人者が問いかける力作、ついに刊行。
目次
第1章 明治神宮の造営と競技場
第2章 最新の設計思想に基づいた明治神宮外苑競技場
第3章 明治神宮大会の開催と一九二〇年代の日本のスポーツ
第4章 外苑競技場での国際大会、そして幻の東京オリンピック
第5章 戦中・戦後の明治神宮外苑と日本のスポーツ
第6章 復興の槌音―国立競技場の建設
第7章 東京オリンピックの開催
第8章 「企業アマ」からクラブスポーツへ
終章 二〇二〇年オリンピック開催と国立競技場の将来
著者等紹介
後藤健生[ゴトウタケオ]
1952年東京生まれ。慶應義塾大学大学院法学研究科政治学専攻博士課程修了。現在、サッカージャーナリスト、元関西大学客員教授(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 1件/全1件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
mura_ユル活動
41
古い建築が解体されること、記憶がなくなること。この国立競技場もその一つ。建設当初は100年前の明治神宮造営の外苑計画に遡る。大正期や昭和初期の日本のスポーツの歴史がこんなにも波乱万丈であったとは。13校問題や文部省と内務省の争い、戦争の影響、政治利用。1924年に建てられた国立競技場は、当時、日本ではやっていなかったサッカーを視野に入れて計画されていたことはすばらしいこと(小林内務省技師)。1940年の幻の東京オリンピックは知りませんでした。サッカージャーナリストの著。図書館本。2014/02/15
Kouro-hou
7
日本最初の国立スタジアムとその周辺事情の本。明治神宮成立から奉納の意味もあってできた外苑競技場。やっとスポーツも近代化して一致団結して世界を目指す、と思いきや学生の扱いを挟んで内務省と厚生省が争ってます。人間とは争うモノらしいです。その後もプロとアマとか、学生と実業団とか、大会招致は決まったけど国内は一本化しないとか争いは絶えず、大会寸前にコート完成とか、なんだー日本もブラジルW杯と一緒だwという気分になれます。一時期は確実にサッカーより人気のあったラグビーの栄枯盛衰考察にも考えさせられます。2014/11/01
東隆斎洒落
5
14.03.09◆著者はサッカージャーナリストであるが、内容はスポーツのみならず、建築・軍隊・日本文化に至り、読み応えのある一冊。◆関東は「国立」「神宮球場」「秩父宮」が全て国立・官営であるのに対し、関西の「甲子園「花園」は、阪神・近鉄の私営。メッカの東西の生い立ちにナルホド。◆戦争で未実現の1940年東京五輪のメインスタジアムは埋立地新設、実現した1964年五輪は国立を改修。未実現の2016年五輪は埋立地新設、実現する2020年五輪は、国立改修。歴史は繰り返す?なんとも面白い。2014/03/09
BATTARIA
2
旧国立競技場が明治神宮外苑にできた背景や、戦前の神宮外苑競技場時代からの国立競技場や、幻の1940年東京五輪など、戦前戦中からの日本のスポーツが、わかりやすく通史としてまとめられている。企業アマチュアスポーツチームが実業団と呼ばれた背景や、大学から実業団にスポーツの主役が移ったのは、思ったより最近だったとか、スポーツの所管をめぐる内務省・厚生省・文部省の暗闘や、プロとアマチュアをめぐるドロドロが想像以上に根深かったこと等々、新たな発見がいっぱい。フルシチョフ失脚が東京五輪期間中とは、もっと驚いた。2018/09/17
Mimuchi
0
スポーツの歴史と合わせて理解できるので面白い2014/01/28
-
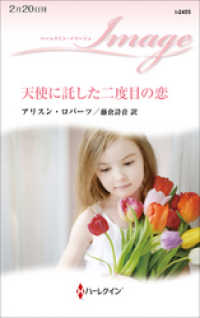
- 電子書籍
- 天使に託した二度目の恋 ハーレクイン
-

- 電子書籍
- あんハピ♪ 7巻 まんがタイムKRコミ…







