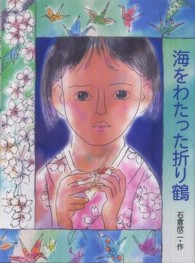内容説明
「陰徳」の思想のもと、江戸時代の豪商たちが困窮者を救済していた事実を史料から発掘し、彼らの「陰徳善行」の精神文化がいかに醸成され普及したのかを探る。いま、改めて「陰徳」という精神文化を認識し、格差にあえぐ現代社会のあり方を人々の精神の根底から見直すことを目指す。
目次
第1章 米騒動と福井県三国の救貧対策
第2章 内田家に関する史料
第3章 “陰徳の豪商”内田惣右衛門の公私の社会貢献
第4章 内田惣右衛門の天保飢饉時における救貧活動
第5章 江戸時代の豪商による救貧活動
第6章 豪商らはなぜ「積善陰徳」を行ったのか
著者等紹介
大塩まゆみ[オオシオマユミ]
同志社大学文学部社会学科社会福祉学専攻卒業後、(株)日本地域社会研究所を経て、同志社大学大学院文学研究科社会福祉学専攻修士課程・博士課程修了。博士(社会福祉学)。滋賀文化短期大学人間福祉学科助教授、福井県立大学看護福祉学部社会福祉学科教授を経て、龍谷大学社会学部地域福祉学科・大学院社会学研究科社会福祉学専攻教授。研究分野:社会福祉学(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
壱萬参仟縁
7
日本のCSRの原点。福田徳三先生の紹介もあり(4頁)。生存権を求める運動を、との思想は今日的意義も高い。生活苦をどうするのか、というのは、生活保護制度があるように、今日的にも本質は変わっていないのではないか。内田惣右衛門は知らなかった。彼はフィランソロピストで、失業者や低所得者のため、また、神社の整備で大工を仕事にありつけるようにしたとも書いてある(60,62頁)。なかなかできたことではない。恭倹とは人に慎みやすく控えめに、積善とは善行を蓄積すること(72頁)。こうした倫理のかけらもない自営業商人に喝っ!2013/05/22
塞翁が馬
5
「積善陰徳」を実践した内田惣右衛門(福井県・廻船業)を紐解く史料。現代日本の企業の慈善活動(CSR)は宣伝に近いが、陰徳は仏教、儒教、道教の三教が統合した中国伝来の思想で、見返りを期待しない純粋な救済精神に則り実践されていた。飢饉の際の米の廉売や仕事の斡旋、失業者救済の為の寺や学校を建設する社会事業や困窮者の救済活動もしていた。その際に恩恵を受けた人が心の負担にならないように細やかな配慮(魚心に水心の態度)も徹底していた。日本オリジナルの社会福祉精神があることに感銘を受けた。2025/06/09
-
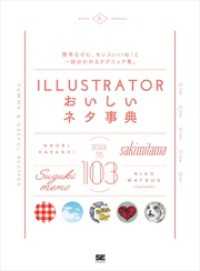
- 電子書籍
- Illustratorおいしいネタ事典