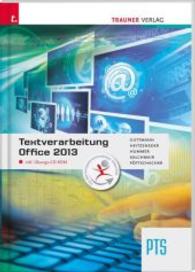内容説明
「学ぶ」というのは知識の詰め込みのことではない。学ぶことによって自分が変わる―それが「学び」の正しい姿だ。哲学もしかり。哲学を学ぶことによって世界が違って見えてくる。常識をひっくり返す思考のアクロバット。そこにはいったいどんなマジック、いやロジックがあるのか。本書によって、読者は哲学の魅力を存分に味わうことができるだろう。
目次
第1章 創造的思考の基礎
第2章 普遍性の相の下に
第3章 問いの操作
第4章 思考の転回
第5章 概念の操作
第6章 媒介の思考
著者等紹介
甲田純生[コウダスミオ]
1965年大阪生まれ。大阪大学大学院博士後期課程(哲学哲学史専攻)修了。博士(文学)。現在、広島国際大学准教授。カント、ヘーゲルを中心とするドイツ観念論の研究からスタートしながらも、現代ドイツ・フランス思想やマルクス経済学、精神分析学など幅広い関心領域のもとに、普遍的人間学の構築を目指す、新進気鋭の哲学者(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
masabi
19
【要旨】ある種のものの見方とその見方で物事がどう変わるかを示す。【感想】哲学的思考と言われるものがどんなスタイルなのかを提示するカタログみたいなもの。常識に囚われない、あるいは常識を反転させるということが分かりやすく書いてある。個人的にはヘーゲルの量から質の変化という部分が以前から悩んでいた箇所だったのでその理解の一助となった。2016/10/22
void
2
【★★★☆☆】常識を疑う・物事の両面性をみること(=創造性)。特殊なものでも普遍の下にみること。問いそのものの妥当性・水準をみること。因果は逆になってないか。対概念は対のままで・一定の量を越えると質が変化する(質に限界値がある)。因果の過程をより細かく、媒介を意識する。ってなのが哲学的思考法の特徴だよって本。フロイト心理学も多め。あとがきで「勇み足」と自戒しているように、突っ込みどころは少なくないし、方法論だったら論理学の本のほうが有益。でも読んでて「それどうなの」と疑問が出やすいから、良い訓練にはなる。2013/08/20
絵具巻
1
文京区立水道端図書館で借りました。2012/07/29
わし
1
殺人の禁止について、原因と結果の逆転についての記述が興味深かった。 2012/07/13
ぐりにゃる
0
この本を読んでなにが変わったのだろうか、ということを問い続ける必要があると思うに至るなど。本を読むことに限らず、何かを知覚して、それについて考えるということは、その前後で自分が変質させるきっかけになるように思う。その本に書いてあったことがどんなに素晴らしいか、よりも、その本を読んで自分は何を得たのか、ということを問い続けたい。筆者の言いたいことは、こんな感じだろうか。問い続ける姿勢は大切。疲れるけどね。2012/06/15