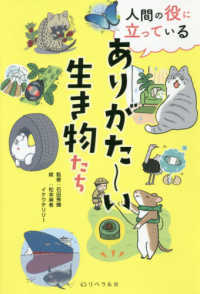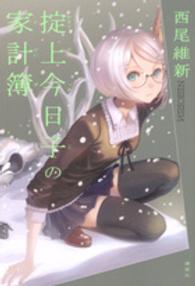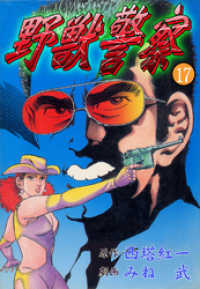内容説明
本書は、市井の人の言葉や文章を細やかに拾いながら、当時の人びとの暮らしぶりや悩みの背景を再現させた『大正期の家族問題』『昭和前期の家族問題』に続く待望の完結編である。戦後の大混乱と社会改革を越えて、空前の経済成長に湧く一方、不遇な子どもたちや夫婦間の軋轢など、現代につながる昭和の家族の変貌を描く。
目次
第1部 終戦直後の混乱と改革―一九四五~五〇年(混乱と窮乏のなかで;夫婦は同権、親子は平等;家族関係の現実)
第2部 生活向上と新生のとき―一九五一~六五年(戦後からの脱出;昭和三〇年代の明るさとうしろ側;近代家族は生まれたか)
第3部 経済成長下の家族の動揺―一九六六~八八年(揺らぐ伝統的な結婚観;不遇な子をどう救うか;国際婦人の一一年と家族;家族を揺さぶる波風;戦後正和で家族はどう変わったか;家族不安感の克服に向けて)
著者等紹介
湯沢雍彦[ユザワヤスヒコ]
1930年東京都生まれ。東京都立大学人文学部社会学専攻・同法学専攻卒業。東京家庭裁判所調査官、お茶の水女子大学教授、郡山女子大学教授、東洋英和女学院大学教授を経て、お茶の水女子大学名誉教授、養子と里親を考える会理事、地域社会研究所理事(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。