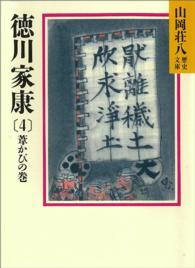内容説明
武田勝頼(一五四六~八二)甲斐の戦国大名。信玄という偉大な父から家督を継ぎ、強大な軍団を擁しながらも、長篠合戦に敗れ、ついには武田家を滅亡させた勝頼。猪突猛進型武将という従来の固定観念から脱し、統治者や文化人としても優れていた素顔を明らかにする。
目次
第1章 若き日の諏訪勝頼
第2章 武田家相続
第3章 食うか食われるか
第4章 長篠合戦の真実
第5章 領国の立て直し
第6章 御館の乱と勢力拡大
第7章 束の間の安定
第8章 武田家滅亡
第9章 勝頼の統治
第10章 勝頼の人柄と文化
著者等紹介
笹本正治[ササモトショウジ]
1951年山梨県生まれ。1974年信州大学人文学部卒業。1977年名古屋大学大学院文学研究科博士課程前期修了。現在、信州大学人文学部教授。博士(歴史学)(名古屋大学)(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 1件/全1件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
roatsu
15
同時代から恣意的に形成された通説と異なり、英邁で覇気に富む、信玄公の後継足るに相応しい資質を持つ青年武将だった勝頼公の実像が浮かび上がる。書状引用が多いが、同人の高い教養と配慮の細やかさ、宿敵の織田徳川を始め同時代の武田家が抱えた外交や内政事情をよく伝えて非常に良い手法と思う。穴山や木曽など武田滅亡の引金を引いた裏切者が早くからマークされていた事実は興味深い。一時的にせよ時代の寵児だった信長が席巻する中では滅亡は不可避だったかもしれないが、それでも最善と言える奮闘の末に滅びた名君の実像は今も強く胸を打つ。2016/10/29
中島直人
14
無能な後継ぎという役割を当てられてしまった武田勝頼の名誉挽回を目論んだ評伝。著者の勝頼を持ち上げたいとの意思は強く感じるが、なら何故、前代あれだけ強力だった武田家が、こうも脆くも呆気なく崩壊したのかが分からなくなってしまう。そういう意味で、迫力不足説得力不足で物足りない。2017/05/04
電羊齋
5
主に武田勝頼の発給文書および各種史料を通じて、国を滅ぼした「猪突猛進型武将」という勝頼への評価の再考を行っている。ちなみに、長篠の戦いの敗因については、単純に兵力差によるものとしている。本書は、長篠敗戦後の領国統治の立て直し、軍役改革、外交戦略に力点が置かれている。勝頼の重商主義的側面と御館の乱での勝頼の行動に対する著者の評価も興味深い。武田氏は長篠から一気に滅亡へと向かったのではなく、勝頼の各方面での涙ぐましい努力と気配りにより一定の成果を収めたが、それでもなお滅亡に至ったというのが正しいらしい。2014/11/08
wang
0
文学作品によって作られた勝頼像を離れ、実在の文書等で武田勝頼がどういう人物であったかを探ろうとした書。諏訪家の後継者としてスタートした勝頼の領主像を描いた部分や、新府城に移り新しい武田領国支配を固めようとする部分など著者自身の言葉で書かれた部分はよく書けている。が、その他はやたらと引用が多く読みにくい。全文引用必要なのか?さらに全訳と要約が続き本書の3分の2近くが引用ではないかと思うと水増しにすら感じる。適切な要約と重要文書の引用で読みやすく書かれていればもっとよかった。2016/01/23
suwa_shiro
0
猪突猛進型で長篠の合戦で家臣の意見を無視して大敗し、そこから坂を転げ落ちるように衰退して名家を滅ぼした武将、それが私の子供時代に一般的に言われていた武田勝頼のイメージだった。本書はそんな武田勝頼の生涯を資料から丹念に検証している。新府城の築城、御館の乱での動き、税の徴収など、基本的に勝頼の失策だといわれてきた行動が実は理にかなったものであったことに驚いた。2023/12/26