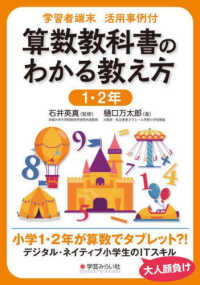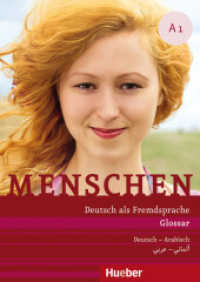内容説明
古来より日本人は膨大な日記を書き残してきた。この日記こそは、日本の歴史や文化を本格的に学ぶ際に欠かせない史料である。本書では、平安後期から戦国期までの約五百年間の重要かつ特徴ある日記一六点を取り上げ、最先端の研究者が分かりやすく紹介する。また、同時代の日記についても近年の成果や情報を巻末に盛り込んだ有用な一冊である。
目次
日記で読む日本中世史
第1部 中世前期の日記(『中右記』(藤原宗忠)―宗忠の見た白河院政
『台記』(藤原頼長)―学問と武のはざまで ほか)
第2部 南北朝・室町期の日記(『園太暦』(洞院公賢)―最後の王朝貴族
『満済准后日記』(満済)―黒衣宰相がリードした室町政治 ほか)
第3部 戦国期の日記(『政基公旅引付』(九条政基)―公家の在荘直務と戦国社会
『言継卿記』(山科言継)―庶民派貴族の視線 ほか)
著者等紹介
元木泰雄[モトキヤスオ]
1954年兵庫県生まれ。1983年京都大学大学院文学研究科博士課程後期課程指導認定退学。博士(文学)。現在、京都大学大学院人間・環境学研究科教授。中世前期政治史専攻
松薗斉[マツゾノヒトシ]
1958年東京都生まれ。1988年九州大学大学院文学研究科博士後期課程単位取得満期退学。現在、愛知学院大学文学部教授、同人間文化研究所長。日本中世史専攻(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ぽんすけ
7
中世研究に必須な日記16作を取り上げダイジェスト的に解説した本。だけどダイジェストと言っても各日記の特色や背景などはきちんと押さえられているので、それぞれがどの研究細目に当てはまるかわかりやすい。こうして読んでみると日記って本当に面白いなと感じる。私の学生の頃は教授の好みだったのか何なのかわからないけど、日本中世史はひたすら荘園文書を読み込むというもので凄まじく苦行だった。あと網野善彦先生が絶対神みたいな感じだったので、作中できちんと網野説を批判批評してるところは個人的におおっ!となった。じっくり再読も可2023/04/06
月音
4
取り上げる時代範囲が広く、日記の記録者(記主)の身分、日記の内容が多岐にわたるにもかかわらず、散漫な印象は受けない。時代順に並べながら、記主と記された人物、出来事が前後で緩やかにつながり、一本の歴史の流れとなっているからだろう。個人を通して歴史を見るか、歴史の流れの中の個人を見るか、16点の日記それぞれの研究者の切り口は鮮やかで変化に富む。公家から武家の世に変わっていく過程での公家側の動向はアクティブであり、有為転変の身を嘆き、衰退していくイメージが一新された。⇒続2023/12/19
そーだ
4
『中右記』『台記』『平範記』『玉葉』『明月記』『民経記』『花園天皇日記』『園太暦』『満済准后日記』『看聞日記』『蔭凉軒日録』『親長卿記』『大乗院寺社雑事記』『政基公旅引付』『言継卿記』『駒井日記』の以上16の日記が取り上げられている。刊本などの書誌情報が充実していて、入門書として良くできていると思う。活字化さえしてれば日記は読めると思うので、興味があるものは読み下しや現代語訳がなくても取り組むべきだと思う。2013/12/12
桜花
3
中世の公家の日記について解説した本。私は御堂関白記、紫式部日記、枕草子しか知りませんでした。だから意外と数々の日記が記されていて驚きました。日本人って書くことに対してはすごい情熱を昔から持っているんですね。また今と違い公家の儀礼などに関して書きためるというのが理由でそれが家の誇りだったようです。2016/09/05
tatu
1
同時代の人が記した日記は、第一級の史料である。中世の日記が「家」の記録であり、個人的な事項を記すことよりも、儀式の手順や書面のやり取りを記録し、家業の参考資料的な役割を持つものであることを再認識した。家が困窮した場合に、経済的価値を持って取引されることから、その家に留まらず、普遍的な価値を有していたのであろうか。掲載されている日記について、その性格を把握するのに非常に有用である。2017/11/22
-

- 電子書籍
- 冷酷眼鏡とウワサされる副騎士団長様が、…
-

- 和書
- 新ビジネス実務論