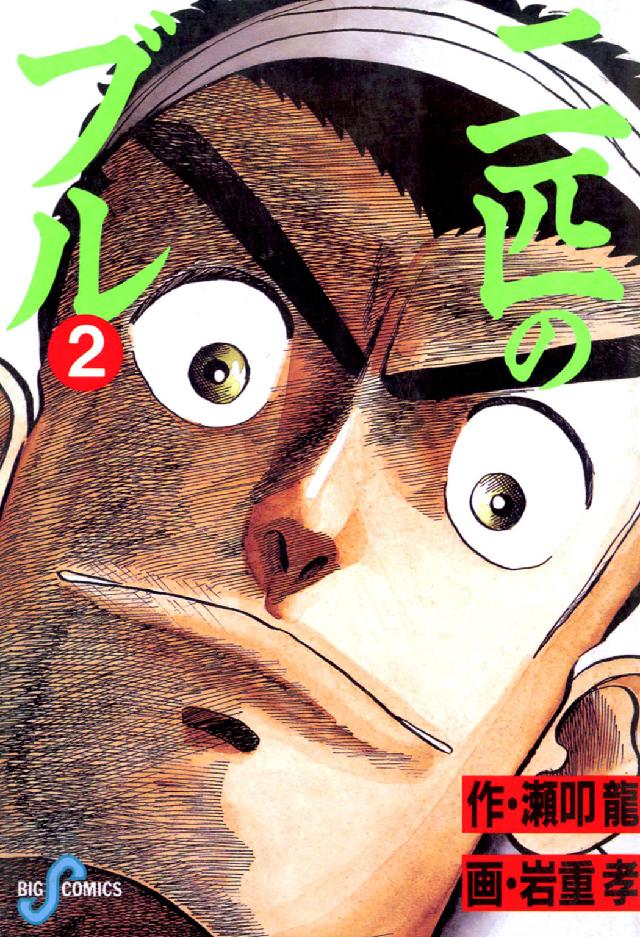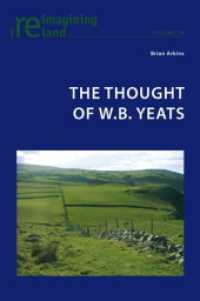- ホーム
- > 和書
- > 人文
- > 哲学・思想
- > 日本の哲学・思想一般(事典・概論)
内容説明
幕末維新期、戊辰戦争を頂点とする一連の戦いにおいて、会津の戦死者はナショナルな祭祀から排除された。彼らと、生き残った会津の人々とが経験した「犬死に」―この非業と不条理に満ちた死の経験は、その後どのように「克服」され、「解決」されていったのか。本書では、戊辰戦争や西南戦争での戦死者を会津の人々がどのように認識し、自らのアイデンティティを組み立てていったのかを明らかにする。
目次
序章 死者と共同体
第1章 会津藩の戊辰戦争―近代会津へのプロローグ
第2章 「阿蘇の佐川官兵衛」をめぐる記憶と忘却
第3章 近代会津アイデンティティの系譜
第4章 「雪冤勤皇」期会津における戦死者の記憶と忘却
第5章 戦後会津における「観光史学」の軌跡
終章 “二つの戦後”をめぐる“死者の政治学”
著者等紹介
田中悟[タナカサトル]
1970年大阪市生まれ。1993年京都大学文学部卒業。社会人を経て、2002年立命館大学法学部中退。2008年神戸大学大学院国際協力研究科博士課程修了。博士(政治学)。現在、神戸大学大学院国際協力研究科助教。この間、成均館大学校東アジア学術院研究員、国際日本文化研究センター共同研究員、大阪女学院短期大学非常勤講師、ソウル大学校国際学研究所客員研究員(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
yooou
5
☆☆☆☆★ 想像以上にスリリング。近代日本をデザインした人々の思惑が浮き彫りとなってくるような構成は考え抜かれたもので読み応えは十分でした。2010/07/29
あまたあるほし
3
会津が敗北の歴史をどう乗り越えようとしたのか、その軌跡を追う。佐川勘兵衛の顕彰の考察では国家への忠誠を尽くしたものを讃えたところから、単に会津武士を讃えるという目的の変化を紹介している。戦前の皇国史観的会津史から戦後は司馬遼太郎が広く紹介した敗者としての会津史に変わる過程は興味深かった。 2010/05/16
yamikin
2
最近の「昭和ノスタルジア」にしてもそうだが、ある過去の事実をどのようにして現代において意味付けるのかというのは、その時代ごとのナショナリズムやパトリオティズムによって決定づけられる。会津の場合、戊辰戦争を会津の人たちが各時代でどのように意味付けていったのかを追うことでこの地の歴史が浮き上がってくる。本書に目を通せば、大河ドラマ的ロマン主義に端を発して商品化された歴史観光資源も相対化される。注意すべきは、そのダイナミズムも含めて歴史なのだから、商品化された観光資源は一概に批判されるべきものではないということ2014/10/22
しろろぞ
1
近代国民国家における「死」と共同体との関連性、それを近代会津を舞台に分析している。佐川官兵衛や白虎隊の記憶の変容が、時代(特に日本という国家)との関係で変わる過程が興味深い。会津観光史観についても驚くことが沢山あった。歴史の評価というのは時代と共に変わるものだけど、死者の有り方も少しずつ変わっていく。ただ、その地域の人に根差したもの、ということは変わらないような気がした。http://memoria1.blog.fc2.com/blog-entry-90.html2013/08/23
あんこ
1
宮崎十三八の辿った足跡がジンジンきた…。観光史学、「歴史散歩」、「限りなく美しく深い」会津…こういう視点は何としても地元を盛り上げたい郷土史家や地元関係者なら少なからず持っていると思う。それが学者と郷土史家の違いなのかな。観光史学や歴史小説と歴史学の軋轢そして未来について、もっと詳しい論理が読みたいな~。著者の言いたいこととは別の方向性で読んでしまったな。でも、野口英世で湧いた会津とか震災後大河ドラマで取り上げられた事によって再び幕末が盛り上がってる会津とか、その辺りについても今後考証があれば嬉しいな。2013/02/17
-

- 電子書籍
- 科学の名著<1> インド天文学・数学集…