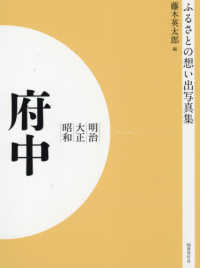出版社内容情報
外部に公表されなかった生活保護者の情報。行政の立場にいる著者だからこそ入手できたデータと経験で被保護世帯の実態を解明する。
内容説明
行政に管理され外部に公表されることのなかった生活保護者たちの情報。行政の立場にいる著者であるからこそ入手できたデータと現場経験をいかして、被保護世帯の実態を明らかにしていく。資料的価値を備えた一冊。
目次
序章 問題意識と研究の目的
第1章 生活保護の現状と日本型ワーキングプア
第2章 要保護層の貧困の実態
第3章 被保護母子世帯の貧困ダイナミクス
第4章 要保護層の就労自立支援プログラム
第5章 ホームレスの就労自立支援
終章 日本型ワーキングプアと岐路に立つ生活保護
著者等紹介
道中隆[ミチナカリュウ]
1949年生まれ。大阪府立大学大学院前期博士課程修了。大阪府庁はじめ各自治体に勤務し、保健福祉の政策運営にかかわる。厚生労働省「生活保護事例検証委員」、桃山学院大学講師など歴任。現在、堺市健康福祉局理事、大阪府立大学非常勤講師、日本パブリックサービス通訳翻訳学会(「PSIT学会」)理事(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ゆう。
21
著者は、ワーキングプアのうち、閾下稼得にある10万円以下層を日本型ワーキングプアと定義しています。そして、公的扶助ソーシャルワーカーの社会的役割の一つに笛木俊一氏にならい、貧困問題に対する「社会診断家」の役割があり、生活保護制度そのものに内在化する機能だと理解できるとしています。この本では、日本型ワーキングプアに対して、生活保護制度などがどのような役割を果たしているのかを実証的に研究し、岐路に立つ生活保護制度にどのような課題があるのかを研究された本です。いろいろと学べました。2015/02/27
ゆうゆう
11
日本型ワーキングプア、最低賃金と実質的最低生活保護費の著しい乖離。働いても働いても得る収入が、世帯の最低生活費を下回り、その収入が賃金の下限を定める最低賃金を基礎に算定した月額賃金にも届かない。就労してもなお生活保護から脱却できない。日本型ワーキングプアやボーダーライン層…層の固定化して、貧困の世代連鎖してる。肌感覚は間違ってなかった。これをなんとかする仕組みを作るのが政治じゃないのかなぁ。2021/05/16
うにもろこし
2
生活保護行政や貧困などの状況についての実証研究集。一つ一つがそんなに長くないのでポンポン読めるから読みやすい。日本型ワーキングプアの定義が若干わかりにくい印象。統計学的にいろいろ検定するというよりはパネルデータを見ていくという感じの章が多いかも。貧困対策の分野でよく言われることの復習という部分が少なくないため新しい理論を知りたいっていう人には向かないかも。2014/02/09
なおた
0
行政に管理され外部に公表されることのなかった生活保護者たちの情報。行政の立場にいる著者であるからこそ入手できたデータと現場経験をいかして、被保護世帯の実態を明らかにしていく。資料的価値を備えた一冊。2021/01/09