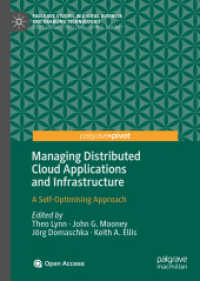内容説明
啓蒙期の科学は解剖学的な差異と精神性を関連させ、男女は身体的のみならず能力や性格においても本質的に異なるというジェンダー観を成立させた。このジェンダー観は、近代社会の形成にあたって規定的な力として作用し、人びとの居場所や役割、行動規範を定めるとともに、政治・経済・社会のさまざまな制度のなかに組み込まれていく。本書では、知の専門化、参政権運動、協会活動、母性福祉、社会保険、戦争という歴史事例をとりあげ、ジェンダーの構築と変容の過程、構造をつくりだす力としてのジェンダーの作用、そしてヨーロッパの女たち、男たちが近代のジェンダー化された社会をどう生きたのかを描きだす。ヨーロッパ諸国における女性史とジェンダー史をめぐる動向も合わせて考察。
目次
第1章 近代フランスの医療と身体 救済の手と簒奪の手が…―モケ・ド・ラ・モットの助産とジェンダー
第2章 女性参政権運動 「マンズ・シェア」―イギリス女性参政権運動への男性のかかわり
第3章 歌うドイツの男たち 一九世紀ドイツにおける男声合唱運動―ドイツ合唱同盟成立(一八六二年)の過程を中心に
第4章 ジェンダーの構造化と裁判 健康な母親と強壮な子孫―アメリカ社会福祉制度形成における裁判所判決とジェンダー
第5章 社会保険とジェンダー 近代化過程における労働者のジェンダー化―ドイツにおける社会保険制度の成立とジェンダー
第6章 女性にとって戦争とは 戦争とジェンダー―スペイン内戦の場合
第7章 イタリアの性差の歴史 性差から歴史を語る―イタリアにおける女性史と“ジェンダー”
著者等紹介
姫岡とし子[ヒメオカトシコ]
1950年京都府生まれ。1980年フランクフルト大学歴史学部マギスター(修士)課程修了。1984年奈良女子大学大学院人間文化研究科博士課程単位取得退学。文学博士。現在、筑波大学大学院人文社会科学研究科歴史・人類学専攻教授
長谷川まゆ帆[ハセガワマユホ]
1957年岐阜県生まれ。1985年名古屋大学大学院文学研究科博士後期課程単位取得退学。現在、東京大学大学院総合文化研究科准教授
河村貞枝[カワムラサダエ]
1943年兵庫県生まれ。1973年京都大学大学院文学研究科博士課程単位取得退学。文学博士。現在、京都府立大学名誉教授
松本彰[マツモトアキラ]
1948年東京都生まれ。1983年東京都立大学大学院人文科学研究科博士課程単位取得退学。現在、新潟大学人文学部教授(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
-

- 電子書籍
- 求婚魔王と留年の勇者【タテヨミ】 第1…
-
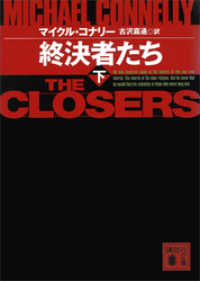
- 電子書籍
- 終決者たち(下) 講談社文庫