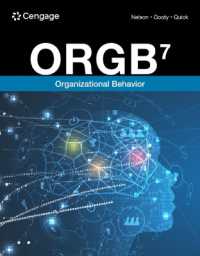内容説明
上杉謙信(一五三〇~七八)戦国期越後の盟主。越後を本拠に関東・越中・能登を支配した上杉謙信については、江戸時代の兵学者らによって史実と異なることが多く語り継がれてきた。本書は、謙信が生きた時代の史料のみを使って、本物の謙信像を提示する。
目次
序章 御館の乱
第1章 戦国期越後とその景観
第2章 守護上杉房定
第3章 父、守護代長尾為景
第4章 長尾景虎の登場
第5章 上杉輝虎への道
第6章 越後の城と領主
終章 天正五年の能登攻め
著者等紹介
矢田俊文[ヤタトシフミ]
1954年鳥取県倉吉市生まれ。大阪市立大学文学部卒業。博士(文学)。新潟大学人文学部助教授を経て、新潟大学人文学部教授(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
こきよ
68
二度の上洛や小田原城攻囲、鶴岡八幡宮での関東管領就任、川中島や北関東、北陸での転戦。一次資料からの考察で読み取れる上杉謙信像は極めて封建的である。毛利や織田等とは違い、あの地域でほぼ寝業無しで領国経営をしていたという事実は、やはり名将なのだろうと思わざるをえない。2016/02/13
Toska
17
謙信の伝記としては異色の内容。彼個人にしか関わりのない出来事を大胆にカットする傾向があり、例えば出奔事件などはわずか2行(!)で終わってしまう。その代わり、戦国越後史の解像度が高まることは間違いない。もともと謙信を生んだ長尾氏は守護代の家柄にすぎず、同格の国人領主がひしめく中、彼らとの連合政権とならざるを得なかった。例えば前線で孤立した北条高広が「裏切った」のも、彼が譜代の家臣ではなく一個の独立した領主であるからには当然の選択だったと著者は言う。当時の村落のあり方や謙信の都市政策についてのコメントも有益。2026/02/12
中島直人
12
上杉謙信の政権は独立権力を持つ領主の連合体だった。本来同格の領主に優越するためには、より上位の権威である天皇や将軍に頼らざるを得ず、無意味に見える関東出兵はその対価だった(上杉謙信が義侠心のため行ったものではない)。もし権力構造が本質的に異なる織田政権と本格的に戦った場合、ここの合戦での勝利は得られた可能性があるが、最終的には敗れざるを得なかった。2016/11/01
アンパッサン
3
人間謙信を知りたくて買ったのだが。謙信軍は謙信とおなじくらいの領主連合体だった。となりの武田もある意味そうだが、越後はそれ以上。だから北条大熊とかが反旗を翻す。おなじじゃないというために必要だった毛氈鞍覆とか関東管領の地位。盤石ではなかったんだなあ、上杉家。2019/04/10
秋津
3
上杉謙信について史料を用いて論じた一冊。謙信の権力は、自立した「大領主を抱え込んだ権力」であり、領国支配のためには彼らの協力を求めることもあったこと、「長尾」と「上杉」の家格とその権力について、また、後世の軍学書や合戦図屏風に見られる川中島での武田信玄との一騎打ちは軍学者による創作であることなどを前史も含めて考察しています。余談ながら謙信の男色について半分くらい割いている項があるのは何なのかと思いつつ、筆者御本人が「(謙信は)男好きのただのおっさん」とおっしゃっていたなと懐かしく思うなど。2014/01/01
-
- 洋書
- ORGB (7TH)
-
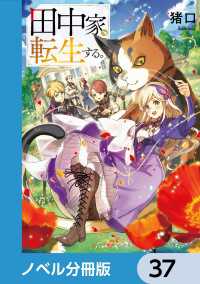
- 電子書籍
- 田中家、転生する。【ノベル分冊版】 3…


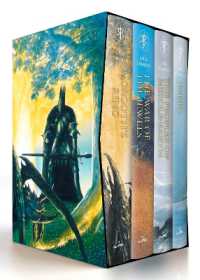
![A Fiery Pillar, of Heavenly Truth, Shewing, the Way to a Blessed Life. Composed by Way of Catechism, ... by Alexander Grosse, ... the Elevnth [sic] Edition](../images/goods/ar/work/imgdatag/13854/1385490950.JPG)