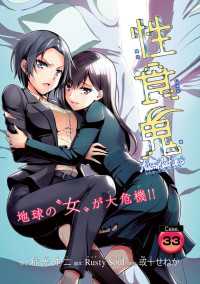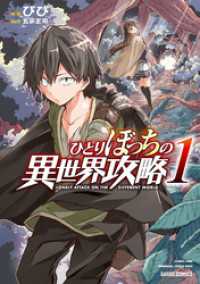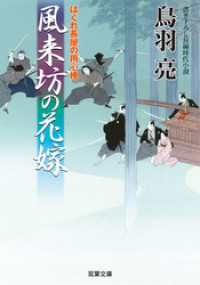出版社内容情報
人間の社会的行為の三類型を剔出した古典。
内容説明
離脱・発言・忠誠という人間の社会的行為の三類型の剔出を通じて、小は町の零細企業から大は巨大国家にいたる組織社会における人間の行動原理を明らかにする現代社会科学の古典の改訳新版。本書をめぐって国際会議が開催されたことにもその重要性が表れているように、本書は、経済学と政治学の生産的対話の試みであり、新古典派の市場主義一辺倒によって切り裂かれつつあるかにみえる公共性の再生・復権の手がかりを与える。
目次
第1章 序論と学説的背景
第2章 離脱(Exit)
第3章 発言(Voice)
第4章 離脱と発言の組み合わせ―固有の難しさ
第5章 競争が助長する独占
第6章 空間的複占と二大政党制の力学
第7章 忠誠(Loyalty)の理論
第8章 アメリカ的なイデオロギー・慣行のなかの離脱と発言
第9章 離脱と発言の最適な組み合わせは可能か
著者等紹介
矢野修一[ヤノシュウイチ]
1960年生まれ。1986年京都大学経済学部卒業。1991年京都大学大学院経済学研究科博士後期課程単位取得退学。高崎経済大学経済学部教授
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
なーちゃま
3
2周目。「経済は競争制度の下、うまくいく」と経済学者はじめ人々は信じているが、「競争のメカニズム」、つまり具体的にどういった経路で商品の淘汰、選別、質の向上に向けたフィードバック、が行われているのか丁寧に分析している。この本のタイトルが『離脱と発言』ではなく、『離脱、発言、忠誠』なのはなぜか。離脱も発言も合理的経路だが、忠誠のみ非合理的な概念。この3つの概念をうまく活用し、グリーン投資の論文が書ければいいな。2021/10/10
いとう・しんご
3
最近、引きがいい感じで、この本もビンゴ!って感じの1冊。「離脱」という経済学の視点、「発言」という政治学の視点に「忠誠」という新たな学際的視点を加味して、ヴェトナム戦の泥沼に突き進む大統領府の衰退ぶりを分析しているが、それは安倍政権、ひいては自民党の衰退にも共通しており、数ページごとにスマホのOCRを開いてメモ帳に転記するほど。巻末のハーシュマンのライフストーリーも、大変、興味深く、その部分から読むのも一興。2020/08/16
こたつ
3
hamachanブログで何度か登場していていつか読みたいと思っていたので読んでみました。経済学では専ら「離脱」しか重視されてきませんでしたが、政治学的な「発言」を考えることによって生産的な議論を展開しています。私の関心から言えば、やはり(ブラック)企業における労働者の反応としての「離脱」と「発言」(と「忠誠」)をどのように考えるべきか、そこに労働組合がどのように関わるべきか、という点ですが、「離脱」の回路を確保しつつ、あくまで「発言」を担保することに労働組合は重きを置くべきかな、と思いました。2016/05/22
いせやん
3
ある商品・組織に対する不満を伝える手段として、市場の競争において通例想定されている「競合する他のものに乗り換える」=離脱の他に、不満を伝えて改善を求める「発言」があることを指摘し、両者の機能を説明する。そして、離脱できるのに発言を選ぶ「忠誠」についても詳しく考察されている。競争にさらされている=離脱が存在する時に返って改善が遅れるという国有鉄道の例や、離脱先がないゆえに強力に発言する人々が大きな力を持つ、共和党保守化の説明が、特に面白かった。2015/08/23
じょに
3
重要だと思うけど、単純なスタートラインから変数を増やして行くので、いかんせん記述が単調でややこく、サラっと通り過ぎるだけに留めた。要するに、組織へのコミットメントの話。組織が気に入らない時、そこから離脱をするのか、改善を要求する声を上げるのか、忠誠する行動をとるのか、それぞれどのような条件で成り立つのか。細かく考えれば、組素朴な疑問はいっぱい出てきそう。現実はややこしいが、この区別は出来る。扱う組織、扱う国によって条件は色々変わってくるだろうけど。そういえば忠誠と反逆は両立するんだよね。2009/04/30