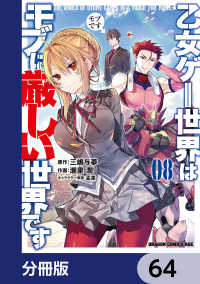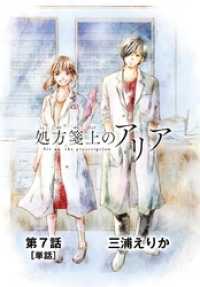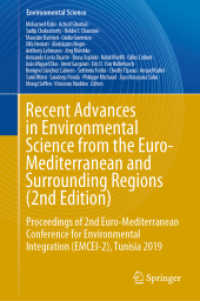出版社内容情報
【内容】
アメリカ外交の基盤は、19世紀に形成された。方向性が見えない現代アメリカ外交の行く末を見定めるためにも、19世紀のアメリカ外交の検証が今日、切に求められている。
本書は、「アメリカ外交の伝統」とされるモンロー・ドクトリン(モンロー主義)を中心に、19世紀前半のアメリカ外交、つまり、アメリカ外交の基盤を考察したものである。アメリカ学会「清水博賞」受賞
【目次】
はじめに――イデオロギーと現実政治
凡例/口絵/地図
序 章 研究の枠組み
1 概要・構成および用いられる史料
2 先行業績の批判的検討
3 研究の視角
第1章 モンロー・ドクトリン概観
1 今日のモンロー・ドクトリンとその起源
2 ウィーン体制
3 「モンロー・ドクトリン」の形成と展開
第2章 1812年戦争の外交――モンロー宣言前史
1 1812年戦争
2 開戦と早期講和の挫折
3 米仏交渉とジョール・バーロウ
4 ロシアによる調停の申し出
5 ナポレオン戦争の終結とゲント講和
6 自由主義の国際関係観
第3章 モンロー宣言の背景――革命第二世代の構想
1 イデオロギーの変容――「共和主義」から自由主義
2 決断の時――英米共同宣言の提案
3 「共和主義」と米英提携
4 閣議決定と政策形成者の国際情勢認識
5 「アメリカ体制」論の対外構想
6 自由主義の台頭
第4章 モンロー宣言をめぐる政策決定
1 非植民地化・非干渉と米英露関係
2 モンロー宣言への道
3 米英の確執
4 「ロシア要因」
5 モンロー宣言の現実政治的側面
第5章 対中南米外交におけるモンロー宣言の不履行
1 モンロー宣言の国内向けの側面
2クレイ決議の棚上げとコロンビア、ブラジルとの同盟拒否
3 パナマ会議への対応
4 パナマ会議をめぐる議会の論戦とラ・プラタ連邦との提携拒否
5 “コミットメントなき誓約”から「創り出された伝統」へ
第6章 モンロー・ドクトリンとは何か
1 モンロー・ドクトリンの変遷
2 モンロー・ドクトリンの復活
3 ローズヴェルト系論から汎米主義へ
4 冷戦期のモンロー・ドクトリン
5 冷戦終焉とモンロー・ドクトリンの変容
終 章 アメリカ外交の基盤としてのモンロー宣言
あとがき
「第7次年次教書」原文
主要参考文献/事項索引/人名索引
内容説明
アメリカ外交の基盤は、19世紀に形成された。方向性が見えない現代アメリカ外交の行く末を見定めるためにも、19世紀のアメリカ外交の検証が今日、切に求められている。本書は、「アメリカ外交の伝統」とされるモンロー・ドクトリン(モンロー主義)を中心に、19世紀前半のアメリカ外交、つまり、アメリカ外交の基盤を考察したものである。アメリカ外交は建国以来、アメリカ特有のイデオロギーによって突き動かされてきたのか。あるいは、時として見られる現実政治(レアルポリティーク)こそ、アメリカ外交の真の姿なのか。同時代のアメリカ外交の観察を媒介とした、原史料にもとづくアメリカ外交の基盤の再構成、すなわち、「現在と過去との対話」(E・H・カー)から見えてくるアメリカ外交像を探る。
目次
序章 研究の枠組み
第1章 モンロー・ドクトリン概観
第2章 一八一二年戦争の外交ーモンロー宣言前史
第3章 モンロー宣言の背景―革命第二世代の構想
第4章 モンロー宣言をめぐる政策決定
第5章 対中南米外交におけるモンロー宣言の不履行
第6章 モンロー・ドクトリンとは何か
終章 アメリカ外交の基盤としてのモンロー宣言
著者等紹介
中嶋啓雄[ナカジマヒロオ]
1967年東京都生まれ。1995年一橋大学大学院法学研究科博士後期課程単位修得。ハーヴァード大学大学院歴史学部留学(1993~94年)。現在、大阪外国語大学外国語学部助教授。専攻はアメリカ外交史・国際関係史
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。