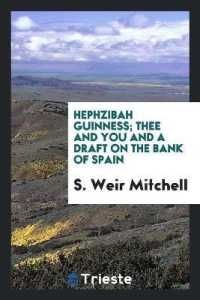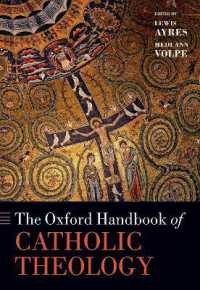出版社内容情報
【内容】
近世から近代への連続性に注目しつつ,誕生期の「円」の実態構造を解明,複合存在としての「円」の相互関係の検証を通して貨幣史研究を歴史統計分析へと拡大。日経■経済図書文化賞受賞。
【目次】
はしがき
序章 明治維新期の財政と通貨
1 幕末期の幕藩財政と通貨
2 維新政権と太政官金札
3「廃藩置県」後の財政と通貨
4 紙幣インフレと松方紙幣整理
第1部 「円」の成立
第1章 万延二分金考――幕末・維新期の基準通貨――
1 明治初年の通貨事情
2 万延元年の幣制改革
3 新貨条例と両円切替え
第2章 内ニ紙幣アリ外ニ墨銀アリ――大隈財政期の通貨構造――
1 正貨流出と金円・銀円の退場
2 内ニ紙幣・外ニ墨銀
3 大隈派官僚の通貨論
4 銀紙格差と紙幣主義の敗退
第3章 金銀本位制論――「貨幣法」成立前史――
1 明治16年「銀本位制貨幣条例案」
2 明治24年「銀本位制貨幣法案」
3 明治26年「貨幣制度ニ付諮問案」
4 明治30年1月「金本位制施行方法」
5 明治30年2月「貨幣条例中改正法律案」以後
第4章 円銀始末――英領海峡植民地における円銀流通とその終焉――
1 円銀とその海外流出
2 英領海峡植民地における円銀
3 日清戦争と円銀
4 金本位制採用と円銀の還流
5 その後の円銀
第2部 貨幣市場と貨幣相場
第5章 横浜洋銀相場の生成と消滅
1 開港と洋銀相場の生成
2 為替相場としての洋銀相場の展開
3 洋銀相場の変質と消滅
第6章 金円・銀円・紙円の関係について
1 太政官金札の発行と金札相場
2 「新貨条例」体制とその崩壊
3 紙幣インフレと銀紙格差
4 銀価下落と金銀混計問題
第3部 経済計算の貨幣的問題
第7章 両・円切替期における通貨と記帳
――大阪・山口家勘定帳および備後府中・延藤家勘定帳の事例に即して――
1 大阪における銀目廃止と両円切換え
2 備後福山藩の藩札整理と円の普及
第8章 明治前期財政統計における金・銀・紙混計問題
――明治14年度正貨予算書の分析を中心に――
1 会計法規上における「円」計算の原則
2 院省庁支出「外国ニ関スル費用」
3 外債元利支払いとその邦貨計算
4 明治14年度「正貨収支概計表」
結章 幕末・明治前期の通貨構造
1 「両」金本位制の成立
2 開国と「両」の国際的平準化過程
3 「両」から「円」へ
4 金円・銀円・紙円
5 両・円の対外価値――洋銀相場と外為相場
あとがき
参考文献一覧
関係法令年表
索引
内容説明
「円」の誕生の物語は幾多の先行業績をもつ。日本貨幣史の近世から近代への連続性に注目しつつ、誕生期の「円」の実態構造を解明し、複合存在としての「円」の相互関係の検証を通して、貨幣史研究を歴史統計分析へと拡大する。
目次
序章 明治維新期の財政と通貨
第1部 「円」の成立(万延二分金考―幕末・維新期の基準通貨;内ニ紙幣アリ外ニ墨銀アリ―大隈財政期の通貨構造;金銀本位制論―「貨幣法」成立前史;円銀始末―英領海峡植民地における円銀流通とその終焉)
第2部 貨幣市場と貨幣相場(横浜洋銀相場の生成と消滅;金円・銀円・紙円の関係について)
第3部 経済計算の貨幣的問題(両・円切替期における通貨と記帳―大阪・山口家勘定帳および備後府中・延藤家勘定帳の事例に即して;明治前期財政統計における金・銀・紙混計問題―明治14年度正貨予算書の分析を中心に;幕末・明治前期の通貨構造)
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
人生ゴルディアス
フルボッコス代官
-

- 和書
- 敗北からの創作