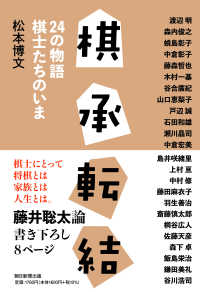出版社内容情報
アジア・太平洋戦争末期、米軍の沖縄本島上陸を前に、島々は戦場になった。先島(八重山・宮古諸島)攻撃の中心を担ったのは、戦後世界における権威・権益を見すえた英軍だった。主な任務は日本軍航空施設の無力化である。石垣島に漂着した反乱清国人苦力(クーリー)たちを米英軍が砲撃し捕縛したロバート・バウン号事件から93年後だった。
明治維新後、八重山は琉球併合をへて沖縄県の一部となった。かつて琉球王府の人頭税で土地と島空間に縛りつけられていた民衆は、皇民化教育や徴兵制をとおして近代社会を知った。標準語励行。郷土部隊。経済活性化のための軍隊誘致決議。御嶽(うたき)信仰の神道化。熱狂はつくられる。
やがて陸海軍総兵数一万三千人が配備され、島民の根こそぎ動員が始まる。食料供出。台湾疎開。マラリア猖獗地帯への避難。爆撃。特攻。学徒の鉄血勤皇隊……。ヤマト世は戦世だった。歌と踊りで神をもてなす島々の民は、いかにして軍事化の道を歩んだのか。
本書は英米軍の活動報告や日本兵の日記、島の住民の証言を読み、歴史を綴り、上空で爆弾を投下する側と下で爆撃される側の視点を交差させる。各地に拡がる八重山出身者の戦死記録や米軍の偵察分析を付す。
台湾や尖閣の有事を想定した沖縄本島・先島の基地化、島民の島外避難計画が進む今こそ、未来へと託す「八重山の戦争」。
【目次】
地図
八重山諸島/石垣島/1944年11月に米軍が作成した「主要な日本軍の施設」/同「軍事上想定可能な施設」
はじめに
第I部 大和世は戦世
第一章 八重山の明治維新
ロバート・バウン号事件
異国船の来航
江戸幕府崩壊と琉球王国
琉球併合
宮古島遭難者殺害事件
熊本鎮台設置
八重山の役人
琉球処分と廃藩置県
清国への八重山・宮古割譲論
士族たちの抵抗
石炭と軍事化――フランスの占領計画
山縣有朋・伊藤博文・森有礼の来島
学校開設と皇民化教育
御真影・教育勅語下賜
陸軍教導団
徴兵制への布石
日清戦争勝利祝賀会
人頭税廃止後、資本主義と重税の波
台湾領有と海底ケーブル設置
第二章 軍隊とシマヌピトゥダー(島の人びと)
徴兵令施行と郷土部隊
徴兵忌避
日露戦争勝利の熱狂と初の戦死者
在郷軍人会の忠魂碑建立運動
昭和の始まり
八重山教員赤化事件
沖縄連隊区司令官の赴任
八重山義勇軍の編成
軍隊誘致
宮古島から漕ぎ出た久松五勇士
生活改善運動
標準語励行
「石垣校標準語行進曲」
校歌と臣民
無らい県運動
精神障害者の監置と放置
戦争を推進する詩人
兵隊が歌う安里屋ユンタ
言論統制と新聞・ラジオ
金属回収された桃林寺の梵鐘
ユタ狩り、御嶽改革
海軍神社と八重山神社
軍事演習
沖縄人はスパイとみなす
牛肉の行方
第三章 開戦
県議会と職員の戦勝祈願
八重山郡翼賛壮年団
婦人たちの総動員
常会・隣組
御嶽信仰の神道化
従軍慰安所の設置
軍神大舛大尉
軍学校より一高を選んで国賊扱い
教育界と少年兵
軍紀の乱れ――強姦・逃亡・窃盗団
船浮要塞の建設
八重山旅団
十・十空襲と台湾沖航空戦
八重山の十・十空襲
作戦演習
護郷隊
残置諜者・特殊隊
朝鮮人の水上勤務部隊
海軍
飛行場建設
海軍三二二設営隊
日本最南端の特攻基地
特攻
八重山の鉄血勤皇隊
八重山出身学徒の沖縄戦
ひめゆり部隊
第四章 疎開と避難
南洋群島からの帰還
台湾疎開
学童疎開
台湾疎開船の尖閣諸島遭難
軍の住民対策
御真影の奉護
住民避難計画
四箇字(石垣・登野城・大川・新川)住民の避難
戦争マラリア
* 八重山各村の戦時の状況
第五章 敗戦
8月27日の不敬罪裁判
安東丸事件
部落を一周させられた米軍捕虜
石垣島事件
事件発覚
軍政の空白
注
第II部 1945年 八
内容説明
沖縄戦の捨て石にされ、戦場となった歌の島、神の島。島の民はいかにして軍事化の道を歩んだのか。英米軍・日本軍・住民の視点が交差する「八重山の戦争」。
目次
第1部 大和世は戦世(八重山の明治維新;軍隊とシマヌピトゥダー(島の人びと)
開戦
疎開と避難
敗戦)
第2部 1945年 八重山の戦争日誌
第3部 八重山出身者の戦死 1944‐1945年
資料 米軍の偵察分析(抜粋)
著者等紹介
大田静男[オオタシズオ]
1948年沖縄県石垣市生まれ。地元紙・業界紙記者をへて石垣市立図書館開館準備室で郷土資料を担当。石垣市立八重山博物館勤務をへて石垣市教育委員会文化課長を2008年退職。八重山諸島の戦史・戦後史・芸能史・ハンセン病史を調べ、『八重山の芸能』(ひるぎ社)で沖縄タイムス出版文化賞、『八重山の戦争』(南山舎)で同賞と日本地名研究所風土研究賞を受賞。石垣市文化財審議委員長、石垣市立八重山博物館協議会会長、石垣市史編集委員、1992年の創刊以来、月刊誌『やいま』(南山舎)で「壺中天地」を連載中(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
-
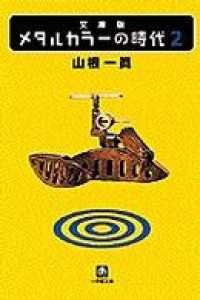
- 電子書籍
- メタルカラーの時代2 小学館文庫