出版社内容情報
成熟期にあるこれからの日本では、博物館や美術館はもとより、図書館、劇場・ホール、公民館、福祉施設、教育施設、アートプロジェクトなどの文化的な営みや文化資源の集積が、地域づくりの重要な役割を果たすのではないだろうか。文化活動が地域に新たな価値をもたらし、住民の自治を育み、地域づくりの基盤をなすことが期待される。
その流れにあって、近年、文化施設の総体を「文化的コモンズ」と捉え、議論をする機運が生まれている。この概念が分野の境界を越えて人びとを結びつけ、地域の活動に新たな価値をもたらしている。
本書は、日本の文化施設の成り立ちをふりかえり、役割や意義を論述するとともに、過去の例に学び、成功例を示し、新たなパースペクティヴを得ることをめざしている。
文化施設を拠点に形成される「文化的コモンズ」の姿を本格的に論じる、初の試論である。
内容説明
成熟期にあるこれからの日本では、博物館や美術館はもとより、図書館、劇場・ホール、公民館、福祉施設、教育施設、アートプロジェクトなどの文化的な営みや文化資源の集積が、地域づくりの重要な役割を果たすのではないだろうか。文化活動が地域に新たな価値をもたらし、住民の自治を育み、地域づくりの基盤をなすことが期待される。その流れにあって、近年、文化施設の総体を「文化的コモンズ」と捉え、議論をする機運が生まれている。この概念が分野の境界を越えて人びとを結びつけ、地域の活動に新たな価値をもたらしている。本書は、日本の文化施設の成り立ちをふりかえり、役割や意義を論述するとともに、過去の例に学び、成功例を示し、新たなパースペクティヴを得ることをめざしている。文化施設を拠点に形成される「文化的コモンズ」の姿を本格的に論じる、初の試論である。
目次
第1部 その連なり(博物館;図書館;公民館;劇場・ホール;福祉施設)
第2部 その営み(文化施設4・0;文化的コモンズの意義;文化施設のガバナンス;当事者の役割;文化施設のマネジメント;地域の文化施策;文化芸術の「怪しさ」を抱いて)
著者等紹介
佐々木秀彦[ササキヒデヒコ]
1968年東京都台東区生まれ。アーツカウンシル東京企画部企画課長。専門は文化施設論、文化資源論。東京外国語大学卒業、東京学芸大学大学院修士課程修了。江戸東京博物館、江戸東京たてもの園、東京都美術館の学芸員を経て現職。所属する東京都歴史文化財団の経営企画、新規事業立ち上げに従事。国・自治体の文化施策や文化施設にソーシャル・キュレーションの視点で関わる(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
トム
takao
sun
バジルの葉っぱ
かふん
-

- 電子書籍
- 極道上司に愛されたら~冷徹カレとの甘す…
-
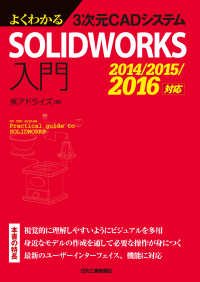
- 電子書籍
- よくわかる3次元CAD SOLIDWO…


![気ままねこさまカレンダー 卓上書き込み式[B6タテ]【S4】 〈2026〉 永岡書店のカレンダー](../images/goods/ar2/web/imgdata2/45226/452264583X.jpg)




