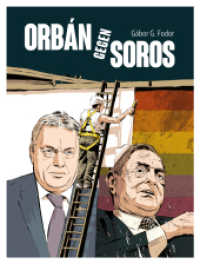出版社内容情報
自分を理解してくれる人がいない、友人や伴侶が得られない、最愛の存在を喪って心にぽっかりと穴があいたような気持ちがする、老後の独り居が不安だ、「ホーム」と呼べる居場所がない――このような否定的な欠乏感を伴う感情体験を表現する語として「孤独」が用いられるようになったのは、近代以降のことである。それまで「独りでいること」は、必ずしもネガティブな意味を持たなかった。孤独とは、個人主義が台頭し、包摂性が低く共同性の薄れた社会が形成される、その亀裂のなかで顕在化した感情群なのである。
ゆえに孤独は、人間である以上受け入れなければならない本質的条件などではない。それは歴史的に形成されてきた概念であり、ジェンダーやエスニシティ、年齢、社会経済的地位、環境、宗教、科学などによっても異なる経験である。いっぽう、現代において孤独がさまざまな問題を引き起こしていることも事実であり、国や社会として解決しようとする動きが出てきている。その際まず必要となるのは、孤独を腑分けし、どのような孤独が望ましくなく、介入を必要とするのかを見極める手続きである。
2018年に世界で初めて孤独問題担当の大臣職を設置したイギリスの状況をもとに、孤独の来歴を多角的に照らし出す。漠然とした不安にも、孤独をめぐるさまざまな言説にもふりまわされずに、孤独に向き合うための手がかりとなる1冊。
内容説明
“21世紀の疫病”と呼ばれ、社会的解決が叫ばれる「孤独」。対処の第一歩となるのは、それが人間の本質的条件であるという見方を疑うことである。ネガティブな欠乏感としての「孤独」が近代において誕生し、複雑な感情群となるその歴史をひもとく。
目次
序論 「近代の疫病」としての孤独
第1章 「ワンリネス」から「ロンリネス」へ―近代的感情の誕生
第2章 「血液の病気」?―シルヴィア・プラスの慢性的な孤独
第3章 孤独と欠乏―『嵐が丘』と『トワイライト』にみるロマンチック・ラブ
第4章 寡婦/寡夫の生活と喪失―トマス・ターナーからウィンザーの寡婦まで
第5章 インスタ憂うつ?―ソーシャルメディアとオンラインコミュニティーの形成
第6章 「カチカチと音を立てる時限爆弾」?―老後の孤独を見つめ直す
第7章 宿なし、根なし―「ホーム」と呼べる場所がないということ
第8章 飢えを満たす―物質性と孤独な身体
第9章 孤独な雲と空っぽの器―孤独が贈り物であるとき
結論 新自由主義の時代における孤独の再定義
著者等紹介
アルバーティ,フェイ・バウンド[アルバーティ,フェイバウンド] [Alberti,Fay Bound]
1971年生まれ。文化史家。ロンドン大学キングス・カレッジ近現代史教授。専門はジェンダー、感情史、医学史。歴史学博士(ヨーク大学)。イギリス初の感情史専門の研究所であるロンドン大学クイーン・メアリー感情史センターの創立メンバーの一人。マンチェスター大学、ランカスター大学、ヨーク大学等でも教鞭をとる
神崎朗子[カンザキアキコ]
翻訳家。上智大学文学部英文学科卒(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
trazom
藤月はな(灯れ松明の火)
オフィス助け舟
どら猫さとっち
S