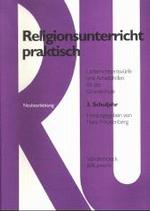出版社内容情報
ケイトリン・ローゼンタール[ケイトリンローゼンタール]
著・文・その他
川添節子[カワゾエセツコ]
翻訳
目次
1 生と死のヒエラルキー―英領西インド諸島の会計と組織構造
2 労働の記録―ペーパーテクノロジーの比較から見えるもの
3 奴隷制の科学的管理―アンテベラム期の南部における生産性分析
4 人的資本―アンテベラム期の南部における命の値踏み
5 自由を管理する―南部支配の再現
結論 経営と奴隷制の歴史
著者等紹介
ローゼンタール,ケイトリン[ローゼンタール,ケイトリン] [Rosenthal,Caitlin]
カリフォルニア大学バークレー校歴史学部准教授。マッキンゼー・アンド・カンパニーで勤務後、ハーバード大学でアメリカ文明史の博士号を取得。その後、ハーバード・ビジネス・スクールのフェローを経て現職。専門は、ビジネスにおけるマネジメント慣行、情報技術、労務管理の史的展開。定量的手法と定性的手法を組み合わせて、ビジネス史、経済史、労働史を結びつけた視点から研究を行っている。2013年にはKroossビジネス史優秀論文賞を受賞。2016年にはUCバークレーでの「アメリカ資本主義史」講座が、同大学のアメリカン・カルチャーズ・センターのイノベーション・イン・ティーチング賞を受賞した(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
owlsoul
8
資本主義における数値化の暴力。それが無制限にあらわれるのが奴隷制のプランテーションにおける会計帳簿のなかだ。帳簿において奴隷は資産とされ、年齢や性別、能力や性格によって値付けされ、歳をとるごとに減価償却される。一人一人の生産性が記録・計算され、それを下回ると懲罰がくわえられる。奴隷制の高度な会計技術は、数値化の暴力に制限がかからない環境でおこなわれた実験の成果といえるが、この技術は現代社会にまでつながっている。暴力による物理的な死と、経済的落伍による社会的な死。どちらに駆動されるにしろ、本質は同じに思える2024/10/20
ととろ
3
人類が奴隷をどう会計処理していたかが前々から気になっていて、本書を手に取り植民地主義時代の奴隷の帳簿に辿り着いた。人類は薄暗い期待を裏切らず、奴隷を資産計上して貸借対照表に表示していたし、生殖能力に応じて資産価値を再評価したり加齢に伴って減価償却していた。理解は出来る。自分が奴隷制に対して社会通念上の懸念が無い状況下で農園の帳簿係をやっていたら、同じように奴隷を管理するだろうから。経理の自分が従業員に等級別の単価を設定していることと、農園の帳簿係が奴隷に等級別の単価を設定していることの距離はそう遠くない。2022/11/11
つまみ食い
2
ひたすら気が滅入る一冊…2025/03/02
tkokon
2
【暴力と体系】○何かで見てタイトルに興味を持ち。○奴隷の道徳的な面を一旦置いておくと、そこには高度なマネジメント体系が発達し、経営資源(としての奴隷)の状態管理・生産性管理・様々な施策の有効性調査等、今のマネジメント理論にも通じる取り組みがこの頃既になされていた。もちろん、奴隷制が廃止されると維持できなくなった体系も多く「力による支配」が成立していることが前提にあるかもしれない。数字による抽象化は、「距離を超える」「生身を扱っている感」も失わせる。膨大な生産性向上の陰に人道的な暗闇があっただろう。2023/06/18
takao
2
近代的会計システム2023/05/18
-

- 洋書電子書籍
- Mathematical Modell…