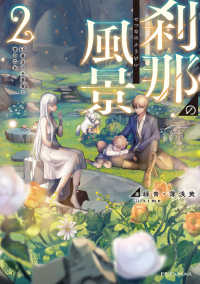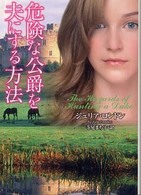出版社内容情報
ダヴィンチをあげるまでもなく、科学と美術の親密性は高い。本書は古代から東西の宗教画・現代美術まで、科学画像の歴史をたどり、ニューロ・サイエンス(神経科学)を基盤とする「実験美術史」の構築に向かう軌跡を描く。具象画を描く盲目の画家の脳の働き。レネサンス期の人体解剖図を現代医学から見てわかること。視線を誘導するよう仕組んでいたカラヴァッジョの絵…。人間の知覚と美の関わりを探る。カラー豪華版。
内容説明
ミケランジェロ、光琳…。作品を見るときに作動する人の神経メカニズムには普遍性がある。視覚・記憶・情感の生物学的しくみを追究する科学との協働が明かす、造形の内側、美の秘密。
目次
第1章 美術あるいは芸術家と科学の親密性(どのような親密性があるのか;科学画像の種類―歴史的変遷と根源的な課題 ほか)
第2章 美術史には科学画像リテラシーが必要か?(二〇世紀における写真と美術の関係;光学機器による科学的調査と美術作品の研究)
第3章 ニューロサイエンスの観点から美術作品を見る(一九九〇年代からクローズアップされた美術と脳の関係;オーリャックの聖ジェロー像の眼のかがやき ほか)
第4章 美術史はニューロサイエンスと協働できるか?(ニューロサイエンス(神経科学)からの美術(美術史)へのアプローチ
美術史家デイヴィッド・フリードバーグの神経科学者との協働)
終章 実験美術史の試み(科学的調査や分析化学を取り込んだ実験美術史の可能性;ニューロサイエンスとともに歩む実験美術史の試み)
著者等紹介
小佐野重利[オサノシゲトシ]
1951年生、東京大学大学院人文科学研究科博士課程中退、同大大学院人文社会系研究科教授。研究科長・文学部長を経て退職、現在、東京大学名誉教授、同大特任教授。マルコ・ポーロ賞(1994)受賞、イタリア連帯の星騎士・騎士勲位章(2003)およびイタリア星騎士・コメンダトーレ勲位章(2009)を受章。アンブロジアーナ・アカデミー(ミラノ)会員(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
trazom
アキ
くるぶしふくらはぎ
izw
Shori