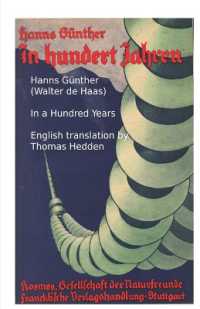出版社内容情報
学校から時代が見える。学校を見てゆくと、歴史の流れがよくわかる。
学校は時代の要請により生まれ、時代とともに変化してきた。日本で学校はどのように始まり、発展して現代に至るのか。〈『礼記』に「家に塾有り、党に庠有り、術に序有り、国に学有り」〉(はじめに)。日本で学校と教育の広がりは、古代、令制にもとづく大学寮から始まる(第1章)。
中世、足利学校には学徒が雲集し、足利は〈日本で初めての学園町であった〉(第2章)。近世には藩校や私塾・家塾や寺子屋(手習所)の世界が豊かに展開する。岡山藩主池田光政が地方の指導者の育成のため庶民の子弟にも他藩の子弟にも門戸を開いた閑谷学校。入塾にあたり三奪すなわち身分・学識・年齢の差なく平等に学び、運営の多くも塾生が担った咸宜園。また寺子屋には女子も通い、寺子屋を終えた後の女学校の設立も構想された。水戸弘道館は、修養の場としての偕楽園をも一対の施設とし、総合大学的教育研究を行なった(第3-7章)。やがて改革の時代を経て、近代の文明の時代、経済の時代、経済によって文明と戦争が結ばれた時代、そして敗戦後、環境の時代から今日へ(第8章)。学校はこれから社会の時代に向かうのか。類のない通史。
内容説明
学校から見てゆくと、歴史の流れがよくわかる。古代の大学寮以来、足利学校、藩校や塾や寺子屋の世界、文明と経済、環境の時代から今日へ。類のない通史。
目次
第1章 学校と教育の広がり
第2章 足利学校
第3章 学校の制度
第4章 教育の世界
第5章 藩校と寺子屋の世界
第6章 改革の時代
第7章 西南雄藩の学校改革
第8章 文明と環境の学校
著者等紹介
五味文彦[ゴミフミヒコ]
東京大学名誉教授。放送大学名誉教授。公益財団法人横浜市ふるさと歴史財団理事長。1946年、山梨県に生まれる。東京大学文学部国史学科卒業。同大学大学院人文科学研究科修士課程修了。文学博士。専門は日本中世史。著書に『中世のことばと絵』(中公新書、1990、サントリー学芸賞受賞)ほか多数(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
-
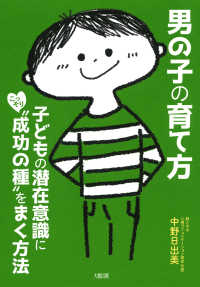
- 電子書籍
- 男の子の育て方(大和出版) - 子ども…
-

- DVD
- エレファント・マン