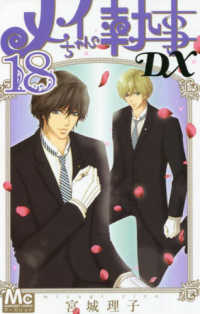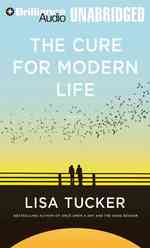出版社内容情報
〈国体のもとに帝国憲法は存在し、安保のもとに日本国憲法は存在することになった。しかも、国体の中核である天皇も、安保を動かす米国政府も、どちらも、たとえば「勅語」であれ、「ガイドライン」であれ、どれをとってみても国民は言うまでもなく国民代表(国会議員)も手を出せない「絶対的な最高の存在」である。あるいはまた、日本の指揮権は米国にあると考えられるが、帝国憲法下でも「統帥権」は天皇の専権であり、「統帥権の干犯」は許されなかった。つまり、国民から見れば明治期以来、天皇制も日米安保も、手の届かない遠い存在という意味では、近代150年を一貫していることになる〉
第九条を中心とする日本国憲法と日米安全保障条約。明らかに背反するこの二つの骨格を、背反しないかのようにして、占領期以後の日本は歩んできた。しかし子細にみると、「憲法も、安保も」ではなく、米国の要請に応えるかたちで「安保が第一、憲法は第二」となってきたことがわかる。
指揮権密約から安保条約および付属する日米行政協定、安保改正・沖縄返還交渉での核密約、日米同盟と有事法制、自民党の憲法改正案、安保を支える国体思想まで、「対米従属」という観点から、第一人者が戦後の日米関係を再検討する。
内容説明
指揮権密約から安保改正・沖縄返還交渉での核密約、自民党の憲法改正案、安保を支える国体思想まで。「対米従属」という観点から戦後の日米関係を再検討する。
目次
第1章 指揮権密約
第2章 朝鮮半島の有事密約
第3章 安保改正での核密約
第4章 沖縄返還と核密約
第5章 消えた自主防衛
第6章 有事法制下での対米従属
第7章 自民党の憲法改正案
第8章 安保を支える国体思想
第9章 「従属構造」を見据えて
著者等紹介
古関彰一[コセキショウイチ]
1943年東京生まれ。早稲田大学大学院法学研究科修士課程修了。獨協大学名誉教授。和光学園理事長。専攻憲政史。著書『新憲法の誕生』(中央公論社1989、吉野作造賞受賞)(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。