出版社内容情報
本書は自伝の形をとっているが、この社会への鋭い考察である。自由と平等を謳う階級社会。さらには労働者階級と投票、右傾化にも、特に深い分析がなされている。
著者はフランス北東部の都市ランスの貧困家庭に生まれた。13歳で工場勤めを始めた父、小学校を出て家政婦になった母。祖父母もまた極貧の労働者だった。しかし哲学や文学に傾倒し、自身の同性愛を自覚するにつれ、著者は家族から離反してゆく。一族で初めて大学に進み、パリの知識人とも交わるようになった著者は、出自を強く恥じる。ゲイであることよりも、下層出身であることを知られるのが怖かった。
嫌悪していた父の入院と死を機に、著者は数十年ぶりで帰郷する。失われた時間を取り戻すかのように母と語り合う日々。息子が遠ざかったことで、母は苦しんでいた。自ら去ったはずの息子も、別の意味で苦しんでいた。階級社会、差別的な教育制度、執拗な性規範という、日常的であからさまな支配と服従のメカニズムが正常に働く社会。本書はその異様さと、それがもたらす苦しみを、ブルデュー、フーコー、ボールドウィン、ジュネ、ニザン、アニー・エルノー、レイモンド・ウィリアムズらの作品を道標としつつ、自らの半生に浮き彫りにした。仏独ベスト&ロングセラー。
内容説明
パリの知識人となった著者は、父の死を機に数十年ぶりに帰郷する。結び直される母との絆。なぜ、あれほどまでに出自を恥じ、家族から離反しなければならなかったのか。あからさまな支配と服従のメカニズムが正常に働く社会の異様さを、自身の半生に浮き彫りにした仏独ベスト&ロングセラー。
著者等紹介
エリボン,ディディエ[エリボン,ディディエ] [Eribon,Didier]
フランスの社会学者・哲学者。1953年フランス北東部のランスに生まれ、ランス大学とパリ第1大学で哲学を学ぶ。『リベラシオン』紙、『ヌーヴェル・オプセルヴァトゥール』誌で文芸・思想記事の執筆者として長年活動後、カリフォルニア大学(バークレー)、ケンブリッジ大学などで客員教授を務め、2009年から2017年までアミアン大学教授。その後ダートマス大学モンゴメリー・フェロー(特別研究員)に選出された
塚原史[ツカハラフミ]
1949年東京に生まれる。早稲田大学名誉教授(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
おさむ
たま
ハルト
山のトンネル
hasegawa noboru
-

- 和書
- 一所懸命 〈上〉
-
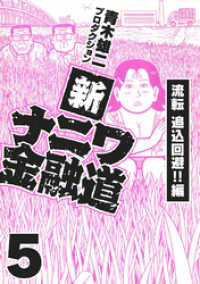
- 電子書籍
- 新ナニワ金融道5 SMART COMI…







