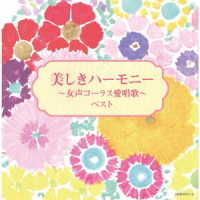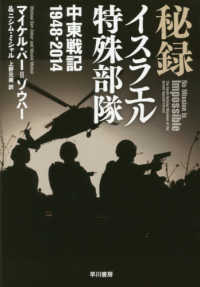出版社内容情報
古気候学の研究者と市民の熱意から生まれた、気候科学のエキサイティングな講義。古気候学とは、堆積物や氷床などに残る痕跡を手がかりに気候変動の歴史を復元し、地球環境を造形するメカニズムを明らかにする学問だ。その成果は地球の理解そのものを確実に変えつつある。本書では第一線で活躍する研究者が、生きた講義の中で発せられる疑問を丁寧に拾いながら、複雑で動的な地球システムの本質を説き明かす。
まず古気候学の面白さ、これが圧巻なのである。歴史と本物の科学がみごとに融けあっている。億年~数年という異なる時間軸を縦横に飛び移る思考。日本海から掘り出した堆積物と数万年前に極地を覆っていた氷床を関連づけるような、壮大なからくりの数々。研究者たちは過去の気候が遺した暗号を丹念に読みこなし、地球環境の頑健さと脆弱さの謎に迫っていく。
地球温暖化はウソかホントかといった表層的な議論はもうたくさん、今度こそ地球と環境の実像を掴みたいという読者に、この質の高いレクチャーを追体験してもらいたい。豊富な図版も紙芝居とは意味が違う。科学的根拠を自ら一つ一つ読み解く過程にこそ、「理学する」手ごたえがある。サイエンスカフェ参加者の探求欲にも感染せずにはすまない、充実の地球システム学入門。
内容説明
古気候学の研究者と市民の熱意から生まれた、気候科学のエキサイティングな講義。古気候学とは、堆積物や氷床などに残る痕跡を手がかりに気候変動の歴史を復元し、地球環境を造形するメカニズムを明らかにする学問だ。その成果は地球の理解そのものを確実に変えつつある。本書では第一線で活躍する研究者が、生きた講義の中で発せられる疑問を丁寧に拾いながら、複雑で動的な地球システムの本質を説き明かす。まず古気候学の面白さ、これが圧巻なのである。歴史と本物の科学がみごとに融けあっている。億年~数年という異なる時間軸を縦横に飛び移る思考。日本海から掘り出した堆積物と数万年前に極地を覆っていた氷床を関連づけるような、壮大なからくりの数々。研究者たちは過去の気候が遺した暗号を丹念に読みこなし、地球環境の頑健さと脆弱さの謎に迫っていく。地球温暖化はウソかホントかといった表層的な議論はもうたくさん、今度こそ地球と環境の実像を掴みたいという読者に、この質の高いレクチャーを追体験してもらいたい。豊富な図版も紙芝居とは意味が違う。科学的根拠を自ら一つ一つ読み解く過程にこそ、「理学する」手ごたえがある。サイエンスカフェ参加者の探求欲にも感染せずにはすまない、充実の地球システム学入門。
目次
第1回 地球の気候はどのように制御されてきたか(地表温度はどのようにして決まるか;全球凍結をめぐる謎)
第2回 地球は回り、気候は変わる(氷河時代と氷期―間氷期サイクル;ミランコビッチの仮説)
第3回 CO2濃度はどのように制御されてきたか(産業革命以前のCO2濃度変動;CO2固定のプロセス ほか)
第4回 急激な気候変動とそのメカニズム―『デイ・アフター・トゥモロー』の世界(急激な気候変動が北半球で起きていた;ダンスガード=オシュガー・サイクルに伴う変動の波及 ほか)
第5回 太陽活動と気候変動―太陽から黒点が消えた日(過去の太陽活動を知る;古気候と太陽活動 ほか)
著者等紹介
多田隆治[タダリュウジ]
1954年生まれ。東京大学大学院理学系研究科地球惑星科学専攻教授。専門は地球システム変動学・古海洋学・古気候学・堆積学(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
Ryoichi Ito
Dolphin and Lemon
nosime_tombo
モコトン
meiji